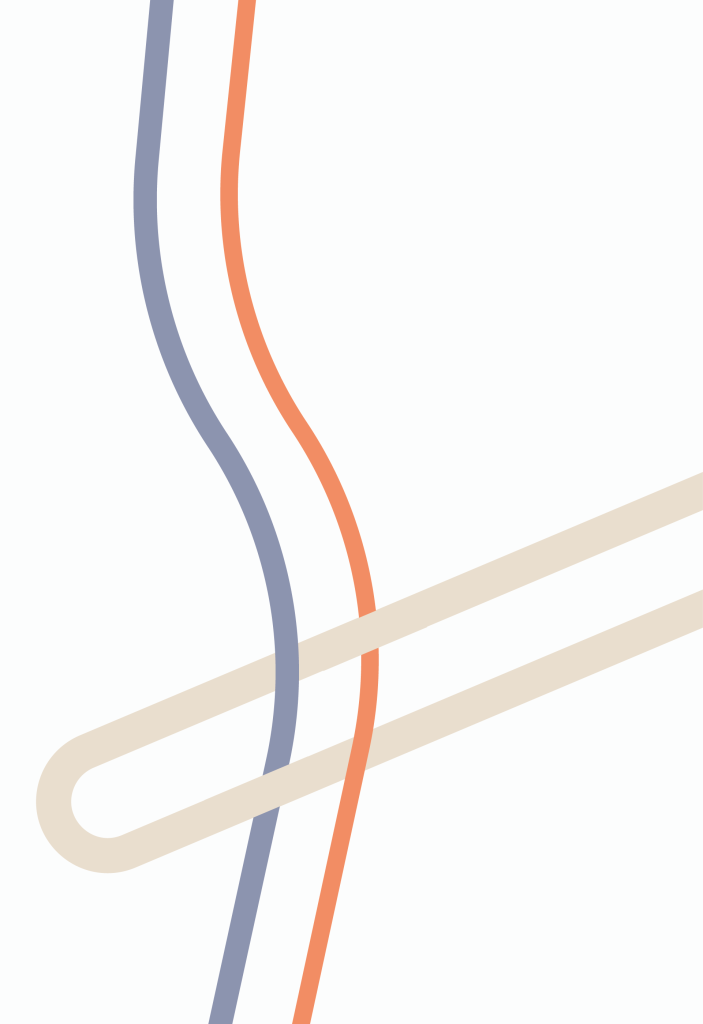文量:新書の約22ページ分(約11000字)
はじめに
古来より人間は、自然環境の様々なものに神が宿っていると考え、崇拝してきました。八百万の神は、その一つの例であると言えます。人間は、日々の営みを行う上で自然環境との関係性を意識的に築いてきたと考えられるのです。
しかし、16世紀から20世紀中頃までの近代社会では経済発展という名のもとに、人間の物質欲を満たすために、天然資源を大量に収奪し自然へ汚染物質を排出するなど、自然環境への負荷的な影響を強めてきました。これは、産業革命以降の工業化社会への発展過程で促進されてきた「大量生産-大量消費-大量廃棄」型の社会システムや、われわれ人間自身の消費嗜好に起因すると考えられます。
この近代社会における自然環境に対する人間の意識や行動は、古来の人間のそれとは異なると考えられ、自然環境に対する人間の意識は共生から征服へと変化してきたと考えられます。そして現代では、公害や地球温暖化をはじめとする深刻化する環境問題を受けて、自然環境(生態系)と人間文明(経済発展)とのあるべき関係性を改めて模索し始めています。
今回は、18世紀のイギリスの産業革命から現代にかけての自然に対する人間の意識やその関係性の変化を概観していきます。
本テーマでは、現代社会総合研究所理事長・所長などを務める、日本有数の環境学者の一人である松野弘先生にお話を伺いました。なお、このブックレットは、いただいたお話と後記する著書から学んだことをもとに、執筆や編集はリベルで行なっております。
松野弘先生
環境学者(環境思想論・環境社会論、博士(人間科学)、現代社会総合研究所理事長・所長、大学未来総合研究所理事長・所長、一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会副会長、岡山県津山市「みらい戦略ディレクター」等。日本大学文理学部教授/大学院総合社会情報研究科教授、千葉大学大学院人文社会科学研究科教授/千葉大学CSR研究センター長/地球環境福祉研究センタ-・環境研究部門長、千葉商科大学人間社会学部教授等を歴任。日本学術会議第20期・第21期連携会員(環境学委員会)。
〈著書〉
- 『「企業と社会」論とは何か』(単著、ミネルヴァ書房、2019年)
- 『現代環境思想論』(単著、ミネルヴァ書房、2014年)
- 『環境思想とは何か』(間著、ちくま新書、2009年)
- 『エコロジズム』(B.バクスター、松野弘監訳、ミネルヴァ書房、2019年)
- 『緑の国家』(ロビン・エッカースレイ著、松野弘監訳、岩波書店、2010年) など
執筆者:吉田大樹
「こころが自由であること」をテーマに、そうあるために必要だと思えたことをもとに活動しています。制約がありすぎるのは窮屈で不自由なのだけど、真っ白すぎても踏み出せない。周りに合わせすぎると私を見失いそうになるのだけど、周りは拠り所でもある。1986年岩手県盛岡市生まれ。
目次
- はじめに
- 第一章 産業革命期の民衆と自然環境
- 産業革命のはじまり
- 「大量生産-大量消費-大量廃棄」型社会の醸成
- 産業革命期の人々の環境意識
- 第二章 20世紀・産業社会における「豊かさ」の病理現象 〜公害・環境問題の深刻化〜
- 環境の価値をめぐる思想の対立
- 20世紀における環境意識の変化
- 第三章 近代の環境問題を経て生まれた、環境思想の登場
- 緑の国家論
- スウェーデンの実例
- 第四章 これからの、自然環境とのあるべき関係性とは・・・
第一章 産業革命期の民衆と自然環境
産業革命以降に発達した「大量生産-大量消費-大量廃棄」型の社会経済システムは、環境へ負の影響を与えてきました。
生産から廃棄までの過程では、原料や燃料として天然資源が消費され、汚染物質の排出も伴いました。その処理が適切でない場合はより直接的な環境汚染につながるため、公害などの問題を引き起こす要因となりました。このようにして、産業革命以降、人間は環境への負荷を急激に強めていったのです。
産業革命は、18世紀中頃イギリスから起こり、その後世界中へ波及していきました。ここでは、産業革命期のイギリスにおける生産体制や生活の変化を概観することで、環境へ負の影響を及ぼすに至った社会背景について、振り返ってみたいと思います。
尚、本章は松野弘先生からの知識やお考えの提供などは得ておらず、リベル側で独自に作成しました。産業革命の発端や当時のイギリスの社会環境や生活スタイルについては、『生活の世界歴史〈10〉産業革命と民衆』[1]を参考にしています。
産業革命のはじまり
イギリスで産業革命が起きたのは、木材の不足という社会的な課題が一つのきっかけであったと読みとれました[1,k252]。木材は、造船などの材料や製鉄などの燃料としての役割を持つため、不足すれば国力の低下や生活の不便が懸念されます。
そこで16世紀中頃イギリスは、木炭に替わって石炭を工業用・家庭用として広く一般的に使うようになっていきました。
石炭利用の一般化に伴い、その需要は拡大していきました。
拡大する需要に応えるためには、大規模且つ効率的に採掘しなければならず、その採掘過程において、特に炭鉱内の地下水の排水は大きな課題でした。当初は馬の力で揚水作業が行われていましたが、この方法では限界があります。炭鉱が地下水で溢れれば、その炭鉱での採掘は諦めなければなりません。
そこで開発されたのが、蒸気機関でした。かの有名なワットの蒸気機関が開発されたのは、1769年であったと言われています。
このように、木材不足という課題から石炭が使われ始め、その採掘にあたっての排水という課題から蒸気機関が生まれました。石炭採掘の他にも、石炭輸送の課題や石炭を製鉄工程に使う技術的な課題などが、さまざまな解決策により解決されていきました。
つまり産業革命は、機械の技術革新による生産上の課題解決の連鎖によって引き起こされていった、という側面があると考えられます。一つの課題解決でまた新たな課題が生まれ、その解決の過程で新たな技術が生まれるという、生産体制が目ざましく進歩した時代であったのだと想像されます。
このようにして大規模で効率的な生産体制が築かれ、工業化社会へと移行していったのです。
「大量生産-大量消費-大量廃棄」型社会の醸成
人々の生活も農耕型のスタイルから、産業型のスタイルへと変化していきました。
それまでは、各地方で農業や牧畜を中心とした生活をしていました。衣食住、そして仕事は、その農村の中でまかなわれていたのです。農村という閉鎖的な共同体の中で、祭りなどの娯楽、教会での教育、伝統的な行事なども完結していました。外の世界との交流によってお金で物や事を手に入れるということが今日に比べると少なかったのです。
そこに、産業革命により工業という新たな仕事が生まれました。人々は、農村を離れ、工場で働き、労働の対価として賃金を得ることになります。
そして、生まれ育った農村・共同体を離れることで(都市化)、他者が身につけている衣服や、所持している贅沢品などを意識し始めるようになります。新たな集団(都市社会)に所属するため、あるいは他者との差異をはかるために、それらを欲するようになっていったのです。
こうした生活様式の変化によって生み出された消費意欲は、商品の大量供給を誘引し、大量供給は贅沢品を含めた物の値段を下げていきました。
そして、物の値段が自分の手の届くところまで下がれば、人の消費意欲はさらに掻き立てられます。
さらに、それらの物を買うためのお金は、工場などでの労働の対価として得ることが出来ました。
こうして、今日に近い消費文化が、産業革命以降イギリスで急速に生まれていったと考えられるのです。
同時に、人口も急激に増えていきました(都市化の進展)。
公式の人口統計によるとイングランド地域とウェールズ地域では、1801年には916万人であった人口が、1851年にはその倍の約1800万人に増加したとされています。
そしてこの人口増加は、労働人口の増加により生産を後押しし、需要の増加にもつながりました。つまり、「大量生産-大量消費」をさらに促すことになったのです。
このような事象の連鎖により、「大量生産-大量消費」とそれに付随する「大量廃棄」という、今日的な大量消費型の社会システムが作られていったのです。
産業革命期の人々の環境意識
現代では、ゴミを分別して出すことは習慣化され、各家庭には上水・下水などのインフラが行き渡っています。トイレは水洗である場合がほとんどです。しかし、当時はそうしたインフラや社会的ルールもなく、行政などによる監視や規制もありませんでした。
産業革命期のイギリスの生活環境などを記した『生活の世界歴史〈10〉産業革命と民衆』[1]によると、当時のインフラや人々の環境意識は以下のようなものであったようです。
「一般に河の流れを下水代わりに使うことが多かったといえば、だいたい想像できるであろう。」[1,kindle2207]
「排水のよくないところでは、家々から外へ投げ捨てられる廃棄物で、道路はゴミ公害でひどい状態であった。」[1,kindle2210]
「比較的豊かな人びとは、部屋の中に室内用便器(おまる)をもち込み、朝になると、道路の中央を走る溝またはどぶまで運んで捨てた。二階から上に住む連中は窓から外に捨て流した。川沿いに住むものは、汚物を直接川に投げ込んだ。」[1,kindle2225]
このような、自然環境に対してだけではなく生活環境に対する配慮のなさは、現代では考えられないものです。その要因は、インフラや社会的ルールの未整備にあると考えられますが、それらが未整備であるがゆえに、環境に配慮する意識も乏しかったのではないでしょうか。
ここまで見てきたように、産業革命期にはさまざまな社会的課題解決の連鎖により、大規模且つ効率的な生産体制が整い、工業化社会(もしくは、産業化社会)へと加速度的に変化していきました。
その変化は、人々の生活様式にも変化を及ぼし、消費意欲を喚起し、また人口の増加も伴って「大量生産-大量消費-大量廃棄」型の社会経済システムを醸成していきました。当時の社会は、インフラや社会的ルールの未整備も相まって、人々の環境に対する配慮は乏しいものでした。環境に対する知識も、乏しかったと考えられます。
したがって、社会システム全体が変化することによって環境への負荷が増大している、という環境意識を持つことは困難であったと考えられます。
産業革命期は、環境問題という大局的な社会的課題へ目を向ける余裕もなく、日々の変化と目の前に起きる課題に対応することで、精一杯な時代であったのではないでしょうか。
第二章 20世紀・産業社会における「豊かさ」の病理現象 〜公害・環境問題の深刻化〜
イギリスから始まった産業革命は、1830年代にはフランス、40年代にはアメリカやドイツ、そして90年代には日本へ波及していきました。産業革命によってもたらされた社会の工業化は、都市環境や自然環境へ負の影響を及ぼしていきます。それによって20世紀に入ると、今度は人間が、自然環境から公害などの負のしっぺ返しを受けるようになっていきました。
そして、それらの環境問題を受けて、徐々に自然環境に対する意識を改め、人間と自然環境との関係性を再検討するようになっていったのです。
ここでは、自然環境に対する人々の思想対立の例や世界的に注目を浴びた書籍や報告書から、20世紀における人々の環境に対する意識の変化を見ていきたいと思います。
環境の価値をめぐる思想の対立
1908年、アメリカ・カリフォルニア州のヨセミテ国立公園にあるヘッチヘッチ渓谷をめぐって対立が起きました。
この対立は、地震等の災害時の貯水池と水力発電用の用地確保を目的として、この渓谷に大規模ダムを造る計画をサンフランシスコ市長が連邦政府に申請したことから起きました。
推進派の代表は、自然環境を資源として有効利用しようと考えるアメリカの森林局長官のギフォード・ピンショーでした。これに対して、反対派の代表は、自然環境は存在そのものが人間にとって価値があると考えるジョン・ミューアでした。彼は今日では有名な米国の環境保護団体「シエラ・クラブ」の創設者でした。
ピンショーは、「保全」(conservation)という概念を掲げ、保全は決して自然を破壊する行為ではなく、天然資源を賢明且つ効率的に利用する環境保全政策の一つの考え方であるとしました。具体的には、以下の4つの原則を示したのです[2]。
「第一に、保全とは、環境全体を管理することであって、たんに森林や草原や河川のみの管理ではない」「第二に、保全は、開発であり、現在この大陸に存在する天然資源を、現在ここに生きている人の利益のために用いることである」「第三に、保全は、天然資源の浪費を取り除くことである」「第四に、保全は、天然資源の開発と保存は多数者の公益のために行われるべきであり、単なる少数者の利潤のためであってはならない」
ピンショーの「保全」概念は、天然資源の有効利用や公共性という点では肯定的に捉えられますが、あくまでも人間の経済活動において天然資源は使用価値がある、という考えに立脚したものでした。
一方でミューアは、有効利用や経済活動という点には自然環境の価値を置いていませんでした。
ミューアは、自然により人間が精神的充足を得られる側面を重視し、自然環境は天然資源の貯蔵庫ではなく、日常生活の癒やしとなる神からの贈り物であるという自然環境への畏敬の念、すなわち審美主義的な考え方を持っていました。
人間にとっての自然の価値を「心身が癒やされ、励まされ、そして力を与えられる場所」[3]として、自然の存在そのものに見出していたのです。
これらの思想的対立は、ピンショーの「功利主義的自然観」と、ミューアの「審美主義的自然観」として整理することができます。
この対立は時の大統領を巻き込んだものとなりましたが、結果は「功利主義的自然観」を持ち保全概念を掲げるピンショーに軍配が上がりました。1913年の下院で、ダム建設が決定されたのです。
この決定の背景には、当時の一部巨大企業が天然資源を収奪することにより、自然環境に破壊がもたらされていたことが背景にありました。「資源の私的利用権の乱用を抑制し、環境資源の利用に際しての科学的な管理基準を設けようとする努力に、一般の人々が幅広い指示を与えた」[6]ということが、保全概念への賛同の要因でした。
ここで重要なことはその勝敗ではなく、20世紀前半の国家や人々は、自然環境はあくまでも人間にとっての資源であり、有効利用する対象であると見なしていた側面があるということです。
言い換えると、人間中心主義的な考え方(Anthropocetnrism)であったと言えます。
20世紀における環境意識の変化
20世紀には、ヘッチヘッチ論争のような自然の価値観をめぐる人間同士の対立だけではなく、自然そのものが人間社会に直接的に影響を及ぼすようになります。
1962年に刊行された、生物学者・作家のレイチェル・カーソンの『沈黙の春』(The Silent Spring)は、ヘッチヘッチ論争に見られた人間中心主義的な考え方から、自然環境自体に目を向ける契機となりました。
この著書は農薬などの化学物質の危険性を訴えたもので、それまであまり知られていなかった農薬の残留性や食物連鎖による生物濃縮のメカニズムを説明し、社会から大きな反響を受けました。
カーソンは著書の中で、それらの事実とともに、人間が自然をコントロールする愚かさを訴えたのです。ちなみに本のタイトルは、化学物質の撒布によって鳥たちが鳴かなくなった春の出来事を記していることに由来しています。
日本でも同じ頃、四大公害病が問題となっていました。
その中の一つである水俣病は、化学工業メーカーのメチル水銀を含んだ廃液の垂れ流しに起因するものでした。メチル水銀は、魚介類の食物連鎖によって生物濃縮し、それを摂取した地元住民に「メチル水銀中毒症」が発症しました。当初は「奇病」と呼ばれ原因の特定は容易ではありませんでしたが、その後原因が特定され、化学工業メーカーは被害者から訴訟を受けることとなりました。
環境問題が、人間の健康と、自分たちに原因があるとはいえ企業活動へも、直接的な影響を及ぼすようになっていったのです。
そして1972年には、ローマクラブの報告書『成長の限界 人類の危機レポート』(TheLimits to Growth)が発表されました。ローマクラブは、イタリアのフィアット社とオリベッティ社の経営者であったA・ペッチェイが中心となって、自然科学者や技術者、政治家などと共に1968年に結成されました。
報告書では、天然資源が有限である中で、経済発展と人口増加が同時に起きているという状況を分析し、「100年以内に地球上の成長は限界に達する」とまとめられました。また、経済的・社会的・生態学的に、持続的な均衡状態を達成するためには、国家や個人の価値観や目標の根本的な変更が必要であるということも指摘されました。
つまり、ヘッチヘッチ論争でピンショーが掲げた保全概念に見られるような人間中心主義的な価値観からの転換が必要であると指摘されたのです。
このように20世紀は、経済活動により自然環境を侵食することで審美的な価値を失うだけではなく、公害をはじめたとした環境からのしっぺ返しを受けてきた時代でした。
人間を中心に、あるいは上位に据えて、自然環境を功利的に利用することの限界がさまざまな書籍や報告書から指摘され、人間は自然環境とどう付き合っていくべきなのか、改めて考え始めることとなったのです。
第三章 近代の環境問題を経て生まれた、環境思想の登場
産業革命以降、人間社会は「大量生産-大量消費-大量廃棄」型の社会システムを整え、経済発展を志向してきました。そしてその結果、環境問題が生じ、その都度対策を講じてきました。
20世紀も後半になると、『成長の限界』レポートに代表されるように、経済発展志向型のシステムでは地球の未来には限界がくると認識されていきました。つまり、対症療法的に環境問題に対応するのではなく、根本的な社会システムの転換が必要であると考えられるようになっていったのです。
ここでは、その新たな自然中心主義的な社会システム論の提唱者である、オーストラリア・メルボルン大学教授のロビン・エッカースレイによる「緑の国家論」を紹介します。また、エッカースレイ自身が緑の国家に最も近い国の一つとして示したスウェーデンの実例についても紹介したいと思います。主に松野弘著『環境思想とは何か』[9]をもとに紹介していきます。
緑の国家論
「緑の国家論」(Theory of The Green State)は、人間が自然環境を利用するという人間中心主義的な考え方ではなく、自然環境(生態系)と共生するという生態系中心主義的な考え方に根ざしています。それは、今日の自然環境と人間文明との関係を価値観レベルから変えていくことを意味しています。
具体的には、まず脱産業社会に向けて、市民の従来の環境意識を変えること。その変えるべきとされた環境意識とは、すなわち、人間の方が自然よりも上位にあるという人間中心主義的価値観です。次に、意識が変わった市民が、自然環境と人間文明が共生するための環境運動を行動として推進していくこと。さらには、人間中心主義的な価値観を基盤とした社会制度(社会システム)の統治の仕組みを変革していくことです。
換言すれば、生態系中心主義的な価値観をもった「緑の市民」(Ecological Citizenship)が、生態系中心主義的な民主主義、すなわち、「緑の民主主義」(Ecological Decocracy)の確立に向けて、社会制度変革を行うことの必要性と重要性を提起しました。
つまり、社会を形成する人々自体の価値観と、その人々が運営する社会システム全体を見直す必要があると考えているということです。
これまでも、1980年代のドイツで登場した「緑の党」など、政治的団体が中心となって生態系中心主義的な政策検討(「緑の綱領」)がなされてきました。
これに対して「緑の国家」構想は、一部の政治的団体による検討や推進ではなく、生態系中心的な思想を持つ「緑の市民」から成る「緑の民主主義」によって「緑の政策」として環境政策を推進することで、「緑の社会=エコロジー的に持続可能な社会」を基盤とした国家、すなわち、「緑の国家」を形成することであるとされています。
では、生態系中心的な意識や価値観とは、どのようなものなのでしょうか。
エッカースレイは、環境政策の基盤として「緑の憲法」を制定することの重要性を説いています。「緑の憲法」では、「緑の国家」の基本的主張として、「人間の諸権利への責任のみならず、生物多様性や地球生態系の生命維持活動と安全性を保護していく責任」を宣言する必要があるとしています[9,P267]。そして政策規定では、国家や企業などが、倫理的配慮の対象として将来世代や人間以外の生物種まで含むことを付言しています。
つまりエッカースレイの提言する「緑の国家」とは、現代だけではなく未来を、人間だけではなく生態系全体を配慮し、人間も人間以外の存在(動植物等)も含めた「生命共同体」(biotec community)を形成していくことを前提としているのです。
スウェーデンの実例
エッカースレイは、「緑の国家」に近い国としてスウェーデンを挙げているそうです[9,P270]。
スウェーデンは、1991年に「生態学的な持続可能な社会」を目指すことを明確にしました。1996年には、それまでの人間重視の「福祉国家」から、人間と環境の双方を重視する「緑の福祉国家」への構造転換を図ることを主要政策目標としています。
具体的な政策の一部を、以下に紹介します。[9,P250]
- 「環境法典」の制定(1999年)
- 「持続可能な開発省」の新設(2005年)
- 「環境に関する15の政策目標」の制定(1998年/2001年)(例:清浄な空気、環境の酸性化を自然の範囲内にとどめる、持続可能な森林、良好な都市環境、気候変動の影響が少ない環境など)
- 「緑の福祉国家」への政策転換(対象:クリーンな生産体系、廃棄物処分体系、交通体系、エネルギー体系など)
そして、それらの政策は、具体的には以下のような形で実施されています。ここでは、その一部を紹介します。[9,P250]
- 「気候変動防止への対応」:1990年から10年間で、GDPが15%増加したにも関わらず、1999年の温室効果ガス排出量は1990年比で0.1%上回っただけであった
- 「税制の改革」:「CO2課税」(1991年)、「SO2排出税」(1991年)、「NOx排出税」(1992年)などの環境税を導入する一方で、所得税や法人は引き下げた
- 「エネルギー体系の転換」:原発を新設しないという政策を採用し、原発以外のエネルギーへの転換を推進していった
- 「持続可能な農業、林業」:「殺虫剤、人口肥料に対する特別な環境税の導入」、「伝統的に開発された農地、森林の保護」など
- 「都市再生」(都市再開発):持続可能な都市政策を推進していくために、「銅ぶきの屋根や鋼管の使用、塩ビ製品の使用禁止等の環境負荷の少ない再開発政策」、「エタノールやバイオガスを使用したクリーンな交通システムの構築」など
このように近年では、人間中心主義的ではなく、生態系中心主義的な思想を基盤とした国家構想である「緑の国家論」などが具体的に示されています。これは、産業革命期以降の近代産業社会がもたらした様々な病理現象に対する私たちの反省を踏まえて生まれた思想です。そして、そのような思想に基づく国家政策が実際に検討され、実行され始めているのです。
第四章 これからの、自然環境とのあるべき関係性とは・・・
木材不足を一つのきっかけとして始まったと考えられる産業革命は、その課題解決の連鎖により、大量消費型の社会システムを急速に築いてきました。当時は、急激に増える人口の消費や廃棄を支えるためのインフラや社会的ルール、または環境に対する知識は持ち合わせていませんでした。
ダム開発をめぐるヘッチヘッチ論争で人々が持った環境に対する意識の一つは、「保全」概念でした。これは、自然環境の天然資源は、経済発展のための有効利用の対象であるという人間中心主義的な考え方でした。
しかしその後、公害問題を起点とした深刻で多角的な環境問題が続き、『ローマレポート』に代表される「成長の限界」の可能性が厳しく指摘されるようになっていきます。
そして近年では、人間中心主義的ではなく、生態系中心主義的に社会経済システムを根本的に捉え直した「緑の国家論」などの思想が生まれ始めています。そして実際にスウェーデンのように、そのような思想を取り入れ実行している国家も出てきているのです。
ここで最後に、これからの環境とのあるべき関係性を考えるためのヒントとして、松野先生にこんな問いを投げかけてみました。
「今後私たちは、どのように視座で環境と向き合っていけばよいのでしょうか?」
松野先生:近年は、「持続可能性」(sustainability)という言葉がよく使われますが、何にとっての持続可能性を追求するのかを考えなければいけません。それは、人間の経済成長にとっての持続可能性なのか(Econmic Sustianability)、人間以外の存在も含めたすべての生命にとっての持続可能性なのか(Ecological Sustainability)、ということです。
例えば、電力のエネルギー源を火力や原子力にするのか、自然エネルギーにするのかという議論の際に、コストの問題が出てきます。しかし、コストを問題にしている時点で、経済成長にとっての持続性を追求している、ということが言えるのではないでしょうか。
確かに、今の便利で快適な生活を大きく変えることは難しいと思います。しかし長期的に見ると、産業革命期に築かれた大量消費型で右肩上がりの経済成長を続けることを目指す社会システムには、限界がきていると言えます。
これまでの環境問題が起きた背景を考えることで、今後どのような思想で環境と向き合うべきかは自ずと見えてくるのではないでしょうか。功利主義的に自然環境を利用するという考え方では限界は見え、審美主義的に環境を見ているだけでは新たな社会を築いていくことにはなりません。
現実的にいえば、中国は経済大国になりましたが、深刻な公害問題に苦しんでいます。これは今後、中国が克服しなければならない問題です。地球温暖化問題に代表されるような地球環境問題に、先進諸国も開発途上国も一緒に取り組んでいく必要があり、それは喫緊の重要な政策課題なのです。
これからは、生態系にとっての持続可能性、自然環境と人間文明との共生ということを基本的な思想として定義し、新たな社会システムを作っていくべき時代であると考えています。
(2019年9月16日掲載)
〈引用・参考文献〉
- 角山栄・村岡健次・川北稔著(1992)『生活の世界歴史〈10〉産業革命と民衆」(河出書房)
- R.F.ナッシュ著・足立康訳(1989)『人物アメリカ史(下)』(新潮社)
- R.F.ナッシュ著・松野弘監訳(2004)『アメリカの環境主義』(同友館)
- R.F.ナッシュ著・松野弘訳(2011)『自然の権利』(ミネルヴァ書房)
- R.F.ナッシュ著、松野弘監訳(2015)『原生自然とアメリカ人の精神』(ミネルヴァ書房)
- C.R.ハムフェリー・F.H.バトル著・満田久義他訳(1991)『環境・エネルギー・社会』(ミネルヴァ書房)
- R.エッカースレイ著・松野弘監訳(2010)『緑の国家』(岩波書店)
- J.J.カッシオ-ラ、松野弘監訳(2014)『産業文明の死』(ミネルヴァ書房)
- 松野弘著(2009)『環境思想とは何か』(ちくま新書)
- 松野弘著(2014)『現代環境思想論』(ミネルヴァ書房)
そろそろほんとに、対立を終わりにしなければいけない時なのかもしれない。 #リベル