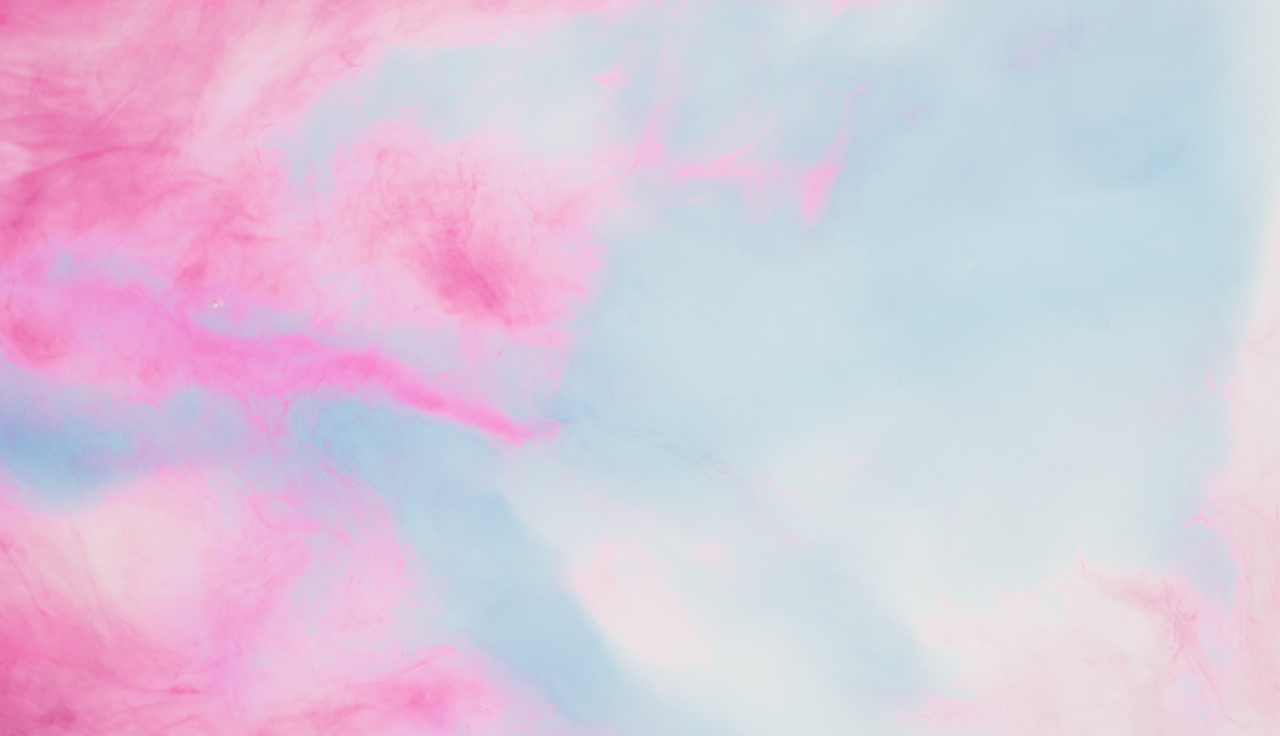
(文量:新書の約12ページ分、約6000字)
世界の見え方は、どのように創られているのでしょうか。眼の網膜に写っているものはみな同じなのかもしれません。しかし、「世界がどのように見えているのか」は人によって違うように感じられます。将棋盤をひと目見ただけで筋のいい打ち手が見える棋士や、ひとつの体験を広がりと奥ゆきをもって表現する作家、世の常識に反することをあたかもそれが当たり前であるかのように滔々と語る起業家や研究者など。目の前にある物体や、直面している体験や事象は似たものであるはずなのに、どうにもその人にとっては違うものに見えているのではないかと感じることがあります。
そのような違いは、どのように生まれるのでしょうか。わたしたちの世界の見え方に対する変化は、何によってもたらされるのでしょうか。
それは、もしかしたら日頃つかっている言葉に対する気の遣い方が、ひとつ影響してくるのかもしれません。今回は今井むつみ氏の『ことばの発達の謎を解く』[1]から学ばせていただきました。世界の認識の仕方を、子どもが言葉を覚える過程を交えながら考えることができました。
生まれてから世界を認識していくまで
生まれて間もないとき、物事をどれだけ適切に捉えられているのでしょうか。おそらく、目に写るものが全て違うものとして五感で察知されているはずです。目の前に現れる人も動物も植物も、まったく同じものを目にすることはないからです。しかしそれらは、認識としては、違うものとされていないのかもしれません。人の認識がどのようにつくられていくのかを、赤ちゃんの言葉の覚え方からみていきたいと思います。
赤ちゃんが言葉を覚え始めるとき、普段からよく見ているものから口にし始めます。たとえば、「ワンワン」です。外で見かけるイヌは子どもにとってはなんとも魅力的で、噛まれたらどうしようという親の心配など尻目にどんどんと近寄っていきます。親は、「あれはワンワンだよ」と教えます。一度で覚えることは困難ですが、出かけるたびに見かけるイヌを、次第に指差して「ワンワン」と呼びはじめます。どうやら、あれはイヌ(ワンワン)なのだと認識したようです
しかし次の瞬間、こまったことが起こります。道端で昼寝をしているネコを指差して「ワンワン」と呼ぶのです。さきほどは確かにイヌのことをワンワンと呼びましたが、この段階で本当に、イヌをイヌとして認識したと言えるのでしょうか。おそらく、その答えはNoです。この段階では、四足歩行で歩くヒトの膝下程度のサイズ感の、毛むくじゃらの動物全般をイヌと誤認しているようです。
ネコのことを「ワンワン」と呼べば、周りにいる大人は「違うよ、あれはニャーニャーだよ」と教えます。それでもしばらくは「ワンワン」と呼び続けますが、次第に子どもの口が重くなり始めます。どうやら、「ボクがワンワンと呼んでいるものの中にはワンワンじゃないものがあるのかもしれない」と思い始めるようです。そして、観察するような素振りを見せるようになっていきます。でも、なかなかニャーニャーとは言いません。イヌとネコを分けて認識することは相当に困難なようです。それに対して、ゾウのことは、さすがにワンワンとは言わず、比較的すぐに「ゾウ」と呼ぶようになります。まずはゾウのようなイヌとは明らかに違う生き物を認識しながら、徐々にネコのような類似性の高い生き物の違いを認識していきます。
既に違いを認識できる大人が、必ずしも違いを教えられるわけではありません。なぜなら、たとえば「ネコは目が少しつり上がっているでしょ」と教えようとしても、「目」という言葉も「つり上がる」という言葉もまだ分からないかもしれないからです。しかし、そのような説明なくしても子どもは次第に違いを認識していきます。凝視するように観察し、他のものとは違う特徴を自分の中で見出しながら、「分かった」と言える状態がある瞬間に生じるのです。他者の力も借りながら、しかし最後には自分の中で、世界にあるさまざまなものをそのものとして認識していくのです。
言葉でしか分かり得ない違いがある
イヌとネコの違いを認識したとき、同時に「世の中には一見同じように見えても違うとされるものがある」ということも認識します。もちろん、そんな小難しいことを実際に口に出したりはしませんが、一つの単語を覚えるだけではなく、そうした抽象的な学習も同時に進んでいきます。あるいはそれ以前に、「どうやらこの世界では周囲にある物体や事象を、微妙な音の違い(=言葉)によって表現している」ということを、赤ちゃんは認識したことでしょう。これも、もちろん口に出して言ったりはしませんが。
日々くりひろげられる言葉との対峙の中から、子どもはひとつの抽象的な理解に達することがあります。そして、抽象的な理解に達すると、一気にその先の学習が進んでいくようです。たとえば、前述した「物事の違い」や「言葉という表現システム」に対する理解も、その一つなのだと思われます。そして、さらに挙げるとするならば、数字もその一つであるようです[1,kindle2141]。
数字を口にしない赤ちゃんでも、数の概念は持っているのだといいます。たとえば、2枚のクッキーが入った箱と3枚のクッキーが入った箱を、まだ数字を話せない赤ちゃんの前に置くと、3枚のクッキーが入った箱に近寄っていくそうです。クッキーがより多く入っている箱を認識できるようなのです。しかし、3より大きな数は、正確には認識できないといいます。4と5は明確に違うと認識することができず、大まかに同じ数として認識するようです。しかし、4と8のような大きな違いは認識できるようです。
このような赤ちゃんの数に対する認識のあいまいさは、発達の未熟さによるものだと思われるかもしれません。しかし、そうとも言えないようなのです。世界には、数字を言語の中に持たない民族がいます。アマゾンの奥地に生きるピラハという民族は、1と2に対応する言葉しか持っていません。この民族に、ある実験に協力してもらいました。それは、ピラハの人の肩を叩いた後、同じ数だけ肩を叩き返してもらうというものです。すると、3回よりも多い回数では適当になってしまい、正確な回数を叩き返すことが困難だったようなのです。つまり、ヒトは本来、3くらいの数までしか認識できないと言えるのではないかと考えられるのです。ではなぜ3よりも大きな数字を普段から問題なく扱えているかという疑問は、数字の学習過程を知ることで解けていきます。
数字はどのようにして覚えるのでしょうか。1や2という数字は、イヌやアリなどの物体と違って、目の前に存在しません。しかし、ものの数は認識することはできます。数字をまだ喋れない赤ちゃんでも、3までなら違いを認識できるのでした。この認識の力をつかって、少しずつ数字を覚えていくのだといいます。まずは、一を覚え、次に二を覚えます。しかし最初は、二は、一よりも多いもの、という漠然とした認識なのでそうです。そこから次第に、三や四というものに触れるなかで、二は一よりも一だけ多いもの、ということを理解していきます。そうなると、三は二よりも一だけ多いもの、四は三よりも一だけ多いものというように、どんどん大きな数字を覚えていくことができます。数字という言葉の意味を抽象的なレベルで理解した後は、呼び方を覚えていくだけでよくなるのです。こうして、一気に数字の学習スピードが上がっていきます。あるいは、理解に至る前でも学習は進んでいて、あるとき一気に学習の結果が表に現れてくるという方が正しい言い方なのかもしれません。
そして、数字という道具を手に入れることで、本来は3くらいまでしか認識できなかったのが、数をどんどんと刻むことで、100や1000、1億や1兆という莫大な大きさまで認識を拡大していくことができます。数字を得るまでは漠然と大きな数としか認識できないものが、100と101、100,000,000と100,000,001などの区別が正確に行えるようになるのです。数は、数字という言葉があってはじめて、3よりも大きなものを扱えるようになったと言えます。
このような、言葉があって初めて認識できるものは、数だけではないと思われます。
突然ですが、イルカはサカナでしょうか?おそらく多くの人は、イルカはサカナではないと答えられたのではないでしょうか。そして同時に、イルカはサカナではないことを初めて知ったときの驚きの感情も、思い出されたかもしれません。
子どもの頃、水族館などで水中を颯爽と泳ぐイルカは、他のところで泳いでいる魚たちと同じ、サカナであると思ったことでしょう。しかしある日言われるのです、「イルカはサカナではない」と。そしてさらに言われます、「人間の仲間なんだよ」と。生活スタイルも見た目も、明らかにサカナ寄りのイルカが人間の仲間であるとは一体どういうことなのかと、半ば混乱します。しかしこれは、パニックになるというよりは、好奇心が吹き出すような興奮状態に近いものだったかもしれません。
イルカは哺乳類であると教えられます。どの段階でイルカがサカナでない事実を知ったかは人によって違うでしょうが、人間もイヌもゾウも哺乳類であると学んだ後であれば、どのような疑問が生じるでしょうか。「ということは、イルカは肺呼吸?」「どうやって水中で生きているの?ボクなんか1分も息をとめられないのに」「そういえば、そもそもなんでサカナは水中で呼吸できるんだっけ?」「哺乳類って全部地上で生きているわけではないんだ。なんで水中と地上に分かれてしまったんだろう」などなど、疑問は尽きません。
このような驚きや疑問が生まれるのは、わたしたちが「サカナとはこういうものである」という認識を、あらかじめ持っていることに端を発するのだと考えられます。サカナは他の生き物とこういうところが違くて、こういうところが同じ、そしてサカナ同士はこんなところが同じなどと違いや同じ点を認識しているからです。そこにイルカはサカナではないという新事実が入ることで、サカナの認識を新たにしなければいけなくなります。水中で泳ぐサカナっぽい形の生き物全てがサカナというわけではないと知るのです。哺乳類は全て地上で生きているわけではないということも知ります。そして、魚類や哺乳類の間に引いていた自分なりの境界を引き直したり、それぞれを決める要素を足したり引いたりしていきます。この過程で新たに分かっていくことも多くあることでしょう。こうして、世界の見え方がまた少し変わるのです。
イルカはサカナではないとは、イルカを他の魚と比べながら観察しただけではおそらく分かりません。これは子どもに限らず大人に関しても言えることでしょう。大人になったからといって、イルカは哺乳類だという知識なくして、イルカはサカナではないと認識することはほとんどの人にとっては困難です。どこかの生き物を見る目に長けた人物が、イルカは哺乳類であると結論づけたのです。それ以前には、哺乳類や魚類という分類をつくった人もいたことでしょう。
これらの細かい分類や違いに対する理解は、魚類や哺乳類という、イルカやイヌなどといった個別種よりもさらに抽象度の高い言葉がなければ認識することが困難です。見た目に分かりやすい個別種の違いに比べて、哺乳類などという括りは何段階か抽象的で複雑だからです。このような複雑な認識には、4以上の数の認識が数字なしでは困難であったように、言葉による思考や定義づけが不可欠であったと考えられます。誰かが哺乳類という分類を言葉で定義し、また哺乳類というものをわたしたちが理解していたことで、イルカが哺乳類であると言われた時にさまざまな疑問が噴出したのです。そして、一つ一つの疑問を解消していきながら、イルカに対する理解をより適切なものに修正することができました。
言葉は世界をより詳しく細やかに認識するために使われています。そして、言葉を通して物事の認識が人々のあいだに広がっていき、それを土台にしながら考えたり生かしたりして新たな発見や発明につなげてきたのだと考えられます。人は言葉とともに世界を認識していっていると言っていいのでしょう。同時に、わたしたちが生来もつ、物事を識別したり記憶したり思考したりする能力を、強力に補助してくれる道具であるとも言えるのです。
抽象が飛び交う大人の世界
いつからか、言葉に困ることはなくなっていきます。イヌとネコの違いなど問題なく見分けることができるようになり、ものの性質を表現する形容詞を使い分け、動作を多様に表現する動詞もいくつものパターンを習得していきます。日々の出来事の共有や他の人への指示出しなども問題なくこなせるようになりました。
しかし、今使っている言葉は、本当に理解していると言えるものばかりなのでしょうか。小さい頃から使っていた、目の前にある具体を表すような言葉は理解していると言えるのかもしれません。しかし、学習過程が進んだり、会社に入って仕事を始めたりすると、抽象的な概念や言葉が多く登場するようになります。かつて手触り感をもってひとつひとつ認識していった言葉とはちがい、いきなり降ってくるように目の前に登場するのです。それでも、様子を伺いながらなんとなく使うことはできます。しかし、それは本当に言葉を有意義に使えていると言えるのでしょうか。新たな言葉に出合ったとき、一見似ている他のものと何が違うのか・何が同じなのかを自分なりに咀嚼していって、はじめて分かったと言えるのでした。そして土台にできるほど明瞭に認識することができれば、そこに思考を重ね、次なる一歩を見つけていけるのだと思います。
イヌはネコと違うと言われたとき、おそらく一生懸命その違いを分かろうとしていました。それは苦しいものというよりは、好奇心がくすぐられるままに動いていた気がします。イヌやネコを何度も指差して、「これは?」と聞き続けていたのです。
大人になると忙しくて、なかなか言葉に気を遣うことは難しいですが、自分に関心がありそうな何かひとつでも認識を深めてみると、世界の見え方がまた少し変わるのかもしれません。言葉をあいまいなまま使うのは、もったいないことなのではないかと、言葉を覚え始めた頃を思い浮かべて、思ってしまいました。
〈参考図書〉
1.今井むつみ著『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)
(吉田)