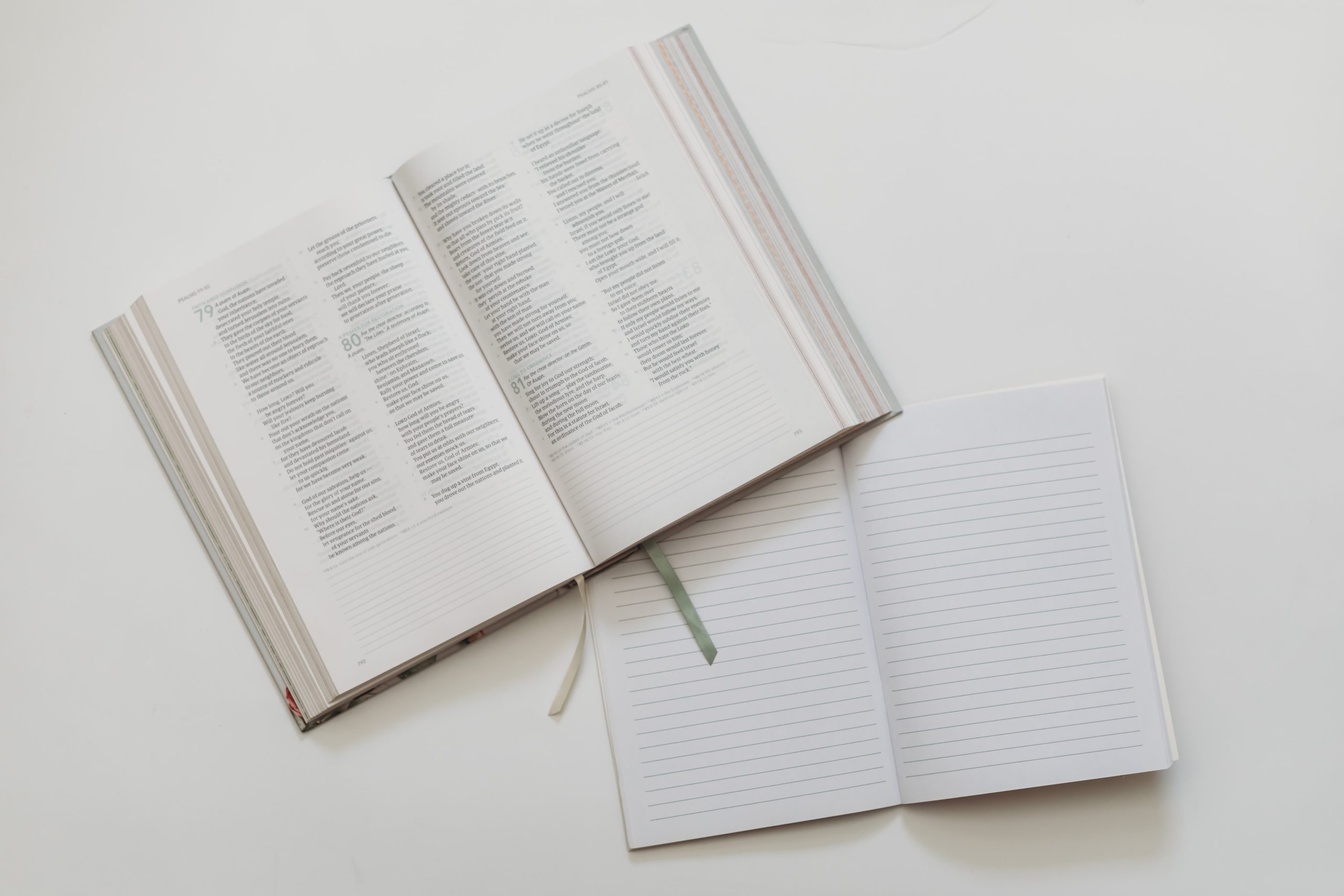
リベルの文化祭でいただいた感想を掲載します。
2025年 初夏 6月8日(日)
今だから話したい、村上春樹のこと
かよさん
皆さんの村上春樹の観点を聞けて、楽しかったです。
「村上春樹の小説は ときどきロールシャッハ・テストである」
「村上春樹が小説を書くことは箱庭療法なのではないか」
この視点が、特に興味深かったです。
ありがとうございました。
yuさん
村上春樹のことを話すのは怖いところがある。苦手が好きに転じて読んできたので古いとかいろいろ言われると自分が責められた気持ちにもなるところがある。なんでなんだろう。このイベントにあたり、「風の歌を聴け」「午後の最後の芝生」「街とその不確かな壁」の短編。新しく読んだような気分にもなる。深読みは難しいのでみなさんと話して影の意味や魂の話など時間が足りないくらいでした。司会や発表の方、ありがとうございました。
よしださん
会の後のフリートークで、村上春樹は漢方薬みたいなところがあるということを聞いたのが印象的でした。たとえば、朝井リョウの『正欲」は最後にガツんと打たれるようなところがあり、自分のもつ世界観が揺らいだりします。村上春樹にはそういうところがあるのか、つまり最後まで読めばあっちから何かを明確に伝えてくるようなことはあるのか、と聞いてみたらそのような回答が。まだ、村上春樹の初心者、『ねじまき鳥クロニクル』の第一部しか読んでいませんが、長く付き合っていきたいと思います。
私のいちおし銘菓
yuさん
お菓子は好きなんですが食べ過ぎるのは良くないとセーブしているところでした。銘菓っていうと箱入りのその土地の名産品?。ケーキ屋のお菓子とはまた違った感じ?思いつかないと初めは思っていましたが話し始めるとかるかん饅頭、白玉饅頭、かすたどん、青島の外郎、鬼瓦も中、草木饅頭・・出るわ出るわ。紹介のお菓子を全部食べてみたくなりました。草加せんべい、南部せんべい・・お菓子は人の心を和ませる力があると思いました。
よしださん
僕が紹介したのは、「山ぶどう」。小さい頃よく食べていたから出身地の銘菓だと思っていたら、斜め下の県の銘菓であることが判明しました。でも?、参加者の誰も知らない銘菓だったので、すこしうれしい。のだけど、他の方の紹介した銘菓も全然知りませんでした。お菓子って大きなメーカー以外も本当にいろんなところが作っているなぁ。長く残っている銘菓は、素朴だけどおいしい、飽きがこない、そんなものなんだろうなとラインナップを見て思いました。マイナーアップデートは密かにしていたりするのだろうか。
退屈で、退屈で、しょうがいないんですけど。
yuさん
退屈・・暇・・。贅沢な悩みだ!と初めは思いました。予定が詰まっていても退屈。いろいろな場所に行っても退屈。解消する必要はあるのか。暇と退屈は悪なのか!話せば話すほど聞けば聞くほど訳がわからなくなる根深い問題だなあと思いました。あの本を読んでも解決するわけもなく、理解できるわけもなく永遠に悩み続ける?のでしょうか。
Satoshiさん
色々と考えを深める機会となり、ありがとうございました。
長文になりますが、「暇と退屈」について参加した中で私の感じた事をまとめてみましたので投げさせて頂きます。
暇と退屈の出所は、「生(なま)の感覚への欠乏感」なのではないか。「暇と退屈」の対極は「生の感覚で行為している状態」。
「生の感覚」とは、目の前の現実に神経(感覚)が集中している状態であり、感覚器官・思考器官・身体器官等が「今」に統一されている状態。集中している状態と言えるだろう。 危機的状況・凄く興味を持って行為している状況等の集中状態。極まるとゾーンに入る。(因みにゾーンは集中とリラックス両方極まった状態。)熟練者の瞑想はこれを作り出せる。
そして集中状態は端的に内発的でしかあり得ない。
現代社会では自らの内発的行為が作り出しにくい状況が多く見受けられる。外因的なやるべき事、やらされ仕事、自分の納得に関係なく、他人が決めた法律・道徳・倫理の遵守等。
真に自分がやりたいと思うこと、やるべきと思えることをやっていないときに特に「暇と退屈」を感じるのではないか。
「生の感覚」への渇望への影響が考えられるものとして、
・自分探し(正に生の感覚探し)
・ホラー、怖いもの見たさ(恐怖という生の感覚)
・依存症全般(刺激による果てない生の感覚の渇望)
・窃盗などによるスリル(失敗出来ない集中による
生の感覚)
・性犯罪(スリルや、欲望という生の感覚)
・背徳感(背くスリルの生の感覚や、外因性への抵抗)
ここに、成功体験による報酬系の刺激等が絡んで来る。
この他にも大したこと無いことから、実害の大きいものまで、現代社会にはかなり多くの事に関連していると考えられる。「生の感覚の渇望」を何かに転嫁することで、捻れた感情が生まれる。
「暇と退屈」を感じることは「生の感覚の欠乏サイン」かもしれない。そんな時は自分と向き合い、本当にやりたいこと・やるべきと思うことをやっているのか、今目の前に有る状況でそれは作り出せないのか、それが難しい状況ならば趣味や別の行為で「生の感覚」を感じられる状況が作れないのか。
まとめると普通の事を言う形になるが、このような自己分析とそれに基づいた行動が必要になるのかもしれない。
よしださん
退屈というのは案外難しいです。感じたいか感じたくないかと言われれば感じたくないもの、明らかなのはそんなところくらいでしょうか?退屈と戦うことを表現するような文学作品もあるような気がしていて、それでは退屈に敗北すると大体変な方向に進んでしまう。敗北ってなんだ?という感じもするけど、退屈とはただ時間があってやることがないことではない。やることがあっても退屈に感じることはある。
戦地に赴いていれば退屈など感じないだろうと言われて納得しつつ、それであえて戦地とはいかないまでも戦いに身を投じたり戦いを引き起こしたりする人もいるのではないかと思ったり。それも一つの生き方なのだろうけど、そんな生き方は望んでいないのだけど社会のそういう雰囲気に巻き込まれているようなこともあるのではないかと思ったり。
人は生きるというのは奥が深い、深すぎる。深いし大変なこともあるけど、そこからはなんとなく逃れられないと思えば(例えばAIが仕事を代替しても新しい仕事が始まるだけ)、その大変なことが変なストレスは生まなくなる。変なストレスとは、「こんなはずではない」というストレス。こんなもんだよねと思っていれば「こんなはずではない」というストレスはなくなる。退屈もみんな感じるものでそんなに簡単に払拭できるものではないと思っていれば、長い目線でこつこつ解消の方向に向かうのではないだろうか、どうだろうか。
2024年 秋 11月3日(日)
ドストエフスキーとその作品の魅力
yuさん
マルメラードフの「自分は神に許されないと思っているからこそ神にゆるされる」は親鸞聖人の「悪人正機説」に通じるものがあるなと感じました。マゾッケがないと読めないのではという意見が面白かったです。少年イリューシャの飼い犬の名前はなんだったか昨日から考えていました。「貧しき人々」「地下室の手記」「悪霊」・・ドストエフスキーを読むきっかけになりそうです。
jscripterさん
ドストエフスキーはずーっと気になっているが、なかなか読めない作家です。問題意識をどう持つかに掛かっているのですが、今回の読書会に参加させていただいたおかげで、少し見えてきました。「悪霊」をまず読んでみると同時に、ニーチェの書簡集にドストエフスキーが出てくるそうなので、そちらも当たってみようと思います。
よしださん
僕はドストエフスキーの作品を読んだことがありませんが、おもしろくみなさんのお話を伺っていました。印象的だったのは、やはり(?)「なぜドストエフスキーを読むのか?」→「頭がおかしくなりたいから」という意見でしょうか。話が長くて、それぞれの登場人物のなかに矛盾があって、所作もおかしかったりするから頭がおかしくなる?ようです。その矛盾と複雑さに徐々にシンクロしていくということでしょうか。僕も科学書なり哲学書なりで常識を覆されたときに呆然としながらも楽しいと思ってしまう、その感覚に似ているのでしょうか。『悪霊』か『罪と罰』あたりを読んでみたいと思いました。
秋といえば、保存食についてシェアする会
よしださん
梅干しを漬けている人が思ったより多いかも?と驚きました。もちろん、このような会に参加される方だからというのもあると思いますが、そういえば私の実家でも漬けている…。
干し柿は甘い柿だと水分が多くて干される前に腐るから渋柿しかできないはず、などというのは初耳の知識でした。そういえば、干すことで渋みも取れるはずで(正確には皮を剥くということが重要なようですが)、渋柿の最適な食べ方として保存食・干し柿のあるのだと受け継がれる知恵の偉大さを感じました。
いずれにしても、今年も柚子胡椒をはじめ、なにか保存食を作っていきたいなと思いました。いろいろな調理法を試行錯誤の上(そして数々の犠牲も…)確立してきた先人たちに感謝です。たしかに、ふなずしを最初に食べた人はどんな感想をもったのだろうか。
「労働」をテーマに話し合う会
よしださん
労働という多くの人がどこかで関わる概念(?)について話しました。賃金が発生する労働とそうでない労働がある、生活の糧と割り切って労働はするけど他にやりたいことがある、そんないろいろな話が飛び交いました。
言葉としては1つなのだけど、それぞれの人が思っていることは違う。これがリアルなのであって、現実というのは本当は多様で複雑であってこれこそリアル、という感じの時間であったのだと今振り返ると思います。