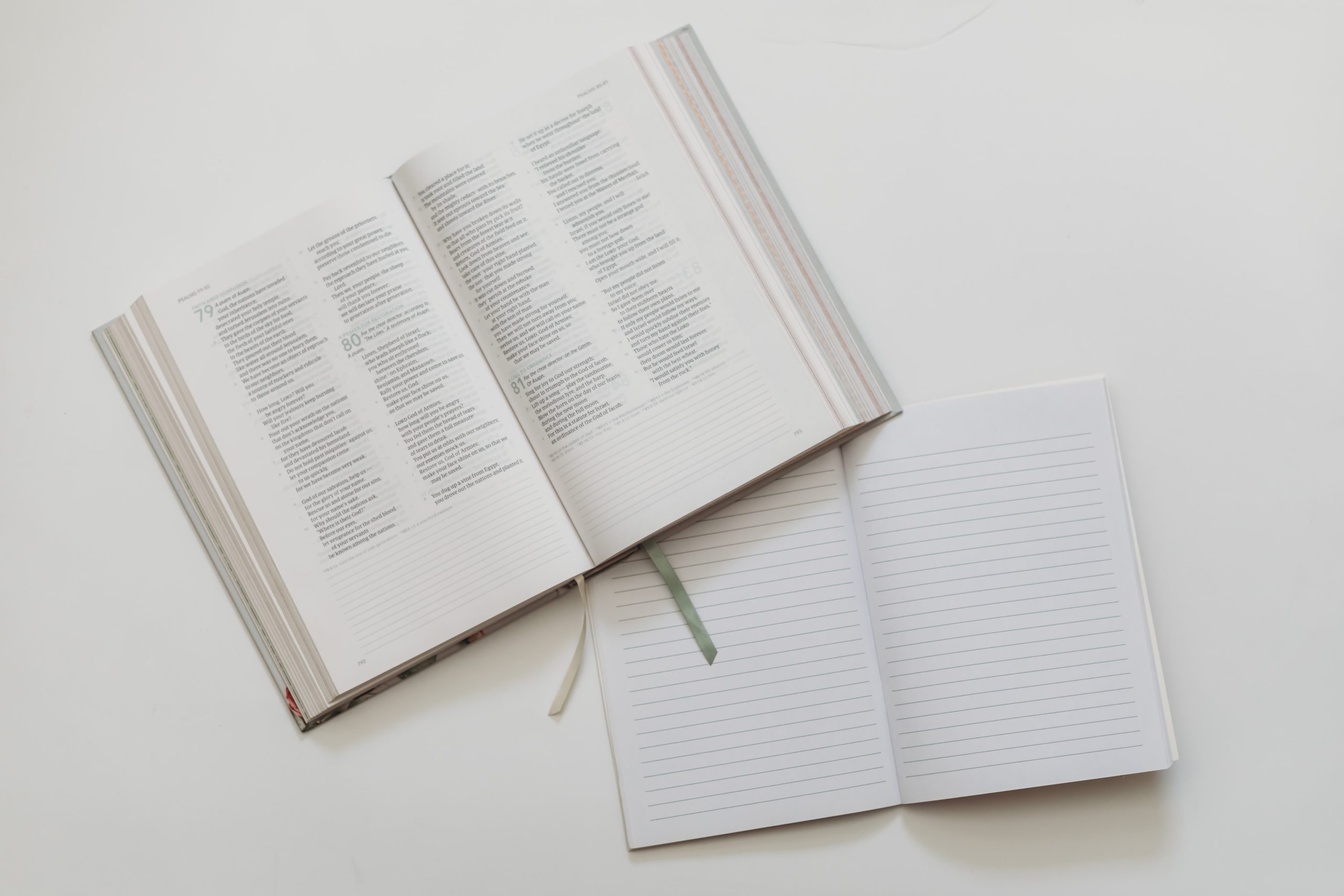
参加者に任意でいただいた読書感想を掲載します。12日(水/午前)は3名、15日(土/午前)は4名、16日(日/午前)は4名、16日(日/夜)は6名の参加でした(主催者含む)。
土曜日の「質問「 」について考える時間。」の質問はこちらでした。
自分の名前に満足してますか
田中未知著『質問』(文藝春秋)
2月12日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『神は、脳がつくった 200万年の人類史と脳科学で解読する神と宗教の起源』E・フラー・トリー
今回は宴会の重要性について(?)。1万8千年前には複数の小集団がある時期(季節)に集まって、協力して狩猟した痕跡があるのだといいます。これはごく普通のことに思われるかもしれませんが、いくつかの点で画期的な進化的変化である言えます。
まず、「ある時期」ということは前々から計画していたということで、計画と実行の能力が備わっていたということ。そしていくつかの小集団が集まるということは、他者の考えを慮ることがより必要とされたということであり、それができていた可能性が高いということです。
そして、そのような変化を伴いながら、1万1千年前頃のものと思われるギョベクリ・テペという大規模な遺跡がトルコの南西部にあるのだそう。そのギョベクリ・テペは宴会場だったのではないかというのです。
人が集まり協力をするとき、宴会や祭りが必要だということなのでしょう。ギョベクリ・テペが最初から宴会場的な目的で作られたのか、後々そう使われるようになったのかは分かりませんが、太古の大きな労働力を費やした先に宴会場になるということには宴会への合理性をみたような気になりました。
2月15日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『神は、脳がつくった 200万年の人類史と脳科学で解読する神と宗教の起源』E・フラー・トリー
神への信仰は、祖先崇拝から始まったというところを読んでいました。
人類の進化によって、省りみることができるようになったり、イマ・ココ以外の世界を想像できるようになったりして、死後の世界を思考できるようになったというのは分かります。でも、それがなぜ祖先崇拝につながっていくのかは今いち理解できていません。あっちの世界でも元気に、というのであれば他者の気持ちを考えるということで、分かります。でも、崇拝までいくのはなぜなのか。それはやっぱり、先を考えられるようになって生じるようになってしまった未来への不安を、長く生きた祖先に導いてもらおうということだったのか。
そうなると、祖先崇拝の延長線上に年功序列があるのか、などとも想像が巡ります。
2月16日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『灰色のミツバチ』アンドレイ・クルコフ
ウクライナの紛争地域、狙撃兵と地雷に囲まれ、誰もいなくなった緩衝地帯《グレーゾーン》の村に暮らし続ける中年男ふたりの話。幼馴染だけど仲良くなかった2人。弱い立場のほうしかそれって覚えていないよねと思いながら。
過去の読書感想はこちらに載せています。
〈読書会について〉
事前読書のいらない、その場で読んで感想をシェアするスタイルの読書会を開いています。事前申込をあまり求めない、出入り自由な雰囲気です。スタンスや日程などについてはこちらをご覧ください。