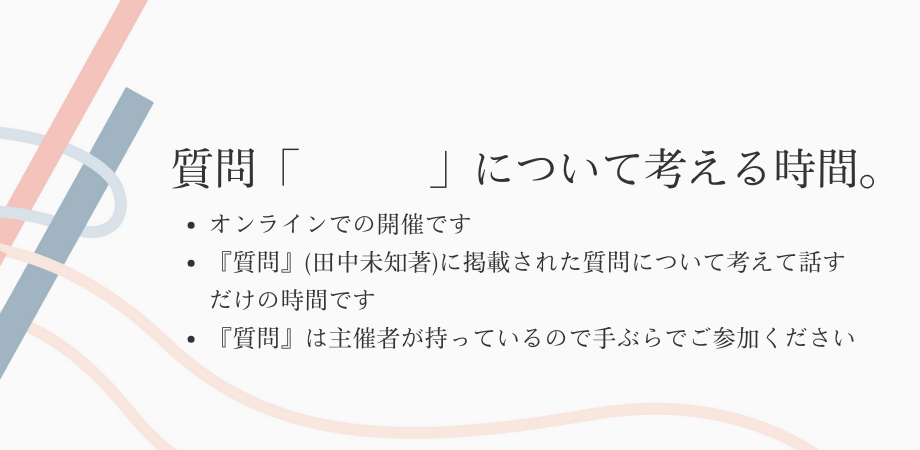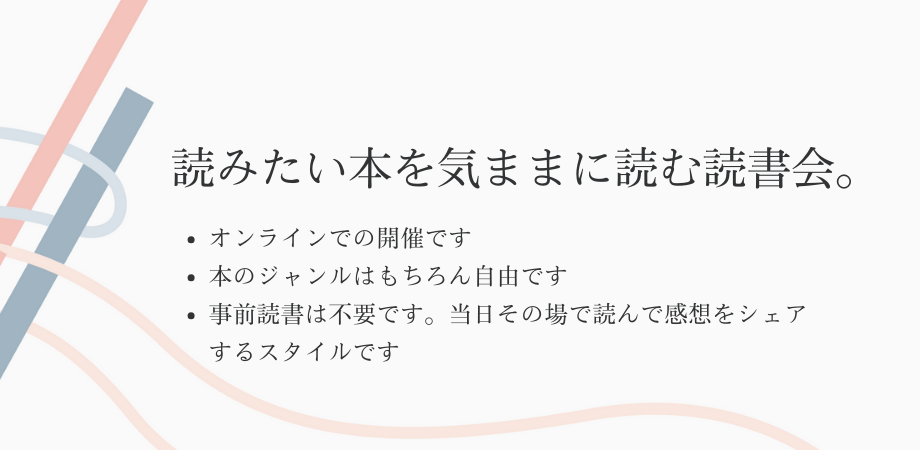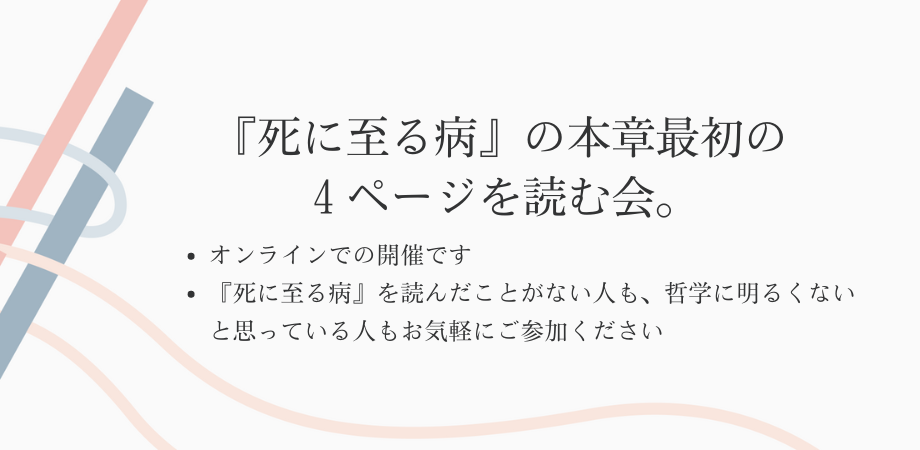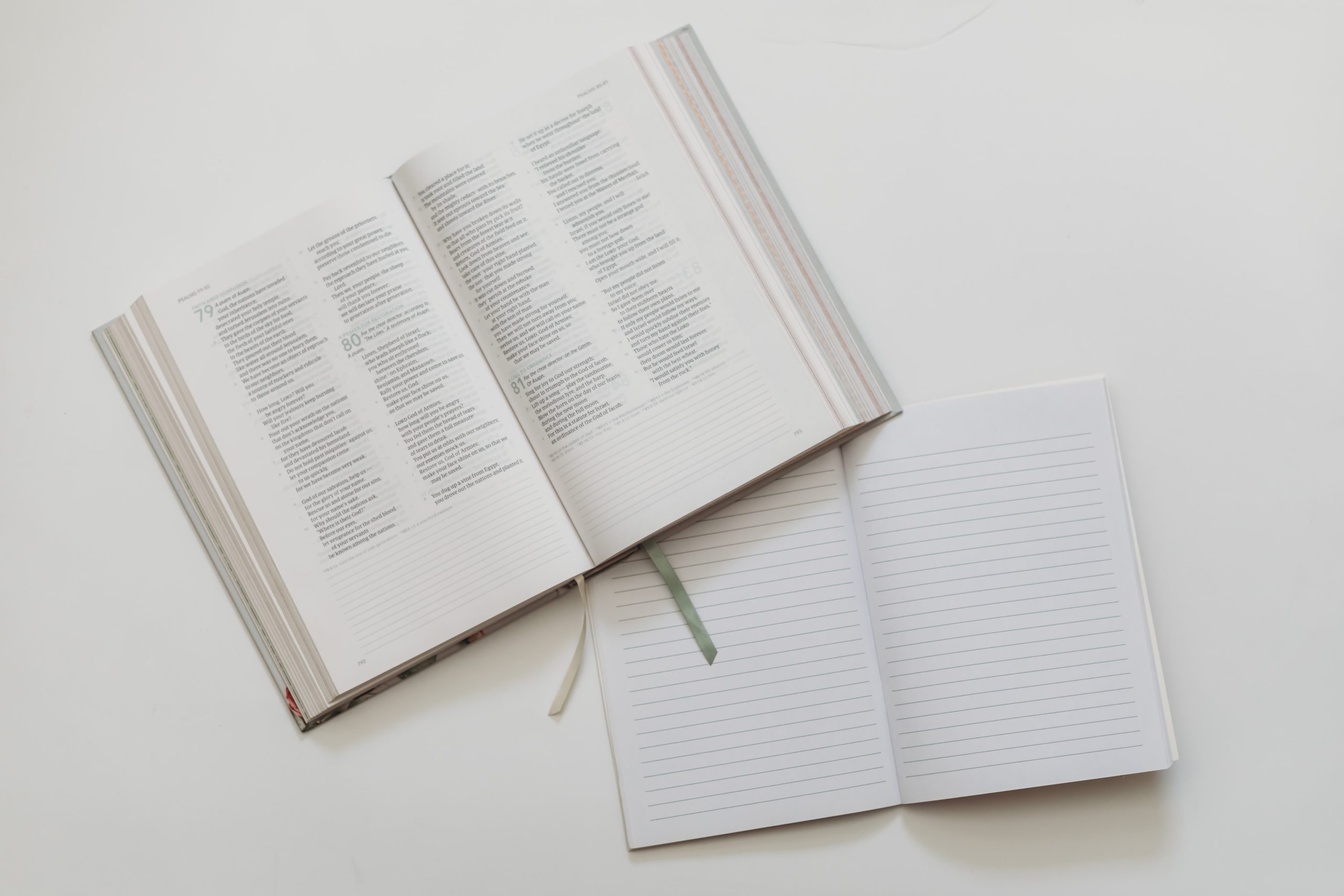
参加者に任意でいただいた読書感想を掲載します。14日(水)は3名、16日(金)は5名、17日(土)は8名、18日(日)は8名の参加でした(主催者含む)。
土曜日の「質問「 」について考える時間。」の質問は、
真実と事実の区別をどこでつけますか
(田中未知著『質問』(文藝春秋))
でした。
9月14日:読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『ある家族の会話』ナタリア・ギンズブルグ
作者はイタリアの女性作家です。ムッソリーニが台頭してきた時代に生きた家族の出来事が末娘の目を通して、書いてあります。父がどうしただとか、母がどうしただとか。この本に出てくる場所・出来事・人物は全て現実に存在したものであるそうです。自伝的な小説です。よくこんなに覚えていられるなと思いました。
「あの年の夏パヴェーぜは私たちの家に来る時にはいつもさくらんぼを食べながらきた」
「なんというロバだ」が父の口癖。
よしだ『自由からの逃走』エーリッヒ・フロム著/日高六郎訳
思想を分析するときは、その思想を唱える人の価値観や生い立ちを知る必要があるということが書かれていました。他の本で、人は客観的にはなれるけど中立的にはなれない、というのを読んだことがあります。また、人は合理的な生き物なのではなく合理化する生き物なのだとも。
自己というものを通して考えたり何かを発したりするとき、自己に蓄積している記憶や認識などといったものは排除できないのだと思います。もっというと嫌悪感や大なり小なりあるトラウマ、あるいは自分が拠り所としてきた考えは思考をする上で無意識に強く影響するように思います。
9月16日:読みたい本を気ままに読む読書会
うさじさん『「こころ」はいかにして生まれるのか』
本日もありがとうございました。
今日は対話について学ぶことができました。
ソクラテスの対話では、考えさせられるような質問をして、相手が応答することによって対話が生まれるようです。「問い」が生まれることによって、物事をより深く考えるきっかけになるのではないかと感じました。
ソクラテスの対話は、A⇔Bの一対一的な関係をイメージしましたが、オープンダイアログのリフレフティングという対話だと、Aが話したことについて、BとCが対話するという、A⇔B⇔Cの三角的な関係となっているようです。対話に第三者が入ることで、どのような気持ちや考えが浮かぶのでしょうか?
対話の方法にも色々あるのですね。
色々な場で、対話の方法や場の設定の仕方などに活かして行けれたらと思います。
yuさん『ある家族の会話』ナタリア・ギンズブルグ
あの年の春、ドイツ軍がフランスを占拠し、イタリアが戦争に突入しようとしていたあの春は遠ざかる。作者は思い出してこの話を書いている。レオーネがいなくなりパヴェーぜはその話をしない。
家族は店でバラバラに暮らしている。戦争って・・遠いようだけどそうではないのかもしれない。個人的な本当に個人的な回顧録だと思った。
9月17日:読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『デカルトの憂鬱』
皇女エリザベトとデカルトの手紙のやりとりがあったそうです、30年戦争で領地をなくしオランダのハーグで亡命生活を送るエリザベト王女は、憂鬱に苦しめられている。デカルトがそうだあったかは書かれていないです。本の引用と解説は全て作者の手によるもの。
今日読んだ読んだところは「疑う」というところです。「そもそも何かを疑うということは」・・・。こういうことを考える、感覚は間違えるから気をつけようと振り返りをすることそういう行為が大事なのかななど思いました。
グループでは、新聞記者について話しました。記事を書く以前に雇われたサラリーマンである。2019年に公開された映画「新聞記者」を思い出しながら聞いていました。正しいこととは?真実と事実はどう違うのかなど難しいなと思います。
9月18日:読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『星のせいにして』
1918年インフルエンザ大流行は、第一次世界大戦よりも多くの死者をだしたそうです。妊婦の発熱病棟で働く看護婦と手伝いの話。歴史小説です。リン医師だけが実在の人物。
「星のせいのして」とはどういう意味です?と質問が出ました。中世イタリアでは、インフルエンザは「インフルエンザ・デラ・スティレ:星々の影響(インフルエンス)と言われ天体の影響だと思われてきたそうです。
この作品のは会話分は「」がありません。原文にもないそうです。熱にうなされて夢を見ているような感覚を読者に味わってもらうためだそうです。リアルです。今日読んだところは後半でブライディがホワイト夫人の赤ちゃんの洗礼をするところ。
対話では、「坐禅とマインドフルネスはどう違うのか」の話でマインドフルネスはdoing坐禅はbeingなのではないか・・目的があるかないか。19世紀の哲学は幸せを追求していて20世紀は論理?に偏ってきて難しくなってきた?哲学が生活の中でどういきるのかが見えにくくなっているのかな?など考えました。
つやまさん『臨床とことば』河合 隼雄, 鷲田 清一
臨床心理学と臨床哲学の専門家同士のことばをめぐる対談本です。今日読んだところでは、講演や講義をするときに、聞き手があまりにも真面目で、冗談を言ったときでさえ真剣に聞くようなべたべたした聞き方をされるとかえって話しづらい、ということが話されています。ドイツの学生で編み物をしながら講義を受け、でも大事なポイントになるとパッと集中するという人がいたそうで、むしろこういう聞き方をされる方が話し手としては楽で、講義も充実するみたいです。前に読んだ部分で、臨床で1対1で話す場面でも、一生懸命なあまりに言葉の一言一句を掴んでしまうような聞き方をすると相手の無意識が自由に動けなくなってしまう、相手と自分の境界が混じり合うような感じでふわーっと聞くことがコツだと書かれていて、聴くことの奥深さを感じました。
また哲学は19世紀くらいまで幸福の追及を目的としていたのが20世紀に入ってだんだん立ち行かなくなり、代わりにハウツーのような即物的なものがポピュラーになるが、それも現代では限界が見えてきているということです。幸福は哲学やハウツーのように切れ味のよい一般論で語れるものではなくて、個々の事例において地べたを這うような「臨床の知」によって見いだしていくものだというのが著者たちの考えのようです。雑談の時間にお聞きした、幸福になりたくない人の幸福論というのが気になったので、調べてみようと思います笑
よしだ『自由からの逃走』エーリッヒ・フロム著/日高六郎訳
読書会の間に読んだ範囲では何を書いているのかわからなかったのですが、もう1ページ読み進めたらようやくみえてきました。自分なりの理解をまとめてみます。
大まかにはルターの思想の心理的背景から、人はなぜ自由から逃走し例えばナチズムのような圧倒するような力に屈しようとしてしまうのかを考察した内容です。
ルターはあるとき、次のような啓示を受けたのだといいます[P85]。
「人間はみずからの努力によって救われることはできない。人間は自分の仕事が、神にとって喜ばしいものかどうかさえ考えてはならない。」
これは人間の可能性や能力をかなり虚無的にみている考え方です。当時は、努力やそれによる可能性の追求はある程度は認められるところではあったようです。つまり、救済される人は神によってあらかじめ決められているという予定説が唱えられながらも、救済される人は善い行いをする人なのだろうという考えのもと努力が推奨されていたということです。しかしルターはそれらをすべて否定しました。それはなぜなのでしょうか。次のように書かれています[P85]。
「このような教義は、ルッターのような絶望と不安と懐疑にみたされ、同時に確実性を熱烈に求めていた人間があたえうるような、決定的な解答ではなかった。」
ここからは想像も交えた理解ですが、おそらく当時の人々は「神にとって善いこととはどういうことだろうか、こういうことなのではないだろうか」と模索しながら善い行いや努力をしていたのではないかと想像します。しかしそれでは不確実性が高い。なぜならその善行や努力が本当に善いものなのか・救済につながっているものなのかが”あいまい”であるとも言えるからです。そのあいまいさが、ルッターのような「絶望と不安と懐疑にみたされ」た人間にとっては不十分なものだったということなのだと思います。だからルターは冒頭に示した「人間はみずからの努力によって救われることはできない。人間は自分の仕事が、神にとって喜ばしいものかどうかさえ考えてはならない。」という思想に至ったということなのだと思います。そして次のように続きます[P85]。
「しかし人間は、もし信仰をもっているならば、救済を確信することができる。」
これは、善行や努力などといったあいまいなものではなく、とにかく信仰(信仰的活動)を深めていくことで救済につながるのだという確実性や直接性を高めた思想への転換であるといえるのだと思います。著者のフロムはこのようなルターの思想について次のように言います[P86]。
「確実性への強烈な追求は、純粋な信仰の表現ではなく、たえられない懐疑を克服しようとする要求に根ざしている。」
大胆に言い換えるとルターは、不安で仕方がなくて、確実な救済へつながるような思想を自ら創り出したということです。フロムは次のように続けます。
「ルッター的な解決の仕方は、いまでも多くのひとびとにみられるもので、ただかれらは神学的な言葉で考えないだけである。」
「すなわち、かれらは孤独となった自我を取りのぞくことによって、また個人の外にある圧倒的な強力な道具となってしまうことによって、確実性をみつけだしている。」
この本は1941年に出されたもので、主にナチスの全体主義に陥ってしまった人々について考察されています。中世の階層的・権威主義的な社会から抜け出して民主主義という自由を人々は手に入れたのに、なぜ権威に屈してしまう、あるいは権威に屈することを自ら求めてしまうのかという問いに対する考察です。民主主義や自由主義といった「個」として生きることをある意味では強いられる社会においては、個人は不安で仕方がない。その結果、その反動として強烈に自らを縛ってしまうような思想を求めてしまうということなのだと理解しました。
自由とは個人にすべてを任せてしまうことでは実現されないように思いました。不安や孤独が伴うようでは、個人は自由を求めることはできず、逆に不自由かもしれないけど自分を縛ってくれるある種の安心をくれるところへ向かってしまう。それがとんでもない行為を強いるような思想集団であった場合、個人も社会も崩壊していきます。自由とは不安や孤独への手当てがあってはじめて踏み出してもいい領域なのではないかと思ったりしました。
過去の読書感想はこちらに載せています。
〈読書会について〉
事前読書のいらない、その場で読んで感想をシェアするスタイルの読書会を開いています。事前申込をあまり求めない、出入り自由な雰囲気です。スタンスや日程などについてはこちらをご覧ください。
(よしだ)