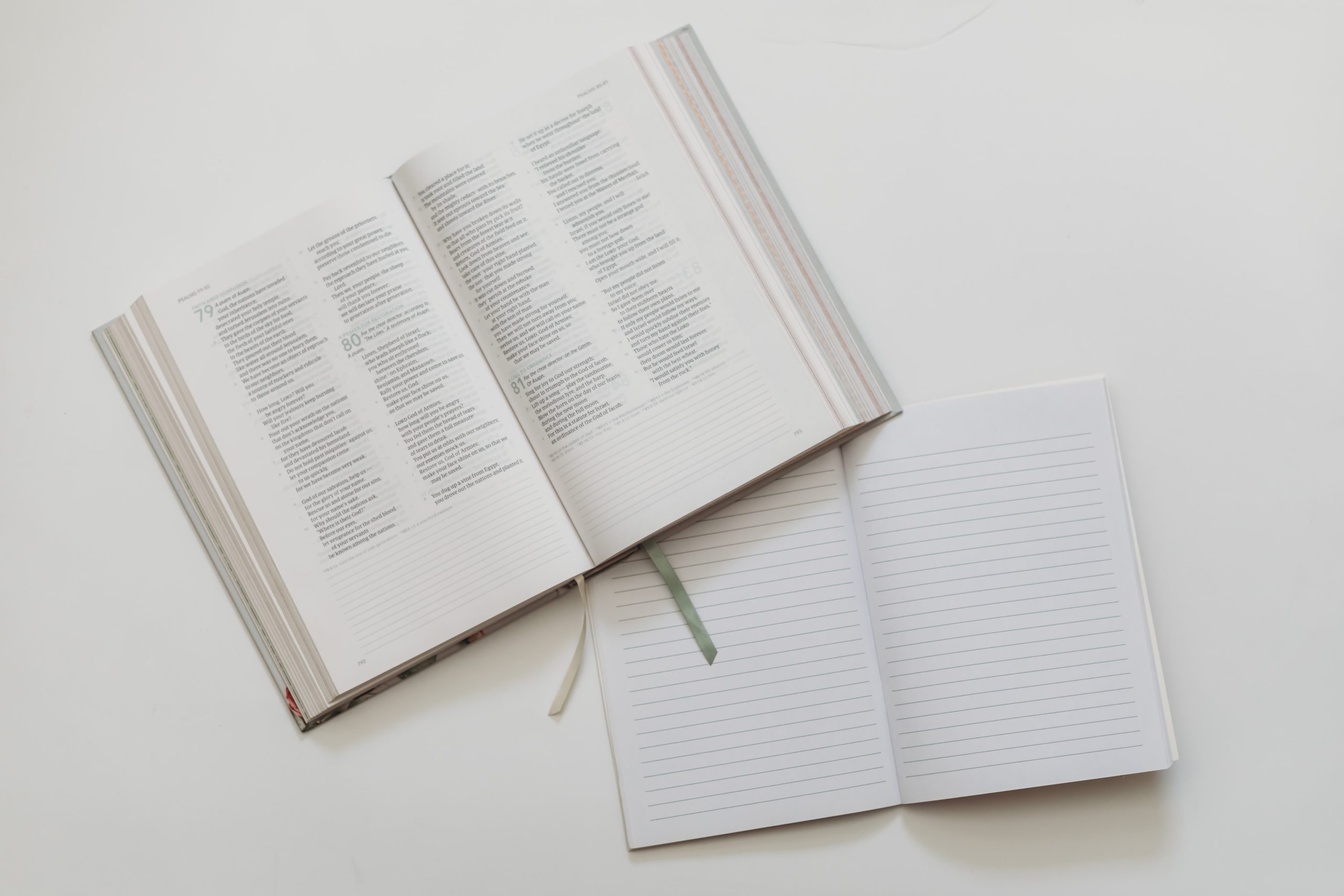
参加者に任意でいただいた読書感想を掲載します。19日(土/午前)は4名、20日(日/午前)は5名、20日(日/夜)は3名の参加でした(主催者含む)。
日曜日の「質問「 」について考える時間。」の質問はこちらでした。
心は体のどのへんに置いておくべきでしょうか
田中未知著『質問』(文藝春秋)
4月19日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『日本国民をつくった教育 寺子屋からGHQの占領教育政策まで』沖田行司
戦後教育の話がメインな感じがしますが、僕自身は寺子屋に興味があって手に取りました。自然発生的に全国的にそのような動きが起きて定着したのはなぜなのだろうと。
今日が読み始めなのでまだ全然序盤です。大昔は貴族や武士に教育の場があったようです。それはいわゆるエリート教育というか、武士なら家を守っていく必要がありますからたぶん長男メインで(?)武士としての心構えや家長としてのあり方などに通じることを教えられていたかな?などと。しかし、同時に庶民にも教育というか学ぶ場が溶け出していったというか、庶民にも教育の場がないとねみたいな考えはあり、ちょこちょこできていったようです。寺子屋がどのようにできていったのかはこれからなので、楽しみです。
4月20日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
Eimiさん『灯台へ』 ヴァージニア・ウルフ
登場人物の中に絵を描いている女性がいるのですが、目に映るものをキャンパスに描写することの難しさを心の声として語っている場面があります。
私も絵を描くことが好きで、それで彼女のもどかしさや悔しさについてはとても理解できました。
しかし(絵の)描写に苦しむ人物を(文字で)描写するウルフの口ぶりはとても良く書けていると思います。
登場人物達同士の会話はほとんどなく、彼彼女らの心の声をかわるがわる書いていく文章で構成されていますが、個性的な人物像の描き方がとても鋭くて幾度も「うーん」と唸らさせています。
よしださん『日本国民をつくった教育 寺子屋からGHQの占領教育政策まで』沖田行司
寺子屋は19世紀から増え始めたとのことです。江戸時代の終わり頃には2万近くもあったのだとか。人口比でいうと今の小学校と同じくらいの数なのだそうです。
ChatGPTの力も借りながら調べてみると、1850年頃の識字率は男性40〜50%、女性10〜20%とのこと。男性に限って言えば同時代のイギリスやフランスと変わらないのだそうです。明治維新前の、欧米からは文明的に大きく遅れていたとされた日本において、識字率の高さというか教育の行き届きには驚き、なぜなのでしょう。
19世紀から寺子屋が増えたのは、農業技術の発達に伴い知識の習得が必要になったり、商業の発達により契約書の作成などが発生したり、貨幣経済も発達したりといった必要性が一つの要因のようです。それでも、これだけの寺子屋が都市部中心ではあったようですがボトムアップで出来ていったことは驚きです。今のように国家主導ではなく、教員という資格や職業の人ではなく、教えられるだけの学力があった人が教えていたとのこと。ここらへんは日本の良さなのかなと思いました。
4月20日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『サロメ』ワイルド
・平野啓一郎訳で読みました。戯曲です。本文より解説と注釈が多いなと思いました。原文に忠実に訳したが1箇所だけ変えた部分があると書かれていました。モローでもピアズリーでもない平野訳。
オープンダイヤローグの本を読んでいる方がいて一旦意見はお盆に乗せて受け取れるものだけ返すというのが印象的でした。
Eimiさん『灯台へ』 ヴァージニア・ウルフ
一度は第一部まで読んだのになんだかわけがわからない感じでもう一度最初からじっくり腰を据えて読み直し、ようやく第一部を読了しました。
感想のシェアの時に他の参加者の方がウルフの文体についてフォークナーなどと同じ「意識の流れ」とおっしゃっていましたが、私はフォークナーの『響きと怒り』の最新訳で惨敗しておりまして、何が何だかわからないままに話が終わってしまったのです。
それに比べたら『灯台へ』はまだ多少は分かりやすく感じます。
『響きと怒り』を読んだのも全く無駄にはなっていないのかも、何事も経験してみるものです…。
ウルフの人物と自然描写が大変細やかで、人物像もよく練られていて、「うーん」と唸らされます。
第二部の冒頭を少しを読みましたが、何人かの登場人物が亡くなった模様です。
帯に「描かれるのはたったの2日のできこと。文学史を永遠に塗り替えた傑作」と書かれています。
いよいよその2日目に入って、この「傑作」は私をどう振り回すのか今から楽しみです。
が、起承転結で説明できる小説ではないので、読書会の感想のシェアタイムは冷や汗かきつつしどろもどろです…。
お聞き苦しかったら申し訳ないです。
過去の読書感想はこちらに載せています。
〈読書会について〉
事前読書のいらない、その場で読んで感想をシェアするスタイルの読書会を開いています。事前申込をあまり求めない、出入り自由な雰囲気です。スタンスや日程などについてはこちらをご覧ください。