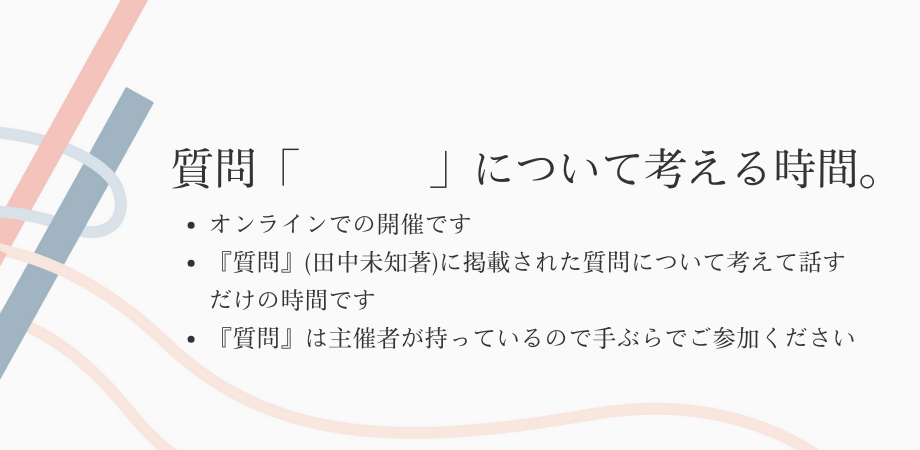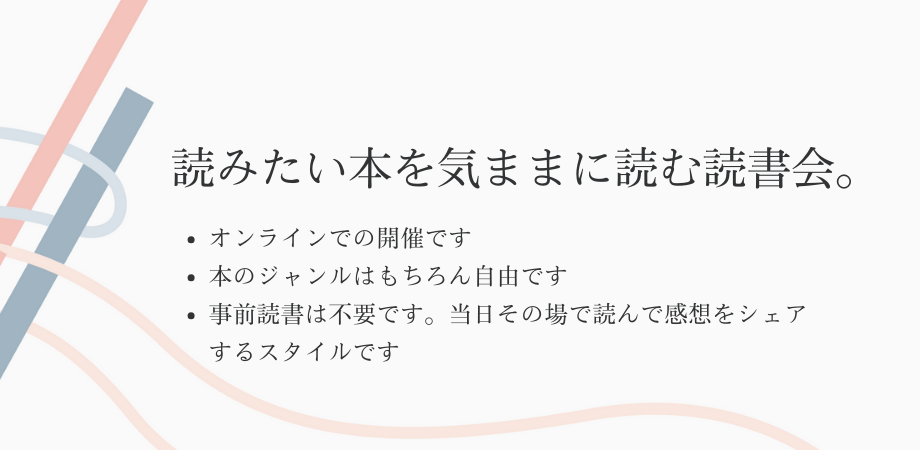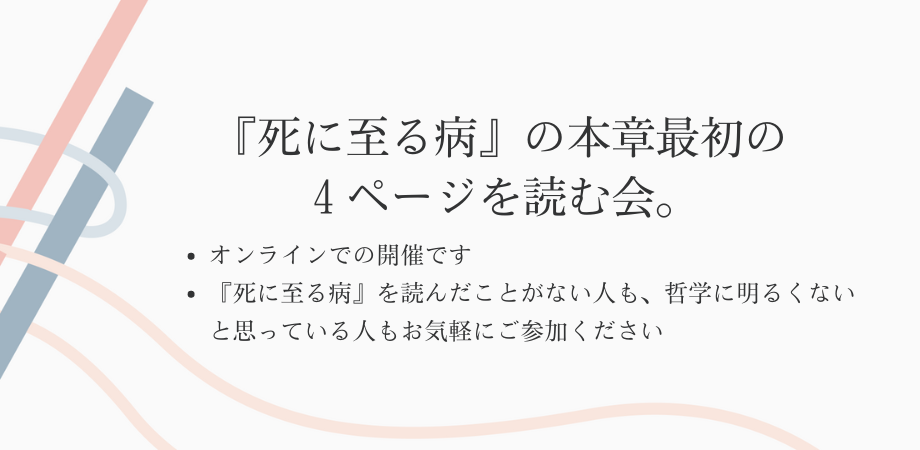(文量:新書の約18ページ分、約9000字)
国語も算数も理科も社会も答えが出れば終わっていたけれど、もうすこし不思議を考える時間があってもよかったかもしれません。
たとえば小学校の社会では、自分たちが住んでいる都道府県や市町村について学んだ記憶があります。私は岩手県出身ですが、岩手県は都府県の中で面積が一番大きいと習います。大きいと言われればなんだかうれしい。しかし人口が一番多いのは東京で、岩手県よりも面積がかなり小さい。なぜ岩手はこんなに大きいのか、そもそも県境は誰がどんな基準で決めたのか。
理科では、たしか教科書にカエルが解剖された写真が載っていました。そして「カエルは鶏のササミに似た味」と書かれていたような気がします。では、なぜカエルを食べないのか。たぶん変温動物のカエルは恒温動物の鶏よりも、少ない食料で大きく発育していくはず…。
国語なんかはそのときの気持ちを四択で答える問題があったような気がするけど、そんなものは人それぞれ。算数では、たとえば八百屋に行って帰ってきたら何時になっているでしょうかなどと日常を問題にしていたような気がするけど、本当の自分の日常に方程式はどこまで対応してくれるのだろうと試してみてもよかったかもしれません。
教科書は誰かの手で作られました。そこには、その先の学習や社会で生きていくための基礎となる知識が、国のねらいとともに盛り込まれていたのだと思います。そのボリュームは振り返ってみると相当な量で、不思議に思ったことをひとつひとつ掘り下げていてはとても終えることができないものだったと思います。
このような学習方法は詰め込み教育として揶揄されることもありますが、決して悪いことだけではないでしょう。たとえば、そもそも不思議なことを発見するには知識が必要です。岩手が大きいと思うためには他の都府県の大きさを知っていることが必要ですし、人口が少ない割に大きな面積をもつ岩手と不思議に思うには東京の人口を知らなければなりません。ひとつの知識がほかの知識と比較されたり結びつけられたりしながら、不思議なことを発見したり、自分なりに考えたりできるのだと思います。
小学校・中学校の義務教育を終えたら、ほんとうであれば身につけた知識をつかっていよいよ自分で不思議を発見し考えをつくりあげていく番だったのかもしれません。でも、実際はどうだったでしょうか。進学しようと思ったら勉強が一層忙しくなり、社会に出てからも追わなければいけないことが少なくなくしかも移り変わり、なかなか学びの主体を自分のもとに引き寄せるきっかけがなかったように思います。
ノルウェイの高校教師で哲学を教えていたヨースタイン・ゴルデルは、14歳の少女・ソフィーが哲学を学んでいく児童文学『ソフィーの世界』[1]を描き1991年に出版しました。世界で2300万部を超える大ヒットになったようで、1995年に日本で出版されたときにもかなりのブームになったようです。時代としてはバブルの崩壊が認識されはじめ、山一證券や北海道拓殖銀行が倒産をするすこし前ということになります。
『ソフィーの世界』は、主人公・ソフィーの15歳の誕生日に向けて話が進んでいきます。日本では義務教育を終える歳ですが、ノルウェイでも同じく自分で進路を選びはじめる歳のようです。ゴルデルは著書を通して何を伝えたかったのでしょうか。物語は、2500年以上前に存在した古代ギリシャよりもさらに前、神話を知の拠り所としていた時代からの、人間が考えてきた歴史の講義とともに進んでいきます。ゴルデルはきっと、大人になる子どもたちへ、あるいはすでに大人な大人たちへ、学んだり考えたりすることのおもしろさや意味を感じてほしいと思っていたのではないかと思います。
今回は、『ソフィーの世界』から感じた学ぶことや考えることの意味を、自分なりの解釈もいれながら記してみたいと思います。これから大人になっていくソフィーに哲学を教えることにどんな意図があるのか、というのがこの本を読んでいるときの私の関心ごとでした。
神話と木星
記憶はあいまいですが、私たちは10歳そこそこで、雨が降る原理や、肥沃な海と山の関係や、太陽系の全体像などを、簡単な模式図を用いながら学校で習います。これは冷静に考えればすごいことです。すこし前には最先端の研究成果であり、そのもうすこし前では誰も知らなかったことだったはずだからです。そんなふうに自然や世界や宇宙のことを科学的に認識している私たちですから、神話を知の拠り所にしていた時代など、稚拙でかわいそうなものに思えてしまうかもしれません。
『ソフィーの世界』は、ソクラテスやプラトン、アリストテレスなどの哲学者が登場する以前の、神話をもとに人々が生きていた頃の話から始まります。それは、神話をもとに生きていた人々の日常そのものが神話に思えるような、今の常識で考えると非現実的なものでした[1,P36]。
たとえば、雨が降るのはトールという神が槌を振ることで起こると考えられていたところもあったようです。雷が起きれば雨も降り、雨が降れば畑の植物が豊かに実るため、トールは最大級の力をもつ神とされていたそうです。トールによって保たれている世界を脅かす敵もいましたが、トールはその敵も槌によって倒すことができます。トールは偉大なのです。ただ、人々もトールのような神が助けてくれるのをただ待っているだけではありません。神の力が強まるようにと犠牲を捧げました。それは羊であるときもあれば、人であることもあったのです。しかし残念なことに、トールも完全無欠ではありませんでした。あるときトールが眠りから覚めると大事な武器である槌が無くなっていました。どうやら敵に盗まれたようなのです。敵は、豊穣の女神・フレイヤと引き換えになら槌を返してやる、と言ってきます。フレイヤを渡しては畑の緑も、人間も神々も絶えてしまいます。そんなことはできません。でも安心してください。フレイヤを渡さずに槌を奪い返す作戦をトールと他の神々が考え、無事成功させました。
槌が奪われる事件は季節の移り変わりの時期に起きていたとする考えもあるようです。つまり雨が降らない乾季を、槌が奪われたからであると説明するのです。生きることと密接に関わる自然を、神話で説明し、儀式などを通して自分たちなりに相対していたのです。
学校で教育を受けてきた私たちは、このような神話は信じられません。神話をもとに生きていた世界は、おとぎ話としてはおもしろいと感じるかもしれませんが、現実にあったとしたら愚かしいと思ってしまうかもしれません。なにせ解決策としての効果が限りなく薄い犠牲を捧げたりしていたのですから、かわいそうに思えてきます。
しかしこのような神話とともに生きる世界を知ったときに、私はあることを思ってしまいました。それは、教科書に載っていたあのようなかたちで木星が在る、と信じているという点で、神話をもとに生きていた時代の人々と私たちとでは大きく違わないのではないか、ということです。木星とは一つの例えですが、地球の2つ外側の軌道を回っており、マーブル模様で、地球よりもはるかに大きな木星があると、私たちのいったいどれだけの人が実際に確認したことがあるでしょうか。教科書に載っていて、先生が授業で教えてくれたことを、信じているだけとも言えます。この目で見たことも地表を触ってみたこともありません。そういう点では、トールが槌を振ると雨が降る、槌を奪われると乾季になる、などと信じる神話の時代を生きた人たちと同じであると思えてくるのです。彼ら・彼女らも、まわりの大人から教えられたことを、同じように信じていました。
もちろん、教科書に載っていることは、神話的世界観の時代から多くの知が重ねられてきた確からしい知見なのでしょう。製作者の思想が入り込むことはあっても、荒唐無稽なことが載っているとは思っていません。
ここで思ったこと、言いたかったことは、学校を出ただけの時点では、習ったものの上に生きているだけなのではないかということです。ゴルデルが主人公の年齢を14歳に選んだのは、義務教育を経て一定の知の土台ができたときであり、自分で生き方を選択できる年齢だからだと感じました。習った知識をもとに社会に出て、不思議なことを発見したり、習った知識の上にさらに知識を重ねたり、おかしいと思ったら疑ってみたり、そういうことができ始める年齢です。そして、それはもちろん14歳・15歳に限定されることではないでしょう。ゴルデルはインタビューのなかで読者の想定を「十四歳以上のおとな」と応えていたのだといいます[1,P659]。教科書を閉じてそれを足場とし、自分なりの考えをつくりあげていくことが、ある一定の学びを経た大人にはできるということなのでしょう。
哲学者とは
知識を得ると、それを周りに言いたくなりますし機会があれば教えたくなります。そうすることで、知は広がっていくのでしょう。しかし、知識をもって教える人と、哲学者とでは、ある意味では対極にいる人のようなのです。『ソフィーの世界』にはソフィストと名乗る人たちが紹介され、あの有名な哲学者・ソクラテスとの対比のなかで語られていました。
紀元前450年頃、古代ギリシャの首都・アテナイには、ソフィストと名乗る人たちが登場していたといいます[1,P88]。
この頃のすこし前から、神話を知の拠り所とする世界観から、目の前の物事を観察し理性をもって考えを組み立ていく哲学を知の拠り所とする世界観へギリシャでは移り変わっていました。雨はなぜ降るのか、植物はなぜ生えるのか、そもそもそれらのモノたちは何で構成されているのか、自然にあるものを観察し理論を打ち立てていきました。そのなかには、現在の「原子」に通じる考えを導き出したデモクリトスという人物もいました。デモクリトスは、モノは多様な最小単位の物質で構成されており、その物質はあるときには人体を構成するけれども、それが滅すれば別のときには樹木を構成することになる。そしてその最初単位は様々な形をしていてパズルのように他の物質と組み合わさり、一方で頑丈なためそれ以上細かく壊れることはない、という考えを示しました。これはたとえば、炭素・Cが他の原子と結びついて、あるときは人体をあるときは樹木を構成したりしているのだけれど、炭素・Cとして変わらず存在し続ける、という現在でも通じる考えと遜色のないものでした。実験や観察の機器などが整っていない時代に、理性の力だけでここまでの知の深さに達していたのです。
このような、理性的につくられた知が浸透していたアテナイでソフィストは、知識をもち人々に教える立場にありました。ソフィストとは、学のある人、その道に通じた人という意味なのだそうです。しかしソフィストは様々な知識をもちながら、人間には決して出すことができない答えがあると言ったり、良い悪いの絶対的な基準などないと言ったり、知を追求するというよりは知っている範囲を伝えるにとどめるような態度をとっていたようです。
それに対してソクラテスは、自分の物事の知らなさ具合に悩んでいました。ソクラテスが残したとされている有名な言葉に、「無知の知」というものがあります。あるときソクラテスは、ある権威がアテナイで一番賢いのはソクラテスであると示したと聞き驚いたといいます。そこで、評判の知者を自分でたずねてみると、ソクラテスはその見解を認めました。物事を知らないという点において、ソクラテスは他の知者よりも賢いと認めたのです。
ソクラテスにたずねられた知者は、ソクラテスとの対話のなかで自分がいかに物事を知らないかを思い知らされていたことでしょう。周りにはおそらく聴衆もいました。ソクラテスはこのとき以外にも、奴隷でも自由市民でもソフィストでも、いつでも誰に対してでも対話をふっかけていたといいます。
『ソフィーの世界』のなかでは、哲学者について次のように言われています[1,P94]。
哲学者は、自分があまりものを知らない、ということを知っている。だからこそ、哲学者は本当の認識を手に入れようと、いつも心がけている。
これは物語のなかである人物が言っていることなのですが、おそらく著者・ゴルデルの考えでもあるのでしょう。人に物事を教えるとき、自分は無知であると宣言していては、なかなか具合良く聞いてくれないかもしれません。自分は物事を知っている、しかし人間には知り得ないことがあると線引きしてしまった方が、具合がいいのです。
しかしその時点で、物事の認識を固めてしまっていると言えるのではないでしょうか。自分は知っていると言いながら誰かに教えたことを、間違っていたといって直すことは簡単なことではありません。また、薄々あやしいと感じながらかも「これはこういうものです」と言ってしまえば、その言葉に自分自身が固められてしまいそうです。
ソフィストに対して哲学者は、自分は物事を知らないと言い、考えつづける人をいうようです。知るほどに分からないことが増えていくことに、向き合いつづけるのでしょう。自分で考えを築きながらも決して固めることなく、いつか自分を含めた誰かに覆されることを思いながら、どうにか目の前の問いに答えを出そうと探求しつづけるのです。
物事を知らないと言ってしまう哲学者など役に立たないのではないかと思ってしまうかもしれません。知っていると思っているからこそ、なにかを決断できたり、人を導くことができるように思うからです。しかしソクラテスも、ただ知らないと言い続けているだけではなかったようです。
ソクラテスは、死刑制度に異を唱えたり、政敵の密告や中傷に抗議したりしました。その結果、「若者を堕落させ、神々を認めない」という罪で死刑判決を受けてしまいます。恩赦を願えば助かったかもしれないようですが、国家にとってよかれと思ってふるまったのだと、態度を曲げなかったようです。すこし刺激が強い例ではありますが、物事を知らなくてもおかしなことに気づき、それを信じて論を唱え、議論に人を巻き込むことはできるということなのでしょう。しかし、ソクラテスの断片しかまだ知りませんが、実際に世を変えるためには、いまひとつなにかが足りなかったとも言えるのかもしれません。
自由は不自由でもある
『ソフィーの世界』には、こんな一節がありました[1,P48]。
こうして哲学者たちは宗教から自由になりました。
これは、先に紹介したトールが槌を振ることで雷や雨が降ると信じられていた神話的世界観に、哲学者が疑いの目を向け、ひとつひとつの自然現象に一から説明を試みた頃のことを言っています。物事や現象については神話で説明されていた、しかし指摘されればどこかあやしく思えてしまうことに哲学者が切り込んだことで、神話から解放されたということです。たしかにより適切な認識をもつことで、予測や対策の精度が上がることでしょう。犠牲を差し出すというようなほとんど効果が見込めない策に囚われる必要もなくなります。
しかし宗教や神話という信じていたことを失わせることで、逆に不自由さを抱かせたりはしなかったのでしょうか。
私たちは制約があることで、自由で、創造的になれる側面があるように思います。たとえば、サッカーは腕や手を使ってはいけないと言われるから、あそこまで多彩な足技が生まれたり、そのルールの抜け道をつくるかのように頭や肩や背中を使おうとする者が現れたりするのではないでしょうか。ゴールキーパーやディフェンダーがいることで、ボールを曲げたり無回転のブレ球にしたりという技術も発達したことでしょう。
制約があることで思考が働き出します。そしていくつもの選択肢が生まれていきます。
これがだだっ広い平地でボールを渡されただけでは、困惑したり、すぐに飽きたりするのではないでしょうか。きっとすぐに自分たちでルールや設定などの制約をつけ始めるはずです。なにをしてもいい、どこへ行ってもいいと言われると、かえって困って動けなくなってしまうのです。おそらく、私たちの心や頭はそこまで無数の選択肢を並べる能力も、そこから合理的に選んでいく能力もないからストップしてしまうのではないかと思います。ある程度の制約がないと、快活に活動することができないように思えるのです。
『ソフィーの世界』では、サルトルという近代の哲学者が登場しました。サルトルは「人間は自由の刑に処されている」と書いたのだそうです[1,P581]。哲学の歴史のなかでは、これまで主に紹介してきた自然に関する見解だけではなく、人間や社会について多く論じられてきました。人間とは何か、人間の本質とは何か、という問いに答えを出そうとしてきたのだといいます。しかしサルトルは、人間は拠り所となるような本質などない、実存するだけだという考えを示したというのです。
近代の前の時代区分である中世には、聖書に書かれたことが真実であり世の習わしであるとされていました。それが、ニュートンやコペルニクスといった科学者たちの理論によって次第に崩されていきました。人々は信じていたものを失ったのです。
きっと聖書には、人々の行動の規範となる道徳的な内容も書かれているのではないかと思います。私たちの授業の科目にも道徳がありましたし、日常生活でも「情けは人のためならず」というような規範をそれとなく携えながら活動しているはずです。そうした規範意識や価値基準は、選択の拠り所となるという意味でも生活の上でとても大切です。
さまざまな価値や行動の基準となっていたものが崩れたとき、人は困惑したことでしょう。そこで哲学者が登場し、人間の本質を見出し、新たなあるべき姿を築き上げようとしたのではないでしょうか。しかしサルトルは、そんなものはないと言ったのです。その時代に、即興的に見出していくものだという考えを含意していたようです。
本質などという普遍的な拠り所がないのに、人間は中世の宗教的世界観から解放されて自由を手に入れてしまいました。紀元前にも同じく、哲学が神話的世界観から解放してしまいました。自由という運命に人間は巻き込まれてしまったのです。だからサルトルは、「人間は自由の刑に処されている」と書いたのでしょう。
サルトルの言うことが本当ならば、自由な時代を生きる人にとって、価値や行動の基準を自分たちなりに作り上げていくことは、ひとつの大きな仕事であると言えるのかもしれません。人間に本質など無いというのは本当なのでしょうか。たしかに、日常で人の優しい一面をみる一方で、歴史には人間の残虐な一面もみます。ホモ・サピエンス=賢いヒトと言いながら、自分たちの住む世界を破滅させようともしています。人間の本質は何かという議論も興味深いですが、そんなことを考えられる時点で自由であるとも言えるのかもしれません。学ぶ自由、表現する自由、仕事の自由などを手に入れ、そして同時に多くの問題を抱える現代においては、自分たちはどう生きるのかを考えていくことは必要とされていることなのでしょう。
解放されて自由になると、動けなくなって近くの何かにすがりたくなるのかもしれません。しかし、自由すぎるなかでも哲学者のように、困惑しながら分からないと思いながら進んでいくという生き方もあるのでしょう。
自立するということ
『ソフィーの世界』はファンタジーです。ですので、物語は途中から不思議な展開をみせていきます。多少ネタバレになってしまいますが、物語のクライマックスからゴルデルが伝えたかったことを考えてみたいと思います。
物語の最後の方ではソフィーの15歳の誕生日パーティーが開かれています。そこにはソフィーの友達やその両親が参加していました。しかし、それまでソフィーに哲学のことを教えてくれていた人物が突然、この世界はある大人がつくりだした幻想であると言い出すのです。実際に物語はそのように展開されているのです。親たちは困惑し「そんな話はやめろ」と言い出しますが、子どもたちは興味津々でした。
この件が意味することは、これまで義務教育を受けながら過ごしてきた時間や、今の世界は、大人たちがつくり出したものであるということなのだと私は解釈しました。教えられたことをただ信じて、それをもとに思考や行動をしてきたのは、他の誰かの手の上で生きてきたということであり、幻想なのだという意味なのでしょう。
しかしそう捉えられるようになることで、今あるものを批判的に考えられるようになるとも物語のなかでは同時に述べられていました。つまり、批判的に思考し、自分たちの手でそのときに合った考えや規範などをつくっていくこと、ゴルデルが15歳の大人に伝えたかったことはそういうことなのだと思います。同時に、考えることのおもしろさや世界の不思議の数々も。
自立するというのは、なにかを否定することで成っていくと心理学の本で読んだことがあります。思春期に親に反抗するのは、親を否定し頑張って突き放すことで自立していくためであるというのです。たしかにそれまで育ってきた居心地のいい環境から離れるためには、それだけの強い力が必要なのかもしれません。
知識は無限にちかく得ることができます。聞けば教えてくれる人も多くいます。しかし本当に自分に合った考えや今に合った考えというのは、他者や過去からだけではどうしても引き出せないように思えます。義務教育を終えても次の教科書が目の前に現れ、社会に出てもハウツーが無数に出てきます。きっとどこかのタイミングで、すでにあるものから自分を離すことも必要なのでしょう。そして離れてみると、今まで生きてきた世界のおかしなところがみえて、探求のテーマが見つかったりするのかもしれません。それを趣味にしようが仕事にしようが、自分なりに探求していくことはきっと充実へとつながるような気がしています。
〈参考図書〉
1.ヨースタイン・ゴルデル著/池田香代子訳『ソフィーの世界』(NHK出版)
〈「考えることと生活」他のコンテンツ〉
(吉田)
(カバー画像出典元)