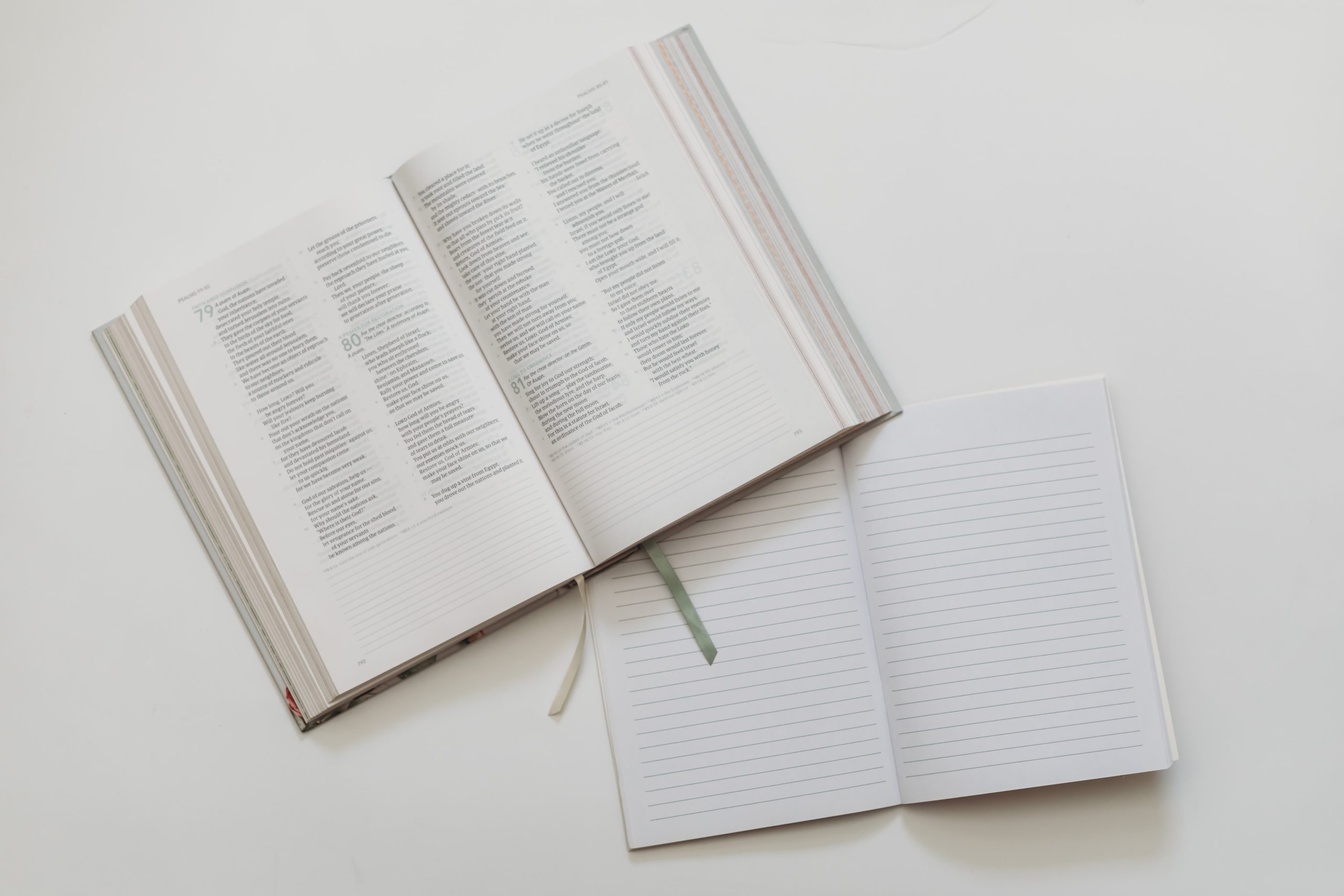
読書会に参加した人とのちょっとした振り返りの時間として、参加できなかった人への読書会の様子や話題のシェアとして、読書会に参加いただいた方の読書の感想をこの場所に載せていきたいと考えています。「気が向いたら」という任意でいただいた感想です。引き続き更新していきます。
過去の分はこちらです。
〈読書会について〉
事前読書のいらない、その場で読んで感想をシェアするスタイルの読書会を開いています。事前申込をあまり求めない、出入り自由な雰囲気です。スタンスや日程などについてはこちらをご覧ください。
※スマホの方は見にくくて申し訳ありませんが、目次一覧の下に本文がございます。
- 2025年7月20日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年7月6日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年7月4日(金/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年6月22日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年6月15日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年6月15日(日/午前):質問「 」について考える時間
- 2025年6月14日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年6月10日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年6月8日(日):〈リベルの文化祭〉退屈で、退屈で、しょうがいないんですけど。
- 2025年6月8日(日):〈リベルの文化祭〉私のいちおし銘菓
- 2025年6月8日(日):〈リベルの文化祭〉今だから話したい、村上春樹のこと
- 2025年6月1日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年6月1日(日/午前):質問「 」について考える時間
- 2025年5月31日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年5月21日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年5月18日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年5月18日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年5月18日(日/午前):質問「 」について考える時間
- 2025年5月13日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年5月11日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年5月4日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年5月4日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月29日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月27日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月27日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月20日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月20日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月19日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月13日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月12日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月12日(土/午前):質問「 」について考える時間
- 2025年4月6日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年4月1日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月30日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月26日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月22日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月22日(土/午前):最近気になっているテーマや本など
- 2025年3月19日(水/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月18日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月16日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月16日(日/朝):〈お試し企画〉散歩して書く会(仮)
- 2025年3月15日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月4日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月2日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月1日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年3月1日(土/午前):質問「 」について考える時間
- 2025年2月26日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年2月23日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年2月23日(日/午前):質問「 」について考える時間
- 2025年2月22日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年2月18日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年2月16日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年2月15日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年2月12日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年2月9日(日/午前):質問「 」について考える時間。
- 2025年2月8日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年1月29日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年1月26日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年1月25日(土/午前):読書のもやもやについて話す時間
- 2025年1月15日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年1月12日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年1月11日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2025年1月7日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月29日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月29日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月28日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月27日(金/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月25日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月22日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月17日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月11日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月8日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月7日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年12月1日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年11月29日(金/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年11月27日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年11月24日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年11月24日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年11月23日(土/午前):読書のもやもやについて話す時間
- 2024年11月20日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年11月13日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年11月10日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年11月5日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年11月3日(土/午後):〈リベルの文化祭〉「労働」をテーマに話し合う会
- 2024年11月3日(土/午後):〈リベルの文化祭〉秋といえば、保存食についてシェアする会
- 2024年11月3日(土/午前):〈リベルの文化祭〉ドストエフスキーとその作品の魅力
- 2024年11月1日(金/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年10月30日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年10月22日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年10月19日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年10月8日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
- 2024年10月6日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
2025年7月20日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
うさじさん『子どもへのまなざし』
「出産直後から母と子がそばにいるかどうかで母親の行動が変わる(ヤギなど他の動物でも同じような行動がみられる)」という内容は興味深かったです。
Takashiさん『政治の世界』丸山眞男
参議院選挙があったからというわけではないですが、買ってからしばらく読んでなかった本だったのでこの読書会を機に読んでみようと思いました。
政治は利権の分け前の奪い合いであったり、個人的な人間関係によって動いたり、政治家の活動動機が過大評価されたりするので学問としての政治学は難しいということが導入に書かれています。
文章は難しいですが、丸山眞男なので目からうろこの内容が随所に出てくると期待し頑張って読みたいと思います!
かよさん『傷を愛せるか』
弱さを克服するのではなく、弱さを抱えたまま強くある可能性を求めつづける旨が印象に残りました。
yuさん『失われたスクラップブック』 ルリユール叢書 /エヴァン・ダーラ 木原善彦=訳
句読点や改行のない約550ページの長編。化学工場のある町イソーラに住む人々の健康への違和感が描かれ、企業や専門家の「問題ない」という姿勢に疑問を投げかける。住民?の頭の中の思考が断片的に並び、徐々に物語の輪郭が見えてくるような構成。
小澤さん『理想の国語教科書』
著者の公開ホームページでも読むべき書と言われている、「百年の孤独」を選びました。麦焼酎の方は飲んでいても、意外と読書家の方々に読まれていない様子だったのは、中南米を舞台にした非常にクセの強い「発酵品」のような文学だからなのでしょうか。映画化される前に、これを機に読んでみたいと思います。冒頭部分だけでは、せっかく印刷した家系図の人物はまだまだ登場していません。準備万端で旅に出るように、しっかり読み進めたいです。
2025年7月6日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『失われたスクラップブック』 ルリユール叢書 /エヴァン・ダーラ 木原善彦=訳
改行がなく、登場人物もランダムに登場して一体誰の話なのかよく分からないまま300pをこえました。
300p超えると面白くなる?やら環境問題の話?やら聞いていました。日常にいたら気になる人や誰も気にしていないのに自分だけ?が気になる違和感?などが書かれているのかな?働いているマフィン工場で何かゴミみたいなものを毎日組み立てていた男の話など。2パターン同じサイクルで突然、え?また!笑?となりました。
2025年7月4日(金/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『オブローモフの夢』ゴンチャロフ
過去に奈倉有里さんの「ロシア文学の教室」で紹介されていた人物で気になっていました。
稀代な怠け者としてロシア人なら知らぬ人はいない愛されキャラで、岩波で3巻あるうちの1巻目はずっと布団から起き上がってこないと聞いていました。読んでいる本は「オブローモフ」の10年前に書かれた第一部第9章のみが文庫化されたものです。
2025年6月22日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
Takashiさん『共感の正体』山竹伸二(他の方が読まれた本です)
感想を話し合ったとき、「なぜ女性の方が共感力が高いのか」という話になりました。ほんと、なぜでしょうね。
そこまで親しい間柄でもない女性どうしがほんのちょっとの共通点を見つけ、わーっと話が盛り上がるのをよく見ます。男どうしじゃなかなかああは行きません。
さて、そんな話をしつつ「読書会って男女関係なく盛り上がることができるよなあ」と考えていました。これもまたなぜでしょうね。
2025年6月15日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『徒然草』吉田兼好
教科書でお馴染みの随筆です。短い話が243個ありました。
今日は、117:友達にするのに良くないもの7つ。善い友は3つ〜 127 改めても益のないことについてを読みました。
動物に対する目線や諦めることの潔さなど書かれているなと思いました。現代でいう自己啓発?という質問も出ました。人生訓のようであり面白みもあるなと思いました。
2025年6月15日(日/午前):質問「 」について考える時間
この回の質問はこちらでした。
あなたの生まれた日はどんな空模様でしたか田中未知著『質問』(文藝春秋)
yuさん
質問は「自分の生まれた日の天気は・・」天気は多分朝の5時頃と聞いてるから夜が明けていない云々考えました。聞かないとわからないことを話していて自身の子供の頃のことを思い出したりして「母に日記を書きなさい」と言われて描いててなど思い出しました。考えをまとめることについて話ができて、質問はいいきっかけになると思いました。
2025年6月14日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『覇権からみた世界史の教訓』中西輝政
イギリスは遅く動くという知恵があるのだそうです。混沌とした状況のとき、リスクはいくらでもあります。そのリスクがまだ差し迫っていないのに動くと、悪い状況にいくことも多々ある。均衡状態をリスクだと思って相手を攻撃すると、攻撃したことが非難の対象になり敵が増える、みたいなことです、たぶん。リスクはいくらでも見積ることができるけど、それが差し迫っているか、今動いたらどんな展開の可能性があるのか、そういうことを考えて、本当にリスクが差し迫ってから対応をする、危機を乗り切るためにリスクを犯すことが重要、みたいな教訓を得ました。
2025年6月10日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『「競争」は社会の役に立つのか 競争の倫理入門』クリストフ・リュトゲ
今日から読み始め、ですが少し難しくて早くも積読になりそうな…。
競争を必ずしも歓迎するわけではないけど必要なものとして論じていくような感じがしています。競争との対比で「闘争」はルール無用の殴り合いのようなもので、それに対して競争はルールや枠組みのなかで建設的に行われるもの、という区分けがされていました。教育などに関しても競争の必要性を論じていくようだけど、教育は親が好むとか子供が喜ぶとか、そういう消費的な基準では測れなさそうだけど、そこらへんはどう考えるのだろうと気になりました。
2025年6月8日(日):〈リベルの文化祭〉退屈で、退屈で、しょうがいないんですけど。
yuさん
退屈・・暇・・。贅沢な悩みだ!と初めは思いました。予定が詰まっていても退屈。いろいろな場所に行っても退屈。解消する必要はあるのか。暇と退屈は悪なのか!話せば話すほど聞けば聞くほど訳がわからなくなる根深い問題だなあと思いました。あの本を読んでも解決するわけもなく、理解できるわけもなく永遠に悩み続ける?のでしょうか。
Satoshiさん
色々と考えを深める機会となり、ありがとうございました。
長文になりますが、「暇と退屈」について参加した中で私の感じた事をまとめてみましたので投げさせて頂きます。
暇と退屈の出所は、「生(なま)の感覚への欠乏感」なのではないか。「暇と退屈」の対極は「生の感覚で行為している状態」。
「生の感覚」とは、目の前の現実に神経(感覚)が集中している状態であり、感覚器官・思考器官・身体器官等が「今」に統一されている状態。集中している状態と言えるだろう。 危機的状況・凄く興味を持って行為している状況等の集中状態。極まるとゾーンに入る。(因みにゾーンは集中とリラックス両方極まった状態。)熟練者の瞑想はこれを作り出せる。
そして集中状態は端的に内発的でしかあり得ない。
現代社会では自らの内発的行為が作り出しにくい状況が多く見受けられる。外因的なやるべき事、やらされ仕事、自分の納得に関係なく、他人が決めた法律・道徳・倫理の遵守等。
真に自分がやりたいと思うこと、やるべきと思えることをやっていないときに特に「暇と退屈」を感じるのではないか。
「生の感覚」への渇望への影響が考えられるものとして、
・自分探し(正に生の感覚探し)
・ホラー、怖いもの見たさ(恐怖という生の感覚)
・依存症全般(刺激による果てない生の感覚の渇望)
・窃盗などによるスリル(失敗出来ない集中による
生の感覚)
・性犯罪(スリルや、欲望という生の感覚)
・背徳感(背くスリルの生の感覚や、外因性への抵抗)
ここに、成功体験による報酬系の刺激等が絡んで来る。
この他にも大したこと無いことから、実害の大きいものまで、現代社会にはかなり多くの事に関連していると考えられる。「生の感覚の渇望」を何かに転嫁することで、捻れた感情が生まれる。
「暇と退屈」を感じることは「生の感覚の欠乏サイン」かもしれない。そんな時は自分と向き合い、本当にやりたいこと・やるべきと思うことをやっているのか、今目の前に有る状況でそれは作り出せないのか、それが難しい状況ならば趣味や別の行為で「生の感覚」を感じられる状況が作れないのか。
まとめると普通の事を言う形になるが、このような自己分析とそれに基づいた行動が必要になるのかもしれない。
よしださん
退屈というのは案外難しいです。感じたいか感じたくないかと言われれば感じたくないもの、明らかなのはそんなところくらいでしょうか?退屈と戦うことを表現するような文学作品もあるような気がしていて、それでは退屈に敗北すると大体変な方向に進んでしまう。敗北ってなんだ?という感じもするけど、退屈とはただ時間があってやることがないことではない。やることがあっても退屈に感じることはある。
戦地に赴いていれば退屈など感じないだろうと言われて納得しつつ、それであえて戦地とはいかないまでも戦いに身を投じたり戦いを引き起こしたりする人もいるのではないかと思ったり。それも一つの生き方なのだろうけど、そんな生き方は望んでいないのだけど社会のそういう雰囲気に巻き込まれているようなこともあるのではないかと思ったり。
人は生きるというのは奥が深い、深すぎる。深いし大変なこともあるけど、そこからはなんとなく逃れられないと思えば(例えばAIが仕事を代替しても新しい仕事が始まるだけ)、その大変なことが変なストレスは生まなくなる。変なストレスとは、「こんなはずではない」というストレス。こんなもんだよねと思っていれば「こんなはずではない」というストレスはなくなる。退屈もみんな感じるものでそんなに簡単に払拭できるものではないと思っていれば、長い目線でこつこつ解消の方向に向かうのではないだろうか、どうだろうか。
2025年6月8日(日):〈リベルの文化祭〉私のいちおし銘菓
yuさん
お菓子は好きなんですが食べ過ぎるのは良くないとセーブしているところでした。銘菓っていうと箱入りのその土地の名産品?。ケーキ屋のお菓子とはまた違った感じ?思いつかないと初めは思っていましたが話し始めるとかるかん饅頭、白玉饅頭、かすたどん、青島の外郎、鬼瓦も中、草木饅頭・・出るわ出るわ。紹介のお菓子を全部食べてみたくなりました。草加せんべい、南部せんべい・・お菓子は人の心を和ませる力があると思いました。
よしださん
僕が紹介したのは、「山ぶどう」。小さい頃よく食べていたから出身地の銘菓だと思っていたら、斜め下の県の銘菓であることが判明しました。でも?、参加者の誰も知らない銘菓だったので、すこしうれしい。のだけど、他の方の紹介した銘菓も全然知りませんでした。お菓子って大きなメーカー以外も本当にいろんなところが作っているなぁ。長く残っている銘菓は、素朴だけどおいしい、飽きがこない、そんなものなんだろうなとラインナップを見て思いました。マイナーアップデートは密かにしていたりするのだろうか。
2025年6月8日(日):〈リベルの文化祭〉今だから話したい、村上春樹のこと
かよさん
皆さんの村上春樹の観点を聞けて、楽しかったです。
「村上春樹の小説は ときどきロールシャッハ・テストである」
「村上春樹が小説を書くことは箱庭療法なのではないか」
この視点が、特に興味深かったです。
ありがとうございました。
yuさん
村上春樹のことを話すのは怖いところがある。苦手が好きに転じて読んできたので古いとかいろいろ言われると自分が責められた気持ちにもなるところがある。なんでなんだろう。このイベントにあたり、「風の歌を聴け」「午後の最後の芝生」「街とその不確かな壁」の短編。新しく読んだような気分にもなる。深読みは難しいのでみなさんと話して影の意味や魂の話など時間が足りないくらいでした。司会や発表の方、ありがとうございました。
よしださん
会の後のフリートークで、村上春樹は漢方薬みたいなところがあるということを聞いたのが印象的でした。たとえば、朝井リョウの『正欲」は最後にガツんと打たれるようなところがあり、自分のもつ世界観が揺らいだりします。村上春樹にはそういうところがあるのか、つまり最後まで読めばあっちから何かを明確に伝えてくるようなことはあるのか、と聞いてみたらそのような回答が。まだ、村上春樹の初心者、『ねじまき鳥クロニクル』の第一部しか読んでいませんが、長く付き合っていきたいと思います。
2025年6月1日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『ジーキル博士とハイド氏』スティーヴンス 村上博基 訳
街中で少女を踏みつけ平然としている男ハイド。その男は高潔な紳士であるジキル氏の遺産相続人。弁護士は訝りながらもハイドについて調べるところを読みました。あらかたの筋は知られている本だとは思いますが、未読の人にネタバレは禁止の本だなと思います。
2025年6月1日(日/午前):質問「 」について考える時間
この回の質問はこちらでした。
卵を立ててみたことがありますか田中未知著『質問』(文藝春秋)
yuさん
質問:「卵を立ててみたことがありますか」
・新しい10円玉は、たてたことがある。
・卵は白みだけ。メレンゲを思い出す。
「卵を立てるコロンブス」と言う言葉があるそうです。意味は独創性を議論する。最初に発見して公表するのは難しい。メレンゲしか思いつかなかったので新しい発想になって面白かったです。
2025年5月31日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
Takashiさん『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』村上春樹
小説の中の街は主人公が作り出した観念の世界で争いも変化もない安らかな世界だ。その街の住人になるには心を無くさなければならない。しかし主人公は心である影を外に逃がしたまま、街には入らず苦しみながら生きていくことを選ぶ。
まるで若い頃の村上春樹の決意表明みたいだ。自ら作り出した緻密な観念世界に安住すれば幾つもの小説を書くことはできるけれど、そうはしないで、常に変化に苦しみながら小説を書いていくぞという宣言のように見える。
よしださん『人類の進化大図鑑』アリス・ロバーツ編著
やっぱりいつも不思議だなぁと思うのは、生きていくだけで大変だったであろう頃から装飾品というか芸術的なものにヒトが時間を使っていること。今日みたところでも、何かの牙を使ったネックレスがありました。
それだけ身に付けるものが普遍的に人類にとって大事なものだったのか、(いい意味での)暇があるかどうかなんて結局主観の問題なのか。
2025年5月21日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』ニコラス・A・クリスタキス/ジェイムズ・H・ファウラー
人は人を介してつながっている。さまざまな集団にはそれぞれに中心というかハブになっているような人がいて、その人がいなくなると途端に集団は不安定になりときには瓦解する。ということが書いていて、その続きがセンシティブではあるのですが納得させられるものでした。すなわち、神のような不滅で誰もがつながりをもっている存在は、常に集団の中心であり続けられるので集団は安定するということです。
このことに関わらず、存在を単に否定するのではなく、それが在ることの意味を考えられるようになりたいなと思いました。
2025年5月18日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『イギリス人の患者』マイケル・オンダーチェ
イギリス人かどうかわからないくらい負傷した病人の過去の話。なぜ恋に落ちたのか。ねじまき鳥を読んでいる他の参加者が、記憶が改竄される話をしていて私もあるなあと思いました。昨日天気予報では大雨で実際は晴れて、今日昨日は雨だったと思い込んでいました。他の人と話すことでそれに気がつきました。
2025年5月18日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『エジプト人シヌへ』ミカ・ヴァルタリ
シヌへの物語は紀元前3500年前の古代エジプトが舞台です。シヌへは医者でその人の一生が描かれています。史実に登場する人物が散りばめられ、初めに回想なのでまだ生きている?人って変わらないんだなあと感じます。登場人物の直接的で長いセリフがたくさんありました。
よしださん『つながり 社会的ネットワークの驚くべき力』ニコラス・A・クリスタキス/ジェイムズ・H・ファウラー
人同士のネットワークは、名前を挙げられる友達同士とかそういうレベルではなくあって、感染症の蔓延とか流行とかそういうところで膨大なものであると感じられるはずです。
今回読んだところでおもしろかったのは、グラミン銀行は人のネットワークを担保にした融資の仕組みであるということ。通常の融資は、土地や建物を担保にしたり、勤務先で信用評価したりして貸し出しを決めます。しかし、途上国のそのような担保や信用がない人はどうすればいいのか。そういう人たちがお金を借りられないところに、少額でも融資する仕組みを作ったのがグラミン銀行です。
その担保は人のネットワーク。具体的には、5人のグループを作って、まずは2人に貸してその2人が返済できれば、次の2人に貸してというもの。連帯責任を想起させますが、その5人グループは自主的に作られるものみたいなので、その覚悟というか責任はあらかじめお互いにもっているはずです。そしてたぶん助け合いの関係にあるはず。
グラミン銀行の本は前に読んだことがありましたが、その本はその事業による成果とか社会問題に目が向けられたものでした。もちろん仕組みにも言及していましたが、今回のようにネットワークを担保にしたというところまでシャープな視点ではなかった。難しい問題でも、大きな視点の切り替えでソリューションにまで持っていけるというところに希望を見たような気がしました。
2025年5月18日(日/午前):質問「 」について考える時間
質問はこちらでした。
影を邪魔だと思ったことはありますか田中未知著『質問』(文藝春秋)
yuさん
影を邪魔だと思ったことはありますか?でした。写真を撮影するときの影はすぐ思いつきました。探偵のかげ。あの人には影があると言うふうな影。黒いイメージです。
2025年5月13日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『日本国民をつくった教育 寺子屋からGHQの占領教育政策まで』沖田行司
江戸時代の教育は、武士の特に長男などは義務教育的に藩校に何年とか入らなければいけなかったものの、それ以外の身分の者はそうでもなかったようです。義務教育がある今とは違うということです。そうなったときに寺子屋には別に行っても行かなくてもいいし、学習達成目標も特に義務のものはないわけです。
松下村塾や適塾などの私塾も同様です。行っても行かなくもいい。私塾は入ったからには厳正な階級性などをしいていたところもあるようだけど、それもある意味では本人の自由。途中でやめても良かったのではないかと思います。
今と比べてどっちが良かったかと言われると難しいところですが、とはいえ義務だと言われなければ勉強しなそうだし、勉強して知識をつけなければ考えることもできない。そうなると、いいように使われるだけの存在になってしまうかもしれない。そんなことも思いました。
だけど、多額のお金を払わなくても基本的なことを学べる寺子屋や、やる気さえあれば入れる私塾のようなものは貴重だなと思いました。思い立ったときに学ぶ場があるということは、とても大切なことのように思います。
2025年5月11日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『日本国民をつくった教育 寺子屋からGHQの占領教育政策まで』沖田行司
朱子学とか寛政異学の禁とか、高校の?日本史で出てきた記憶があるワードが出てきました。なるほど、ここらへんは国家運営と教育の関係を考えるのに必要な情報なのだと今回思いましたが、それをまさにその教育を施されている側である高校生で理解するのは難しいだろうなと。
江戸時代は封建社会でありながら藩校に代表されるように、中央からの統制はそこまでされずに自由度があったのだなと思いました。明治維新後は統制されていくのだと思いますが、前に読んだ『五色の虹』では満州に大学を作りながら日本政府(軍)はあまりその内容には興味がなかったりも。教育とは、それこそ古代から普遍的に存在するものだと思いますが、政治との距離感はその時代の為政者や状況などによって異なっていたのかもしれません。
2025年5月4日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
ブリトニーさん『半島』松浦寿輝
筒井康隆の「エロチック街道」に影響を受けて書かれたとのこと。
この人の小説を初めて読んだのですが、品の良い言葉がとても好みでした。場所や時間が全て暗がりへ、地下へと沈み込んでいく展開が何度も出てきます。温泉の先にまた温泉があり、スキンヘッドのダンサー5人が湯浴みをしていたり、島の洞窟の中を気が進まぬもどこへ行くのかわからないトロッコに乗せられてしまったり、夜の海に漂って沖まで流されてしまったら女性の死体が浮かんでいたりする場面が特に好きでした。
また参加したいです!
2025年5月4日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
Takashiさん『NEXUS』ユヴァル・ノア・ハラリ
この世には科学で解明できないことがあるけれど、それは科学が原理的に持つ自己修正プログラムのせいなんだろうと思う。多くの事象にあてはまる科学的な説があって、その説を使えばスマホが作れるけれど、その説はいつでもひっくり返る可能性があることを皆信じている。そういう意味で科学は何も解明していないし真理を述べてはいない。科学は常に心もとない。
一方でお金や社会や宗教の世界は原理的に自己修正プログラムを持たない。そのため修正に必要な仕組みを用意しなくてはならない。自己修正の判断基準となる人命でさえ戦争の前では境界があいまいになる。
科学もお金や社会や宗教と深くかかわっている。世の中は複雑だ。
2025年4月29日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
ishiさん『メインテーマは殺人』
前日までアガサ・クリスティの音声読書をしていたのですが、今回こちらの読書会に初参加するのを機に、今まで読んだことが無い本を音声読書してみようと思って選んだ本です。クリスティの後継者と言われているミステリー作家さんだけあって雰囲気は似ていますが、当然ながら100年前が舞台のクリスティと現代が舞台の小説ではまったく異なるのに、ついクリスティ気分で脳内イメージしてしまい、携帯電話やスターバックスやDNA判定などの言葉が出てくるたびに、現代だー!とギャップを感じたりしました。まだ最初の部分だけしか読めて(聞けて)いないのでストーリー自体に関しては特に感想はないですが、良い機会なので読了(聴了?)できるよう頑張ります。
全体の読後コメントで皆さんのお話をきいて、書籍の感想から話がどんどん展開し思いもよらないような方向で盛り上がるのが楽しかったです。ひとりで読書しているだけでは味わえない読書会ならではの醍醐味だなと思いました。
2025年4月27日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
Eimiさん『楽園への道』 バルガス=リョサ
バルガス=リョサについてなんの前情報も無かったので検索してみたら今月お亡くなりになっていたことを知りました。
色々な発言が取り上げられてきた方のようですが、近年にフェミニズムについての批判をされたようですが、この小説の2人の主人公のうち片方のフローラは確実にフェミニストだと思います。
リョサが描いたフェミニストのフローラと、リョサが批判したフェミニズム…。
早くも「ほほう、興味深い」と思いました。
そのフローラともう片方の主人公のゴーギャンとに温かい眼差しを送るような文体で進むお話は章に分けて交互に2人を描いています。
画家のゴーギャンは知っていますが、社会活動家の祖母のフローラについては全く知りませんでした。
巷で「怒りん坊夫人」と呼ばれてしまっているエネルギッシュで孤軍奮闘するフローラに「頑張れ〜」とエールを送りながら読んでいます。
ゴーギャンの方はタヒチに来たけど生活が成り立たずフランス人に帰国するのに、またタヒチに行ってるみたいですね。
祖母の血は孫にどう受け継がれたのか、これまた楽しみです。
読書会の後の雑談で長編小説について話題になりましたが、やはり生きてるうちは『ユリシーズ』と『失われた時を求めて』の読了を目指したいと思いました。
Takashiさん『NEXUS 情報の人類史』ユヴァル・ノア・ハラリ
まだ上巻の途中までしか読んでいませんが、「情報の人類史」のタイトル通り、情報という切り口でサピエンス全史で語れなかったことを論じた本のように思えます。
今日読んだところは、印刷技術について。
印刷技術は聖書をカトリックから解放したという技術の勝利としてよく挙げられますが、同時に魔女狩りも広めてしまった負の側面もありました。
根拠がない情報であっても、大量にそれが出回って、多くの人によって情報の補強が繰り返されれば人々はそれを信じてしまいます。中世で魔女狩りが信じられたのと同じように、現在私が信じているものは、ひょっとしてマスコミやSNSによって広められた根拠のない何かかもしれないと思いました。
yuさん『イギリス人の患者 』マイケル・オンダーチェ
土屋政雄 訳
イギリス人の患者は第2次世界大戦の終わりごろのイタリアの山の中腹にある廃墟のような屋敷で暮らすイギリス人の患者と看護師の話です。今日読んだところは看護師のハナの古い知り合いの元泥棒が訪ねてきて古い記憶を思い出しているところです。
風や自然描写が細かくあり登場人物は女・男と表現されています。諦めと不確かさとが感じられるようでした。
2025年4月27日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
なるさん『ブランディング・ファースト』宮村岳志
チャプター1の半分くらいまで読了。
「ブランドとは柱、ブランディングはその柱を育てていくということ」という言葉が印象的でした。そのためには、柱となる「競合と違った点」を見つけ、製品(やサービス)にストーリーを付加し、育てていくのが大事だそう。でも、実際はなかなかこの通りに難しいな、というのが全体を通しての感想です。
「強みや尖ったところって自分のプロダクトだからこそかえって気づかないのかもしれないね」という他の参加者さんのご意見に納得させられました。プロダクトの作り手としては全部が「良いもの」のつもりで作ってたり、思い入れが強い箇所があるから、客観的に見た強みを見つけるのがまず難しいのかもしれません。
2025年4月20日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『サロメ』ワイルド
・平野啓一郎訳で読みました。戯曲です。本文より解説と注釈が多いなと思いました。原文に忠実に訳したが1箇所だけ変えた部分があると書かれていました。モローでもピアズリーでもない平野訳。
オープンダイヤローグの本を読んでいる方がいて一旦意見はお盆に乗せて受け取れるものだけ返すというのが印象的でした。
Eimiさん『灯台へ』 ヴァージニア・ウルフ
一度は第一部まで読んだのになんだかわけがわからない感じでもう一度最初からじっくり腰を据えて読み直し、ようやく第一部を読了しました。
感想のシェアの時に他の参加者の方がウルフの文体についてフォークナーなどと同じ「意識の流れ」とおっしゃっていましたが、私はフォークナーの『響きと怒り』の最新訳で惨敗しておりまして、何が何だかわからないままに話が終わってしまったのです。
それに比べたら『灯台へ』はまだ多少は分かりやすく感じます。
『響きと怒り』を読んだのも全く無駄にはなっていないのかも、何事も経験してみるものです…。
ウルフの人物と自然描写が大変細やかで、人物像もよく練られていて、「うーん」と唸らされます。
第二部の冒頭を少しを読みましたが、何人かの登場人物が亡くなった模様です。
帯に「描かれるのはたったの2日のできこと。文学史を永遠に塗り替えた傑作」と書かれています。
いよいよその2日目に入って、この「傑作」は私をどう振り回すのか今から楽しみです。
が、起承転結で説明できる小説ではないので、読書会の感想のシェアタイムは冷や汗かきつつしどろもどろです…。
お聞き苦しかったら申し訳ないです。
2025年4月20日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
Eimiさん『灯台へ』 ヴァージニア・ウルフ
登場人物の中に絵を描いている女性がいるのですが、目に映るものをキャンパスに描写することの難しさを心の声として語っている場面があります。
私も絵を描くことが好きで、それで彼女のもどかしさや悔しさについてはとても理解できました。
しかし(絵の)描写に苦しむ人物を(文字で)描写するウルフの口ぶりはとても良く書けていると思います。
登場人物達同士の会話はほとんどなく、彼彼女らの心の声をかわるがわる書いていく文章で構成されていますが、個性的な人物像の描き方がとても鋭くて幾度も「うーん」と唸らさせています。
よしださん『日本国民をつくった教育 寺子屋からGHQの占領教育政策まで』沖田行司
寺子屋は19世紀から増え始めたとのことです。江戸時代の終わり頃には2万近くもあったのだとか。人口比でいうと今の小学校と同じくらいの数なのだそうです。
ChatGPTの力も借りながら調べてみると、1850年頃の識字率は男性40〜50%、女性10〜20%とのこと。男性に限って言えば同時代のイギリスやフランスと変わらないのだそうです。明治維新前の、欧米からは文明的に大きく遅れていたとされた日本において、識字率の高さというか教育の行き届きには驚き、なぜなのでしょう。
19世紀から寺子屋が増えたのは、農業技術の発達に伴い知識の習得が必要になったり、商業の発達により契約書の作成などが発生したり、貨幣経済も発達したりといった必要性が一つの要因のようです。それでも、これだけの寺子屋が都市部中心ではあったようですがボトムアップで出来ていったことは驚きです。今のように国家主導ではなく、教員という資格や職業の人ではなく、教えられるだけの学力があった人が教えていたとのこと。ここらへんは日本の良さなのかなと思いました。
2025年4月19日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『日本国民をつくった教育 寺子屋からGHQの占領教育政策まで』沖田行司
戦後教育の話がメインな感じがしますが、僕自身は寺子屋に興味があって手に取りました。自然発生的に全国的にそのような動きが起きて定着したのはなぜなのだろうと。
今日が読み始めなのでまだ全然序盤です。大昔は貴族や武士に教育の場があったようです。それはいわゆるエリート教育というか、武士なら家を守っていく必要がありますからたぶん長男メインで(?)武士としての心構えや家長としてのあり方などに通じることを教えられていたかな?などと。しかし、同時に庶民にも教育というか学ぶ場が溶け出していったというか、庶民にも教育の場がないとねみたいな考えはあり、ちょこちょこできていったようです。寺子屋がどのようにできていったのかはこれからなので、楽しみです。
2025年4月13日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
Eimiさん『DUCKS(ダックス)』著者 ケイト・ビートン 翻訳 椎名ゆかり 出版 インターブックス
2005年、21歳の主人公ケイトは学生ローンの返済のために時給の良さで男社会のオイルサンド採掘の現場で働くことに決めた。
その後の二年間をグラフィックノベルにしたのがこの本です。
オバマ元大統領も2022年のベストブックに選んでいます。
氷点下の職場も寒いけど、心はもっと寒くなりそうな体験で「アレ」「モヤ」「オヤ」とすること度々。
男性からのセクハラがすごくて。
でも環境が人をそうさせているのかな、って思ったり…。
日本版のサブタイトルには「仕事って何?お金?やりがい?」とありますが、壁は仕事内容云々の前のところにあるような。
まだ三分の一しか読んでいないのだが、この後ケイトは辛い思いをしそうで怖い。
でも彼女は実際に漫画家になってこの本を執筆したのだから、アート系に進学したことを無駄にはしなかったのはすごい。
ただ日本の漫画に慣れてしまっていて、淡々とした絵面が多いのもあり表情読み取れないし、登場人物の顔の区別がつかない…。
読むペースが漫画のようなペースにならないのはそのせいだろうか。
yuさん『女の子のための西洋哲学入門 : 思考する人生へ』[著]メリッサ・M・シュー、キンバリー・K・ガーチャー
芸術の章を途中まで読みました。芸術哲学者は、どのようにそしてなぜ芸術家はその人が制作するものを制作するのか、またその人の作品がどのような影響を我々にもたらすのかが論じられていて、2人の画家を例に、ハンナアレントの見解が出てきました。
2025年4月12日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『女の子のための西洋哲学入門: 思考する人生へ』著メリッサ・M・シュー、キンバリー・K・ガーチャー.
この本は過去の哲学者の考えの入門ではなく現代の女性哲学者の考えがまとめられています。6章〜7章の途中まで再読しました。それぞれの章で論じられる映画や人物がいてそれらについて語られています。元々の人物や映画から見直してみたいと思いました。倫理学・会議主義・科学・疑いがテーマでした。
よしださん『熟達論 人はいつまでも学び、成長できる』為末大
為末さんは、スポーツの運動の機構や心理を言語化していて、いつもおもしろいなと思いながらブログを読んだりYouTubeを見たりしています。運動は意識では整理ができないほど、速く・いくつもの部位の動きが連動していて、それを言語化しようとすると逆に調子を崩すなんて話を聞くことも。でも、そんなことはないのか、どうなのでしょうか。あとは、この本ではないですが、「やる前からダメな結果になることが分かっていることがあって、そのときはスタート前からどう収めるか考えている」なんて、ちょっとしたタブーを口にすることもあって、そういうところもおもしろいです。その視点でみると、この選手は今日はここでせめて見せ場を作って終わろうとしているのかな、などと憶測がついてスポーツ観戦もおもしろくなります。
前置きが長くなりましたが、この本では熟達を5段階で整理していて、一番最初に「遊」がきています。遊ぶことは、自分に制限を設けることなく、思いきり体を動かすこと。逆に正しいフォームを身につけようとすることは、常に正しさの枠に動きが沿っているかを意識し、自他の評価を気にすること。そんなことが書かれていて、なるほどなと思いました。無意識にでも、思いきり動かしてその記憶をしておく。その上で、制限を付けたり矯正をしていく。その、あの頃の記憶、みたいなのが大事なのだとしたら、やっぱり子供の頃は遊ぶのが大事なのだろうと思いました。大人でも遊ぶことから入る、遊びに戻ることが大事なんだろうなと思ったり。
2025年4月12日(土/午前):質問「 」について考える時間
この回の「質問「 」について考える時間。」の質問はこちらでした。
自分に足りないものがあるとしたら何だと思いますか田中未知著『質問』(文藝春秋)
yuさん
最近、基礎的な知識を学び直したいと感じていたところでしたのそのことについて話しました。数学・語学・歴史・有名な本・音楽など。それと忖度についても足りていないと感じています。
2025年4月6日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『梅干しを漬けてわかること』有本葉子
生活雑貨の店においてあり気になり手に取りました。梅干しをつけることで季節の移ろいやその年の気候変動なども感じ取れるそうです。実際に行うことと想像することと知っているだけのことはかなり違うなと感じました。
2025年4月1日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『バブル 日本迷走の原点』永野健二
バブルのことなんだけど、「日本迷走の原点」とあるように、その後の失われた20年を経て2016年に出版された本のようです。
まだ序盤ですが、企業経営における財テクっぽい片鱗が思える出来事が紹介されていました。ある手法を用いることによって、自社株式が1年少しで10倍以上になり、その1年後にはさらに3倍になる。その株式は、第三者割当て増資で引き受けた先があったので、その引き受け先は3年に満たない期間で引き受けた株価が30倍になったことになります。それはB/SやP/Lに影響します。なんか、地道にコツコツ稼ぐのってバカバカしいよねと思っても仕方ないなと思ったり。
もちろん、30倍になった保有株式は、また1倍に戻ったり0になったりするリスクがあります。ダイエーとか、上がり続けると想定した不動産を担保にして金を借り続けて拡大して、その上昇が下降に転じた時に、まさに天国から地獄へと急転直下したみたいなことも観たことがあります。
神話といえば神話なんだけど、何も信じずに生きるなんてことは考えにくい。すこしバブルの世界に浸ってみたいと思います。
2025年3月30日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
yukikoさん『自分の小さな「箱」から脱出する方法』
2年前に購入した本でしたが、ふと読み返したくなって、今回の読書会で読み返し、
その時には腑に落ちなかったモノが今回はクリアに、はっきり理解することが出来て、
清々しい気持ちになりました!
この本を簡単に言うと、人は自己欺瞞という箱の中に閉じこもりがちだよね?
そして、上手くいかないことを
相手や会社のせいにして、自分が悪いとは思わないよね?という内容です
(ものすごく略しています)
でも、怖ろしいことにこういう人が上司だったり、家庭にいると、
病原菌のように蔓延して、箱の中にいる人ばかりになり、
その組織は機能不全に陥り、お互いを責め合うだけで、何の進展も
ない関係性になるそうです。
ちょっと在りがちな世界。
読書会の時間では1/3程しか読めませんでしたが、
その後、読み進み、箱から脱出する方法が書いてありました。
その言葉は
簡単そうで、中々出来ないですが、
「自分は間違っているかもしれない」と気付くことなんだそうです。
悪いのは自分かも?と自分を疑えということでした。
2025年3月26日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『現実はいつも対話から生まれる』ケネス・J・ガーゲン/メアリー・ガーゲン
タイトルの通りのことを思うことがあり、手に取った本です。
人間にとっての現実とは、ただ目の前にある物質的な世界だけではないと思います。誰かがこう思っているとか、未来はきっとこうなるとか、昔こんなことがあったとか、そんなことが大いに織り込まれています。
前にこんなことがありました。「何年か前に一緒にこんなことしたよね」と言ったら、「いや、そんなことはしていない」と明確な否定が返ってきたのです。そんなにきっぱりと否定されると、「あれ?あれは夢の記憶なのかな?」と急速に不安になっていきました。つまり、現実だと思っていたことが、対話によって非現実になりました。本のタイトルとは逆ですが。それくらい、人の現実とは他者との間に存在しているように思います。
ほかにも、自分のなかでは決まっているのに、ただ背中を押してほしくて相談をすることもあると思います。相談をする前から、別に自信がないとかそんなわけではないのだろうけど、同意されることでそれをやることが当然のことのように思えてくる。自分のなかで現実的になり、現実的だから一歩を踏み出すことができるように思うのです。
人は何かとの間に物質以上のものを生み出し生きているのだとすれば、現実はいつも対話から生まれるように思います。ちなみに、ダンゴムシをじっと観察して、あれこれ思考を投げかけるのも対話であると僕は思っています。
2025年3月22日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『エジプト人シヌへ』下巻
医師のシヌへが各地を旅してエジプトへ帰還したところを読みました。この本は七十年前くらいにフィンランドで書かれた小説かと思って読んでいたら、エジプトには「シヌへの物語」という現存する最古の写本は紀元前1800年ごろが存在するのを知り、今読んでいる小説とそれは関係があるのかなと思ったところです。
2025年3月22日(土/午前):最近気になっているテーマや本など
yuさん
気になっていることを話しました。成田さんが「大抵の人の人生はそんなに大したことにはならないから心配しなくてもいい」のようなことを動画でおっしゃっていて、モンテーニュも同じようなことを伝えていて。そうか、楽しむことが大事なんで、そんな物事大袈裟に考えなくてもいいよねって思っていたところでした。参加者で美術館に今日は行くけど意味がないと言えばないかもとおっしゃっていて、話していくうちに「人生どれだけ意味のなさそうなことができるかがいいよなあ」と何ともなしに思いました。
2025年3月19日(水/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『進撃の巨人 33巻〜34巻』
・進撃は何を伝えたかったのだろう。エルディア人とマーレ人が争っている。巨人も人も壁の中も外も同じで私たちは無知から誤解しあっている。巨人には意思能力のなさそうなものからアニやベルトルトのようなのもいる。それも人間と同じでだんだん巨人もグロテスクな様相だけど人間に見えてきた。2000年の歴史の繰り返し。始祖の巨人と9人の巨人。何を表してる?伏線は回収されてきたような。誰が推しかなあ。強くて美しくて孤独なアニかな?あと1巻で完結。宿題の漫画でした。私たちは、何のために戦うのか。
2025年3月18日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『世界一シンプルな進化論講義』更科功著
読書会の後に微妙に残った部分を読んでいると、そこに興味が向いてしまう話が。
この本は進化の話ですから、それに合わせたかたちで「意識」の話が出てきました。生物は生存に優位になるように進化する、ということを前提に話されます。いわゆる自然淘汰です。興味深かったのは以下のところ(P270)。意識には生きる上でどのようなメリットがあるのかという話の流れで、
「しかし、メリットとは別に、決定的なことが一つある。それは、「意識」には、自己保存に対する強烈な欲求があることだ。私たちにしても、生きたいと思うのは「生物学的に生きたい」のではなく「意識を存続させたい」からではないだろうか。」
つまり、「意識」は生きるための手段として進化したのではなく、「生きる」と同様な目的なのかもしれないということです。なんだか妙に納得してしまいました。
2025年3月16日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『エジプト人シヌヘ』上巻 ミカ・ヴァルタリ (著)
第7の書「ミネア」を読みました。古代エジプト人の医師シヌへの旅の物語です。ヒッタイトにいてこの国の法律のところを読みました。病を恥と考えていたそうです。それぞれの神やくさび文字を粘土板にきざませるなど。奴隷や身分差、金持ちと貧乏人。3500年くらい前の話ですが人間ってあんまり変わらないんだなと思いました。
今日は2人の参加でした。読書会後は、休みになにしてたか、映画館で映画を3本みて夜中になったなど話しました。
2025年3月16日(日/朝):〈お試し企画〉散歩して書く会(仮)
朝6時から開いたお試し企画です。初めての試みでどのような感じになるかわからなかったので、運営グループ内だけで参加者を募りました。
〈ながれ〉
1. まず30分間外を散歩する。
2. 戻ってきて30分間文章を書く。
3. 散歩して、文章を書いた体験について話す。
しょうごさん
とりあえず家を出た。寒い。雨降っている。傘をさす。傘に当たる雨の音。パラパラではないぼつぼつって感じ。いつもと見慣れた光景。今日はいつもいかないところに行こう。数十メートル歩いただけで見知らぬ光景。いかにぼくがパターン化された人間か物語っている。いつも行くスーパー、ドラックストア、お弁当屋さん、コンビニ。家の近所に行くときはだいたい決まった場所で決まったものを買う。だたちょっと横道に入るだけで少しパターンから外れることができると思った。
住宅がたくさんある。よくもまあ人間こんなに家を建てたもんだ。家、家、家、家だらけ。だから家をよく見た。新築っぽい家、少し古びた家、かなり古びた家、空き家っぽい家たくさんあった。新築っぽい家はなんだか様々な種類がある、少し深藍色の家、赤みがかった家、ウッドハウスっぽい家。でも築50年過ぎてそうな家は判を押したように同じパターンがおおい。その築50年過ぎてそうな家の中にちょっとだけおしゃれな郵便ポスト。真っ黒で頭が大きくて、足が一本しかない、馬に乗った中国人っぽい少年が書かれているポスト。おもしろい。判をおされた中でちょっとしたおしゃれ。それが人生を豊かにするのだろう。
新築から築50年以上の家まで様々あったが、一見このなんの変哲もない住宅街も歴史を重ねてきたのだろう。様々に家が立って壊されてまた立って。でも壊されていない建物もあって。1つの地域で歴史の重奏的なものを感じた。
しかし、さすがに築100年はなさそうだ。地域の記憶も人間の寿命ぐらいの年月しか保持できないかもしれない。他の場所にいけば築100年の建造物を見れるかもしれない。しかし、維持するためになにか手は施されているし、なんの手も施されていなかったら、誰も住めない建物になってしまっているのだろう。人間の寿命を超えるとそれ以降はまた別のものになってしまうような感じがする。
もう少し歩くと、トンネルがあったそこを抜けたら夏にプールまで言った道に出た。そことそこがつながっていたのか。意外とそういう事ある。
yuさん
朝6時に、パソコンの前に集合して、30分歩いて30分書いて。
シェアの会に参加した。普段メモくらいしか書いてないけど書くことが気になり参加。
まず、朝6時に集合って起きられるかなって心配。
霧雨の朝。雨用のスニーカーを履いて家を出る。30分に戻ってくるには?ってタイマーをかける。目的地もなく歩くのってないな。樺沢しおんさんのYouTubeで「睡眠・運動・朝散歩」って基本のことを教えてくださっているのを見ていて気になっていたけどまったくできていなかったな。
まず、「歩いて書く」ってところから吟行でしょうと思い、「俳句手帳春2025」とペン・スマホ・家の鍵のみの持ち物。いつも飲み物を持ち歩きがちで重くなるけど身軽で気楽。過去に「俳句の会」に参加していたことを思い出す。いやいつも頭の片隅にあったかも。歳時記どこいった?
なんとなく家の周りを歩く。裏側にまわる。何かの香り、探す。
「未だ暗し つんと香るや 沈丁花」
うん。散歩していることもわからないし、沈丁花の香りはつんとしているのかな。香を表すのってどうしたらいいんだろう・・
「散歩道 なつかしき香や 沈丁花」
早朝ってわからんな。ん。
小さい古民家風カフェにオレンジの灯りがともってて窓際につばひろ帽をかぶった男性?が座ってなにか書いている?
あの店開いているのかな。店の周りをうろうろする。案内表示はなにもない。セロ弾きのゴーシュの世界みたい。
「春の朝 小さな窓辺 つば広帽」
ん。人がかぶっているってわからんな。
家に引き返す。
そこで23分経過。
書かないとなのにお湯を沸かし、豆を挽きドリップする。
時間ないのにしなくてもいいことをしてしまう。出勤前もそう。行動がワンパターン。
朝散歩って、大分県の日田市に民泊に行ったときのことを思い出す。
散歩に誘われて歩いた。クレソンがビニールハウスの近くにたくさん群生していた。採って食べた。そのお宅は湧き水の小さな池にグレーの鯉もいたな。
環境が違いすぎるな。
「大分の民泊の朝 小川のクレソン」
クレソン群生?野良のクレソン?
7時になった。オンラインで再度集まった。4名で感想のシェア。
・犬の散歩をした人
・昨日の読書会で「現代思想入門」が課題ではじめこわいと思ってたOさんに隙があって仲良くなったこと
・地域の記憶と人間の寿命について考えたこと
朝活、楽しかった。書くことって頭の体操なんかな。
tanakaさん
まとまった睡眠、久しぶりにまとまった睡眠をとったせいか、妙に元気。
外は雨。寒そう。ダウンとネックウオーマー、カイロを腰に貼り、ビニール傘を片手にもって、家を出る。春だから、と気分を入れかえて、歩く。散歩で見つけたものを意識的に探そう、それをあとから書こうとしているまったく創造性のない自分に少しウンザリしたまま、それを受け入れるようにして僕は雨の中をまえにまえに歩く。
家の前にレクサスが止まっていることにきづく。羽振りのいい奴がいるらしい。もしかしてこのレクサスは、大家が去年言っていた、5階のほとんど住んでいない、仕事の都合で5階を借りているという、あの人かもしれない、と書いているとき、きづく。
そして歩く。公園が見えて来る。いつもの公園。そして公園の向かいにあるA邸。家の中は真っ暗だから、Aさんはまだ寝ているのだろう。なんせ朝の6時過ぎ。しかも日曜日。
それにしても昨日のA邸のZさんの恐怖。いや、ほかの常連のおじさま方々が思いのほか優しいから、僕が勝手にA邸を安住の場に感じているそのギャップが、そう思わせたのかもしれない。博識すぎるZさん。その存在は闇のようで僕はさいしょ、とにかく怖かった。未知は恐怖。課題本の読書会。「眉唾物でしょ?!」とA邸の2階に響くZさんの裏声。
得体が知れないうえに、洗練されているZさん。
上品そうな紺色のセーターに、アイロンがびっちちりかかったベージュのスラックス、眼鏡はいかにも高級そう。大学の先生なのだろうか。いや、どうやら営業らしい。営業なのか?!この人が!と昨日僕は思った。
Zさんはずっと言っていた。「眉唾物ですね!この本!」眉唾物が口癖らしい。左手には課題本、右手には『構造人類学』レヴィ・ストロース。相当読み込んでいて、いたるところにマーカーが引いてあるのは「構造人類学」。レヴィ・ストロースは何度も何度も読み込んだ、と熱弁するZさん。いったい、いくつなのだろう、白髪や肌の感じからすると60手前くらいだろうか。レヴィストロースに魅せられた人は池澤夏樹といい、爬虫類に顔が似ている。そしてなぜかサルトルの顔になる、という滑稽なことを読書会の場で僕は考えていた。「これ、なんなの?!なんなの、これ?!」とZさんは絶叫していた。洗練されすぎているのに、感情表現が中学生と変わらないギャップ。まったく怖くない。そう、途中から僕はZさんのことが、全然怖くなくなった、だから仲良くなれた。ということに僕は書きながらきづいた。
散歩に話を戻す。さっきまでは暗かった空が明るくなり始めている。A邸の前の自販機でジョージア香るブラックを買う。職場で累計2000本は飲んだであろう、ジョージア香るブラックを、僕は久しぶりにA邸のまえで一口飲んで、そのおいしさにホッとする。そして書いているまさにいま、その香るブラックの熱は、すっかり冷めてしまてっいることにきづいた。
takashiさん
今朝は散歩して文章を書く会に参加した。今朝は犬と小雨の中を歩いた。
まずは犬のこと。
雨が降ると犬はやたらと地面を嗅ぎたがる。雨粒が何かを落としていくからなのか、土の中の生き物が活発に動くからなのか、理由は分からないがいつもと匂いが違うのだ。そしてこれも理由が分からないが、犬はそれを嗅がなければならないみたいだ。犬は嗅覚でできた世界像を持っている。彼らは雨が降るたび世界を組み直しているのだろうか。
次に人のこと。
犬を散歩させていると、同じく犬を散歩している人によく話かけられる。話しかけてくるのは中年以上の女性だ。私は男だが、犬を散歩させている男性どうしは会釈こそすれ会話することは稀だ。つまり私を含め、男は声をかけない。受け身なのだ。
人と人とのつながりはこうあるべき・・・なんて頭で考えているけれど、まず声掛けができるかどうかだよなあと思い返してみた。
〜主催者のしょうごさんより〜
3/16(日)午前6:00からリベル運営メンバーのみお試しで「散歩して書く会」を開催しました。この会は散歩をして外の世界から受けた刺激、身体の実感と、思考・制作をどのように接続するかがテーマになっています。
流れはまず、近所を散歩をして、文章を書くことを1時間程度した後、散歩してどうだったか?書いてどうだったか?を30分ほど共有しました。
やってみて、普段の読書会とは質の違う空気感でした。ゆるい感じというか。「家の近所にこんなのあるよ」というような話から入っていきました。
ただ、そこから俳句の話題になり、俳句を通じて体験とか、感覚をどう言語に落とし込むかという話になりました。同じ体験をしても、どんな単語を選ぶか、文の流れをどうするかで、だいぶ印象がちがいます。今後文章を書くうえで俳句を学ぶと表現の幅が広がるなと思いました。
2025年3月15日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『世界一シンプルな進化論講義』更科功著
今の地球をリセットして、もう一度ゼロから生命が誕生し、進化し、46億年経ったとき、今と同じような生き物のかたちになっているのか、そんな話が書かれていました。
同じようになるだろう派としては、物理法則は不変なのだから、それに応じた合理的な形態の生物になるだろうということ。たとえば、魚は水の抵抗を抑えるために紡錘形になるし、体重を支える限界としてゾウが最大級の動物であるだろうということ。
違うのではないか派としては、進化は複雑で偶然の要素も大きいということ。たとえば、カモノハシは哺乳類でありながら口ばしがあり水中で電気を感じながら餌を見つけるらしい。これはかなり特異な進化であるということ。
これらの話もおもしろかったのですが、進化は今でも続いていて、ホモ・サピエンスはわずか20万年しかまだ生きていないのだと実感しました。繁栄はしているのだけど、生命の歴史からすると今の段階では短期的な繁栄でしかないということです。これが長期で続くのか、確認できないのがなんだか少し残念です。
2025年3月4日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
丸山さん『裸一貫!つづ井さん』
話したいことを話せてよかった
よしださん『世界一シンプルな進化論講義』更科功著
一直線に早く進化する種や形質もあれば、寄り道しながらゆっくりと進化するものもあるというのが印象的でした。というよりも、進化は早いのか遅いのかが僕が知りたいことだったので、ドンピシャでした。
2025年3月2日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『有名すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む』ドリヤス工場
開始前から読みはじめ、「人間失格」「風立ちぬ」「ドグラマグラ」「イワンのバカ」「恩讐の彼方に」「布団」を読みました。紹介したのは「ドグラマグラ」で小説は長いのにすごく短くまとめられていました。記憶を失った狂人の独房にたずねてきた医者から君は「狂人解剖治療」の研究材料だったと説明され物語が展開されるのですが、狂人の視点で書かれているようで、フォークナーを思い出しました。
2025年3月1日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
Kenseiさん『アメリカは自己啓発本でできている』
引き寄せ系自己啓発本が理由を宇宙に求めたのは、単に宇宙という言葉がちょうど良かった可能性がある。
yuさん『金閣寺』三島由紀夫
吃音の主人公が大谷大学に入ったところを読みました。「幼年期の終わり」を読んでいる人がいて「だれかのせいにしたほうが楽」というところから、金閣寺での主人公の過去の出来事もだれかのせいにできる種類のものかな?と思いました。
お金の価値や自己啓発はなんのためになど、普段自分が信じ込まされているものはなにかななど考えるいいきっかけになりました。
2025年3月1日(土/午前):質問「 」について考える時間
質問はこちらでした。
想像しないことも歴史のうちですか田中未知著『質問』(文藝春秋)
yuさん
「想像しないことも歴史のうちですか」歴史は記録されたものなんだけど、もしをかんがえることも大事だし、記録された歴史自体も知らないことばかりだなと思いました。
2025年2月26日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『ジャンクDNA ヒトゲノムの98%はガラクタなのか?』ネッサー・キャリー著
タンパク質の複製の設計図となっていないDNAが98%もあって、それを役に立っていないものとしてジャンクと名付けたけど、研究が進むにつれてそのジャンクたちがさまざまな働きをしていたことを発見しているということ。読書会では、全体のどれくらいが解明されているのかという話になったりもしたけど、全体が見えていないから割合もわからない。そんなことの方が普通なのだろうけど、分かったつもりになる、分かったつもりでなければ動けないのもまた人なのかな、などと。純粋に、DNAっておもしろいなと思いながらちょこちょこ読み進めたいと思います。
2025年2月23日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『金閣寺』三島由紀夫
金閣寺は一度半分まで読んで挫折しています。1章から2章にかけて読みました。金閣寺信仰みたいだなあと思いながら読んでいます。主人公は父の死後、自分の少年時代にまるきり人間的関心というべきものが欠けていたことに驚いたとありいつの地点からの回想かな?と思いました。
2025年2月23日(日/午前):質問「 」について考える時間
質問はこちらでした。
物の表面と中身はどこで区別しますか
匿名希望さん
透明と不透明の話が印象的でした。
2025年2月22日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
takashiさん『超国家主義の論理と心理』丸山眞男
戦中戦後の分析と批判だが、何度読み返しても面白い。国の文化や形式が80年やそこらで変わるはずがないとすれば、本書は現在の我々に対する批判でもある。
日本人である自分の根底に流れるものを揺さぶられる本だ。『菊と刀』とあわせて読みたい。
2025年2月18日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『コミュニティを問いなおす つながり・都市・日本社会の未来』広井良典
個人は直に社会(集団全体)に出ているのではなく、コミュニティを介している、みたいな話がおもしろかったです。家族や会社などを通して社会に参加しているという意味合いですが、たしかにそうだなと思いました。なので、コミュニティは開いたものであるということ。
日本は、他の先進国に比べると、コミュニティが閉じていてソトとの接触も少ないという点が際立っているとのこと。それは、外に外に行かなくても成り立つ、ある意味では恵まれた農村社会が成立していたからではないかとのことでした。工業化が進んで都市部への移動があっても、そこに会社というムラができて閉じたコミュニティの中で生きていくことができたということです。
それがここ20年くらいで閉鎖したムラではいられなくなって変化を強いられているということ。終身雇用などが崩れたということでしょうが、ソトとの接触に慣れていない日本人はそこで不安や困惑を感じるということなのだと思います。そこらへんは、子供であれば教育を介して変わるチャンスがありますが、大人になったらどうなのでしょうか。大人はやっぱり自分でどうにかするしかない、自律的にどんどん変わっていくことが必要とされるように思います。そんな能力をどこかで獲得しておく必要があるのかなどと思いました。
2025年2月16日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『灰色のミツバチ』アンドレイ・クルコフ
ウクライナの紛争地域、狙撃兵と地雷に囲まれ、誰もいなくなった緩衝地帯《グレーゾーン》の村に暮らし続ける中年男ふたりの話。幼馴染だけど仲良くなかった2人。弱い立場のほうしかそれって覚えていないよねと思いながら。
2025年2月15日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『神は、脳がつくった 200万年の人類史と脳科学で解読する神と宗教の起源』E・フラー・トリー
神への信仰は、祖先崇拝から始まったというところを読んでいました。
人類の進化によって、省りみることができるようになったり、イマ・ココ以外の世界を想像できるようになったりして、死後の世界を思考できるようになったというのは分かります。でも、それがなぜ祖先崇拝につながっていくのかは今いち理解できていません。あっちの世界でも元気に、というのであれば他者の気持ちを考えるということで、分かります。でも、崇拝までいくのはなぜなのか。それはやっぱり、先を考えられるようになって生じるようになってしまった未来への不安を、長く生きた祖先に導いてもらおうということだったのか。
そうなると、祖先崇拝の延長線上に年功序列があるのか、などとも想像が巡ります。
2025年2月12日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『神は、脳がつくった 200万年の人類史と脳科学で解読する神と宗教の起源』E・フラー・トリー
今回は宴会の重要性について(?)。1万8千年前には複数の小集団がある時期(季節)に集まって、協力して狩猟した痕跡があるのだといいます。これはごく普通のことに思われるかもしれませんが、いくつかの点で画期的な進化的変化である言えます。
まず、「ある時期」ということは前々から計画していたということで、計画と実行の能力が備わっていたということ。そしていくつかの小集団が集まるということは、他者の考えを慮ることがより必要とされたということであり、それができていた可能性が高いということです。
そして、そのような変化を伴いながら、1万1千年前頃のものと思われるギョベクリ・テペという大規模な遺跡がトルコの南西部にあるのだそう。そのギョベクリ・テペは宴会場だったのではないかというのです。
人が集まり協力をするとき、宴会や祭りが必要だということなのでしょう。ギョベクリ・テペが最初から宴会場的な目的で作られたのか、後々そう使われるようになったのかは分かりませんが、太古の大きな労働力を費やした先に宴会場になるということには宴会への合理性をみたような気になりました。
2025年2月9日(日/午前):質問「 」について考える時間。
この回の質問はこちらでした。
一億円を一日で使えと言われたらどう使いますか
yoniさん
用事で読書会は不参加だったので、初めての投稿ですが「質問の会」で思ったコトを綴ります。
たしかお題は「一億円を1日で使うなら?」だったかな。
個人的にはバカなことに使ってしまうかも。良きことを考え計画する暇は、ない。そして熟考した後の結果に後悔しないかどうかも、分からない。
それなら、実現できないかもしれない「夢」に使うのだ!(オトコのバカなロマン?世界一周船の旅)
すぐアタマに浮かんだのは、ドイツ映画『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』で、マイフェバな1本。余命わずかな若者2人が、それぞれの夢を実現するために病院を抜け出し、ギャングの大金を手にして海まで旅する、最高のロード&バディなムービー。
彼らの夢はもちろん異なるのだが、お袋さんのための「夢」や男性としての「夢」を実現していく様子が、なにか可笑しいし微笑ましい。
そして一番のキモ一番の「夢」は、「海」を観に行くこと。2人のうち1人は今まで海を見たことがない。もう1人が言う。「お前がもうすぐ死んだあと天国に行けたとしても、たぶん孤独で辛い思いをするかな。いま天国では、海について話すのがブームなんだぞ(ジョーク)。死んでも仲間が欲しいだろう?さぁすぐ一緒に北へ行こう!」ドイツは北に海がある〜。
奇跡的な展開で邁進する2人は天使の化身とも思えて、コメディ色強いが個人的に深く思考に沈める作品。ラストには、ヤラれる…。
何度もビデオで観ているが、昨年ある大劇場の閉館前の特別上映にこの映画を観れたのが、もしかしたら私の「意図してなかったがささやかな夢」が実現したコトかも。交通費入れてわずか五千円ですんだが。
2025年2月8日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
匿名希望さん『ピクニック』今村夏子
ギャンブル依存の井川意高の本を紹介された方がいて、依存症についてのいろんな話が興味深かったです。自分は暇だとネットをよく見てしまいますが(ネット依存?)、参加者さんが「足るを知る」と言っていて、「今あることに感謝して満足したら」刺激中毒というキリのない欲から自由になれると思いました。久々に参加叶いましたが、ゆるくてウェルカムな雰囲気が心地よかったです。ありがとうございました。
yuさん『灰色のミツバチ』アンドレイ・クルコフ
ウクライナの現役作家の作品で、現在のロシアとの戦争のときの市民の暮らしがリアル?に書かれているのかなと感じました。村にふたりだけ、あとのひとは逃げた。たいして仲良くもない幼馴染。30分だけ電気が来てそのあいだに携帯の充電をした?というところを読みました。
雑談で、依存やチについてはなしました。ギャンブル依存から砂糖小麦依存まで。身近な話題につながりました。
Takashiさん『熔ける』井川意高
自分のグループ会社のお金106億円をカジノで使った元社長の懺悔録です。額が大きすぎるので庶民の感覚とは違うかもしれませんが、ギャンブル依存に興味があって読みました。
読書会では「秘密はよくないね」という感想を頂きました。確かに著者はギャンブルに嵌まる性格ときっかけがあったにせよ、誰にもばれない状況が続いたので借金も大きくなったのだと思います。透明人間になれる指輪を拾ったばっかりに、善良な羊飼いが大悪党になる「ギュゲスの指輪」を思い出しました。
秘密は毒なのかもしれません。
2025年1月29日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『神は、脳がつくった 200万年の人類史と脳科学で解読する神と宗教の起源』E・フラー・トリー
「出アフリカ」をホモ・サピエンスはしたのだけれど、そこまで世界中にまで進出していったことを不思議に思いました。
いつ出たのかは諸説あるようで、一つには7万年くらい前にインドネシアの山が大噴火を起こしその後数百年気候が変わったことに要因があるのではと考えられているそうです。その理由はよく分かります。環境に変化が起きて住みにくくなったのであれば、移動することも分かります。しかし、ホモサピエンスはその後数万年にわたって世界進出を続けます。まずはアラビア半島へ行き、そこからロシアやヨーロッパの方へと進出したグループもいました。しかし、それより目を見張るのは南へ行ったグループです。
当時は今よりも海水面が低く、地続きであったり海の隔たりが狭いエリアが多くありました。その環境下で、インドネシアなどの東南アジアの諸島へ巡り、さらにはそれでも海の隔たりが大きかったオーストラリアへも進出します。それはリスクがあったことでしょう。
なぜそこまで行くのか。気候変動で住みにくくなっても、それが落ち着いたり、新しい安住の地が見つかればそこに留まってもいいはずです。でもリスクを冒してまでも世界進出をした。それは単純に生きるため、なだけではない気がしてきて気になりました。
2025年1月26日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『枕草子』清少納言
84~めでたきもの:ほめたたえたくなるもの、なまめかしきもの、かたはらいたきもの:いたたまれないもの。あさましきもの:呆然とするもので何かをひっくりかえしてこぼしてしまったことの気持ちは今にも通じるけど、牛車がひっくりかえったのなどは時代を感じました。くちをしきもの:残念なもの。など。
読書会の課題で、電子で読んでいるところです。電子だと操作がなれないので紹介には向いていないなと感じました。
2025年1月25日(土/午前):読書のもやもやについて話す時間
今回のテーマは「読書会に何を求めているのか。コミュニケーションなど」でした。読書会の企画を考えている方がおり、その方から出された話題が広がってこのテーマになりました。
よしださん
人と話すということにはいろいろな意味が含まっているのだと思います。話すことで考えがまとまるというのもそうだし、他の人の意見を聞いて考えを深めるというのもあります。あとは、共有する。誰かと共有することで自分の中で作られた想像や考えが、現実世界に進出する。少し飛躍しすぎかもしれませんが、自分だけの世界にあったものが、誰かとの世界にも入り込むことで、社会への一歩を踏み出すというか、社会に出してもいいのだなと思えたりする、かもしれません。
読書は自分でするものという意見が出ました。誰かと一緒に読書をするという機会があっても、本当にこれ読んでるんだっけという感覚になってしまうという経験談も。読書は自分でするもの。もっというと、学習や作業の多くは自分でするものが多いというか、基本なような気もします。でも、誰かと話したくなるし、誰かと一緒にやった方がいいような気がすることもある。
僕の場合は、人と時間をともにするという基本的な充実感はもちろんありつつ、硬い方の理由としては集合知的な思考をさせてもらっているという感じがしています。どこからともなく予定不調和に展開される話を聴きながら思考することで、自分一人からは出てこないような疑問や問いや視点が得られていて、それがいいなと思っているのだと思います。
2025年1月15日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『進化心理学から考えるホモ・サピエンス』アラン・S・ミラー,サトシ・カナザワ
〈私〉とは何かと考えていったときに、生まれてきてから得てきた知識や経験だけではなく、生まれる前・はるか昔から連綿と紡がれてきた遺伝子の存在は無視できません。ダーウィンが言うように、生物は環境に適応するかたちで進化・変化してきたのだとすれば、今の〈私〉はどこかに確かに生きてきた生物の歴史を帯びて生きていると言うこともできます。その大祖先の適応を受け継いでいるのであれば、それに大きく反するような生き方は合わないものとなってしまうかもしれない、不自由につながってしまうのかもしれない、そんな風にも思います。進化心理学を学びながら、そんなことを考えてみたいと思っています。
2025年1月12日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『響きと怒り』ウィリアム・フォークナー
4部を読んでいますが、説明もなくどこを読んでいるのか迷路のようになりながら信頼できない語り手の句点のないとぎれのない思考を延々ときいているかんじです。
2025年1月11日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『ヒトラーとナチ・ドイツ』石田勇治
今日から読み始め、再読です。ヒトラーの生い立ちから始まりました。それを読んでいると、ヒトラーはどこかでハマったのだなと思えてきます。
元々は戦争や政治に関心が高いわけではなかったようです。この本のなかでは、周りをみてなんとなくうまく立ち回るような日和見的なところがあったみたいな記述も。
ただ、弁論のセンスはあったようで、第一次大戦のあとに思想教育を受けたあと、宣伝・諜報部にまわったそうです。その思想教育機関には反ユダヤ的な講師が複数人いたのだとか。
なんとなくですが、なにもないところに反ユダヤの思想と弁論のセンスが合わさってハマったのではないかと思ってしまいました。そこから一気にナチの総帥までいくわけではないと思うので、その後の段階を追っていきたいと思っています。
2025年1月7日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『神は、脳がつくった 200万年の人類史と脳科学で解読する神と宗教の起源』E・フラー・トリー
相手の気持ちを自分が考えられるのと、相手が自分をどう思っているのかを自分が考えられるのとでは、1段階レベルが違うみたいなことが書かれており、印象的でした。後者は、自分がどう思われているのかという思考が働くことを意味し、客観的に自分をみることになります。自己の認識につながるということです。ネアンデルタール人は、前者の思考まではできたけど、後者まではできなかったのではないかとも書かれていました。私たちホモ・サピエンスは後者の思考までできている、つまり自己を認識できています。
他者からの自分の見られ方を考えられるということは神の創造へとつながっていく、とも。よく「お天道様が見ているのよ」なんて言いますが、それはお天道様という他者が自分を見ているということを考えられるということを意味し、神の創造へとつながっていくということです。現代では神の話をすることは少なくなり、その一方で「自分でどう思うか」が問われることが増えてきたかもしれません。それは、神は自分になり替わったと言えるのかもしれません。別に自分が偉いとかそういう認識ではないと思いますが、私を支配するのは私になったということです。それが個人主義の一つの完成系であるとも言えます。
それが良いのかどうか。それは、私が私や世界をよく理解し、私と世界の調和のとれた生き方を選択できるという場合は良いように思います。でも、自制心が強過ぎたりすると、自分で自分を追い込みすぎることにもつながるかもしれません。個人主義とはいえ、閉じた個人の中で決めていく・生きていくというのは少し違うようにも思いました。話が広がりすぎました。
2024年12月29日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『失脚』デュレンマット傑作選
古典新訳文庫で4つの短編の中の1つです。登場人物がA~Pの人々が会議の中で話し合っている様子?でJがいないのは何故かな?と。秘密警察長官や国防大臣Hなど政治的?な会議でどこの国かや詳しいことはわからず今は置いてけぼりになっているところです。
善や道徳についてカントについて話題になりました。カントは難しそうですが正義の人だったのかな?と感じました。
2024年12月29日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
マークスさん『友だち幻想』
「気の合わない人とでも、少しはぶつかり合いながら、理解を深めていくと、自分の考えに幅を持たせる事ができ良いのではないか」という考えについて色々意見をお聞かせ下さり、参考になりました。
私自身初めての参加で、話す内容が整理されておらず、本の内容を上手く伝えられなかったのですが、皆さんは真剣に聞いて、ご感想も頂き、嬉しかったです。とてもアットホームな雰囲気で良かったです。ありがとうございました。
yuさん『ロンドリ姉妹』モーパッサン
フランスからイタリアへ向かう列車の中。男2人とイタリア人の女一人。男は女の気をひくためにあれこれと考え事をしていて美しい車窓からの風景は全くみていないところが印象に残りました。また、不機嫌な女が急に二人に同行することになってこれからどう物語が進むのか?
会では今年読んだ本やこれから読みたい本なども話して、来年の個人の課題本はどうしようかなと考えました。
Takashiさん『純粋理性批判』カント
岩波文庫上巻第72刷のP117に書かれている「『私』自体」という言葉は物自体と対比させて理解する上でとても良いキーワードだと思った。
しかし光文社古典新約文庫ではこの言葉は出てこない。ネットで拾った英文、独文テキストにも出てこない。岩波文庫の翻訳者である篠田先生のオリジナルの注釈なのか、それともどこかの原文に書かれたものがあったのか、どちらなのかが分からない。
どなたか詳しい方に聞いてみたい。
2024年12月28日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『神は、脳がつくった 200万年の人類史と脳科学で解読する神と宗教の起源』E・フラー・トリー
神は脳の生成物であるということを前提に、人類の進化、特に脳的なところが書かれているのでしょうか。今日が読み始めでした。
僕としては、認識の創造に関心があります。そして、認識は脳も関わっているのだろうけど、身体も関わっているのではないかと。仮に神は脳がつくったのだとしても、その神をつくるのは脳内だけの作用なのではなく、身体的な体験を伴うのではないかということです。筋トレをしまくっているといつしか無敵な感覚になるような、なったことはないですが、そんな身体性のある認識形成について今興味をもっています。
2024年12月27日(金/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『ロンドリ姉妹』モーパッサン
フランスから旅が好きでない男2人がイタリアに列車で行く。途中で20歳まえくらいのフランス美人に会う。しかし、ブレスレットが大きすぎるだのオレンジの食べ方でろくなしつけを受けていないことがわかるだとか、優美さが足りないだとか・・窓から見える香濃いオレンジや景色の長い描写が綺麗でした。
2024年12月25日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』今井むつみ/秋田喜美著
最後の方を読んでいました。チンパンジーとヒトの思考の違いについて書かれていました。論理思考の厳密さでいうと、もしかしたらチンパンジーの方が上なのかもしれなくて、ヒトの方が誤りが多いのではないかということ。
例えばヒトの場合、「これはバナナ」と教えてから、いくつかのフルーツの中から「バナナをとって」と言うとバナナをとることができます。しかしチンパンジーはそれができません。ではどちらが正しいかというと、実はチンパンジーだったりします。なぜなら、黄色い棒状のフルーツがバナナだということはわかっても、色々あるフルーツの中の黄色い棒状のフルーツだけがバナナとは限らないからです。赤い丸いフルーツもバナナかもしれないということです。しかしヒトの場合は、これがバナナというA→Xという学習をすると、X→Aという推論も本能的にするということです。結果的に、赤い丸いフルーツがあっても迷わず黄色い棒状のフルーツを取ることができます。
ヒトは推論をします。だから間違いも犯します。でも、その間違いは可能性でもあり、既存の枠を超えて飛び出すことにもつながる。その飛び出しの結果、失敗をしてしまうことも多々ありますが、その失敗や間違いを補正して妥当な解に近づいていく。ヒトの思考の本質は推論にあるのかもしれなく、その推論とは絶えず失敗や間違いのリスクとセットであるということはあまり知られていないけど大切な示唆であるような気がしました。
2024年12月22日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『エルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告』ハンナ・アレント
歴史的な事実がわかっていないと読み進めづらいなと思いつつ、アイヒマンに何らかの強烈な思想や意図はないのだろうなと思える記述でした。裁判で本人が話すのは、自分の功績めいたことやそれをキャッチコピーのようにまとめた一言の繰り返し。思想が強い悪であればいいということではないけど、何も考えていなさそうな悪に蹂躙されたというのもやりきれないのだろうと思いました。ただ、悪とは、企図する者はほんの一部で、加担する大勢はそういうものなのかもしれません。
2024年12月17日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『モラトリアム人間の時代』小此木啓吾
モラトリアム人間とは、立場を示さない、当事者意識のないお客様気質の人間のことと定義されています。中立とも違います。中立とは中立という立場を示しているからです。その場その場で言動を変える日和見的なところがあり、責任が発生しないような振る舞いをする人間のことをいうのだと思います。
さて、これは良いのでしょうか、悪いのでしょうか。僕個人の意見としては、何事も参加した方が(大変だけど)楽しいし充足感も得られるから、モラトリアム人間的でない方がいいとは思います。しかし、「そうですか、でも自分はこれでいいんです」と言われたら返す言葉が見当たりません。
人間の本質や普遍性とはどこにあるのだろうかと思うことがあります。例えば、労働をしていないと後ろめたい気持ちが起こるとします。しかし、それは周りがみんな労働しているからかもしれません。労働をしない人が一定数を超えたら労働をしていないことに後ろめたさを感じなくなるかもしれません。当事者意識があった方が充実感があるし、そうでなければ退屈だからどこかで責任をもって生きていくことになるだろう、という結論は早計なのだろうと思ったりします。これは、沼です。
2024年12月11日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『モラトリアム人間の時代』小此木啓吾
モラトリアムの意味とその変遷みたいなことが書かれているところを読みました。
モラトリアムは一般的に「猶予」というような意味があるらしく、人間に当てはめると、社会に出るための猶予期間ということのようです。元々は、医者や弁護士など、仕事に就くために事前の十分な勉強が必要な人に対して与えられる社会人になるまでの猶予期間という意味合いが強かったということです。
それが、時代とともに変わってきました。工業化が進むにつれて、医者や弁護士と同じように大学で勉強してから社会に出る必要がある人が増えてきて、モラトリアムを与えられるべき人が増えてきました。つまり、より一般的になったということです。
さらには、昔は師弟関係のように、基本的には年上の人から知識や技術を学ぶことが一般的でしたが、新しい知識や技術は年上の人から学ぶことができません。そうなると、いくぶん吸収力のある若者が重宝され、モラトリアムの地位が向上していきます。昔のモラトリアムは、その期間にいるのは一人前になる前の半人前の期間であり、認められないばかりでなく恋愛なども自由にできなかった。だから早く抜け出して一人前になりたい期間だったそうです。それが、モラトリアムの必要性のなかでその地位が向上し、なかにはそこに安住して抜け出そうとしない人も増えてきたとのことです。もう少し付け加えると、モラトリアム人間とは、単に社会に出ない・仕事に就かない人を言うのではなく、立場を示さない人・決めない人・(提供を一方的に受けその都度態度を変える)お客様気質の人を言うとのことです。これは定義の問題ではありますが、そのように記されています。
別の方が読んでいた本の話の流れで、責任の話にもなりました。何をやらかしても「それはあなたの責任じゃないのよ」と言われるような、責任が個人に帰属しない世界に生きるのはどうなのだろうということです。僕は前に少し想像してみて、それはさすがにハリがなさすぎて嫌だなと思いました。責任は押し付けられると嫌なのですが、自らもつのはそこまで嫌なだけではないような気がしています。モラトリアムという期間も必要だと僕は思いますし、それは働きながらでもこころの何割かはモラトリアムであるというのもいいなと思っています。でも、責任はもてていた方が尊厳や充足という意味でいいのではないかと思っています。
2024年12月8日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
まるやまさん『やる気とか元気がでるポスター』
サルトルの嘔吐、もっと内容がしりたくなった。
yuさん『箱男』阿部公房
今日読んだところは「Dの場合」:少年Dは強さに憧れていた:ある日ふとおもいついて一種のアングルスコープを作ってみることにした。アングルスコープが何かわたしにはよく理解できなかったのですがそのまま読み進め、隣家の便所を家人の目を盗んで覗く計画を立てて実行に移すところを読みました。覗く行為は箱男だなと思いました。他の参加者が読んでいた「嘔吐」で突然わけもなくおそってくる恐怖ってなんなんだろうと考えました。
2024年12月7日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『箱男』阿部公房
段ボール箱に入ってのぞきあなから町をみる。突飛だなとはじめは思っていました。読み進めるうちに自然と主人公が箱男の沼?にはまっていきました。今日よんだところは箱男となった自身の死体の捨て場処は、以前二人で打合せた、例のしょうゆ工場裏をすすめたいという箇所。どゆこと?となっています。それから安楽死に対する見解・・・・。きままな時間でモラトリアムについての各人の捉え方を話しましたが猶予というより異形?と感じました。種明かしがこれからのようです。
よしださん『モラトリアム人間の時代』小此木啓吾
今日から読み始めました。読書会の前の30分の「最近気になっているテーマや本など」で、「モラトリアム」に抱く印象などを聞いてアップを済ませてからの(?)読書でした。
序盤からモラトリアムの説明がされていて、印象的で分かりやすかったのは無党派の話です。無党派とは立場を明らかにしないこととこの本では書かれていました。何らかのテーマに関して立場を明らかにせずに、受け身的なお客さま気質で、当事者意識がない、そんな人間をモラトリアム人間と呼ぶそうです。
それがいいか悪いかは議論を深める必要があると思いますが、一つ良くないと言えることとしては、ナチス時代の社会が全体主義であり、その結果があのような非人道的な活動への加担につながっていたのではないかということです。当事者意識がない集団がなんとなく流されてある活動に従事していく、リーダーが悪であれば悪になりうるということです。
世の中には問題が多いので当事者意識をもてることには限りがあると思いますが、モラトリアムなだけではいけないなと思いました。ただ、モラトリアムは色々な使われ方をしていて、社会に出る前のあるいは社会に出てから一度立ち止まる・ペースを落とす期間としてのモラトリアムというのもあると思います。これは、多様性とか人生100年の時代には必要な時間であるような気もしていますが、混同せずに整理してみることで、モラトリアムの意味や問題性も分かっていくような気がしました。何気なく世の中にある言葉だけど深いなと思いました。
2024年12月1日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
かめさん『ミセス・ハリス、モスクワに行く』ポール・ギャリコ著
シリーズ四作目、最終話。そろそろ終わりという所から会で読み、読了。
1970年代のオイル・ショックの話で日本についても出てきますが、この件が事件?を解決する鍵になっています。
奇想天外にも思える筋運び、どんな立場の人とも通じ合ってしまう掃除婦のミセス・ハリス。今回は鉄のカーテンの向こうで、体制に引き裂かれた恋人たちを結びつけられるのか。大丈夫だろうと思いつつ、いやさすがに無理かもと読み進めていました。
大人のお伽話のようなこのシリーズ、なぜ作者が主人公をこのような人物に書いたのか考えていたのですが、参加者の方から、実際にあった社会的な事柄を取り入れている事が面白いと言われ、執筆時の社会の中で作者が言いたいことが、現在の私たちが感じる以上にあったのではないかと思いました。時代背景を調べ直そうかと考えています。
初めての参加でしたが、自分では読まない分野のお話が聴けて、楽しかったです。(小松左京が書店からなくなっている、というお話はショックでした)
Takashiさん『内田百閒』内田百閒(ちくま日本文学)
内田百閒は夏目漱石の門下生だった小説家で、本書は短編集です。
今日読んだのは「件』(くだん)です。件(くだん)という伝説の化け物になってしまった男の戸惑いを、どたばた喜劇のように書いた面白い短編でした。
私は件(くだん)の伝説を小松左京の『くだんのはは』で知りましたが、それよりも前に内田百閒が書いていることを今日まで知りませんでした。
2024年11月29日(金/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『別れを告げない』ハン・ガン
作家のキョンハは2014年の夏、虐殺に関する本をだしてから悪夢をみるようになる。一人っ子のインソンは、認知症の母親の介護をして看取った。20年来の付き合いの二人。疎遠になりかけていたところに、インソンがキョンハに身分証明書を持ってすぐきてくれる?とメッセージがはいったところを読みました。韓国の病院では看護師は医療以外の任務を担わないそうです。
2024年11月27日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『矛盾と創造』小坂井敏晶著
これの前に読もうと思っていた同じ著者の『答えのない世界を生きる』にはこのようなことが書かれています。「ナチスも、正しい世界を作ろうとした。その構想を誤ったのではない。普遍的真理や正しい生き方がどこかに存在するという信念自体が危険なのだ。」(意訳)
世界は正しい方向に進んでいると考える、そうするとある時そうとは思っていなかった人たちからの逆襲にあう。これは言い換えると、ある人たちは倫理的だと思っていたことが、他のある人たちからすると非倫理的であることだったとも言えるのかもしれない。『自由論』を書いたジョン・スチュアート・ミルは、未開人は自分たちが教育しなければならない、みたいなことを書いていた。
最近は正しさを非倫理的なものにしないためにはどうすればいいのかということを考えることがある。
2024年11月24日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
Takashiさん『内田百閒』内田百閒(ちくま日本文学)
私は内田百閒を初めて読みました。本書は短編・随筆集で、今日は夢の話みたいなものを幾つか読みました。これは何の比喩だとか、筆者は何を言いたいのかとか、難しいことはきっと他の人がやってくれていると思うので、私はそういうことは考えずに文章をゆっくり読みました。ひとつ引用します。
「高い、大きな、暗い土手が、何処から何処へ行くのか解らない、静かに、冷たく、夜の中を走っている。」(『冥途』より)
土手が夜の中を走っているように見えるのか~、なるほど~、みたいな感じが面白かったです。
2024年11月24日(日/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
Takashiさん『内田百閒』内田百閒(ちくま日本文学)
私は内田百閒を初めて読みました。本書は短編・随筆集で、今日は夢の話みたいなものを幾つか読みました。これは何の比喩だとか、筆者は何を言いたいのかとか、難しいことはきっと他の人がやってくれていると思うので、私はそういうことは考えずに文章をゆっくり読みました。ひとつ引用します。
「高い、大きな、暗い土手が、何処から何処へ行くのか解らない、静かに、冷たく、夜の中を走っている。」(『冥途』より)
土手が夜の中を走っているように見えるのか~、なるほど~、みたいな感じが面白かったです。
2024年11月23日(土/午前):読書のもやもやについて話す時間
今回のテーマは「本によって学び考えることと、身体的体験によって学び考えることの違いは何か」でした。
よしださん
僕が出したテーマでいろいろと考える時間になってありがたかったです。
身体性とは難しい概念です。その難しいというのは言葉で表現できにくいとも言えるのかもしれません。400mを全力で走ると疲れます。しかし、それは言葉で言うと「疲れる」ですが、そこには収まらない疲れがあります。苦しい、吐きそうとか、そんな感じですが、しかしながら実際に体験しないと分からないだろうと思ったりします。
先日友人と話していて、nature positiveという言葉が出てきました。今の気候変動問題と関連して、これからはnature positiveとあることが重要だろうということです。nature positiveとは初めて聞いたので真意は分かりませんが、それと身体性を結びつけてこんなことを考えました。
nature positiveの一つのあり方は、気候変動で産業も日々の暮らしも影響を受けるから自然の偉大さを自覚して共存していこうとする、人間の利を考えてのものです。これを仮に功利主義的nature positveと呼んでおきます(あくまでも僕による区分けです)。一方で、日々虫や植物なんかと戯れていて、そこに美しさやかわいらしさを感じることもnature positiveであると言えると思います。こちらは審美主義的nature positveと呼んでおきます。自然が人間に利があるからとか関係なく、自然やそこに生きる生物の存在自体を大切だと感じるこころのあり様です。
どちらのnature positiveも、自然と共生しよう、自然や地球を大事にしようという結論は同じだと思います。しかしその動機は明らかに違います。そして、なんとなく、功利主義的nature positiveは本で学び考えることによって、審美主義的nature positiveは身体的に学び考えることによって得られる主義・価値観なのではないかと思っています。草木を分けいり、ミツバチが花に入り込んで蜜を採集しているところを見る。それを見てかわいいと思う。これは図鑑でもその感覚を抱くのは難しく、やっぱりミツバチと同じ環境に身をおいて、刺されないように慎重に近づいてじっと観察するからこそ得られることではないかと思っています。
何が言いたいかというと、本から得られることと身体的に得られることとはやっぱり違っていて、そこから生まれる価値観やものの見方も違うのではないかということです。双方は補完し合うという意見も出て確かにそうだと思います。ただ、補完はし合うのだけど、違う。身体的にしか得られないものはあるし、本からしか得られないものもある。そんなことの正体を追ってみたいなと話していて改めて思いました。
2024年11月20日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『地下室の手記』ドストエフスキー
おとこが食事会の集合時間の変更をたぶん故意にをしらされていなくて仲間にもはいれなくてきまずいけど負け惜しみを心の中で言っていて。お金もなくて。集団で歓迎されなさ過ぎて男の立場になってしまい、いたたまれなくなりました。
2024年11月13日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『現象学入門』竹田青嗣
〈私〉は何かを判断するときに何らかの確信をもとに判断しているのだと思います。例えば、①殴られると痛い②痛いのは嫌だ③嫌なことはやってはいけない④だから殴ることはやってはいけない、というような思考のもと④の判断をしたりしています。思考といっても、これはもはや常識として捉えられていて意識的に思考することもないはずですが、根拠を尋ねられると①〜④のように説明することができます。そしてその時、①〜③は確信です。人によって違うとか、もしかするとみたいな可能性の話とかそういう次元のものではなく、確信です。その確信は、自分だけでなく誰もが確信として共有しているものであり、異論の余地がないものとして捉えています。つまり、主観ではなく客観であるということです。
しかし、それぞれに反論をすることはできます。①の反論:殴られても痛くない、②の反論:痛いのは嫌ではない、③の反論:嫌なことをやってはいけないわけではない、などということです。①なんかは、格闘漫画でたまに出てきますよね。痛いというのは脳がそう認識しているからでその認識を書き換えれば痛いものが痛くなくなるのだ!なんていう血管が浮き出たキャラも出てきます。あるいは、②の反論も単なる強がりではなく、本当にそう思っている人もいるかもしれません。痛いというものではなくても、ハードなトレーニングをすることで自己を保てるみたいな人もいると思います。僕もスポーツをやっていたときは、そんな心持ちであったような…。
つまり、誰もがそう確信している客観的真実だと思っていることがあって、それをもとに生きているわけですが、それはやっぱり主観性を拭えないということです。いくらでも反論できますし、①〜③の反論を実践する人がいないことを証明することは困難です。だけれども、〈私〉はその主観的客観を確信としてもって生きています。では、なぜそれを確信としてもっていられるのか、確信とはどのようにして生まれるものなのか、そんなことが現象学のテーマなのだと思います、たぶん。客観なんてない、と言って結論とするのではなく、なぜ客観というものをもてるのか、主観のなかに生きている個々の人間がなぜ確信として何かを共有し連帯できるのか、みたいなことへの答えなのかもしれません。迷走しながら読んでいるのでまだわかりませんが…。
2024年11月10日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん『地下室の手記』ドストエフスキー
地下室の手記の読んだところを説明していると、ライムギのホールデンみたいだという感想をいただきました。みんなにすかれたいとおもっている。うそとかきらい。がんばってね。とかいわれるといらつく。自分の顔が阿呆ずらにみえてくるところは太宰治の「人間失格」を連想しました。じめじめしたぼた雪のような話です。
2024年11月5日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『現象学入門』竹田青嗣
まだ序盤です。印象に残ったのは認識コンピューターの話でした。
人は、外にある対象物を見たり聞いたり触ったりして「こんなものがある」ということを認識します。しかし、その際にダイレクトに対象物を認識しているというよりも、認識までの過程でさまざまな処理がされています。例えば、氷を触って冷たいと思う。この時に起きているのは、指で触って指の皮膚になるセンサーのようなものが情報を受けとって信号として神経に伝えて、その後もおそらくいくつかの神経を経由しながら脳に到達する。脳はその信号を受け取り、何らかの既にある基準に則って知覚する。そしてその知覚に「冷たい」という言葉が適切だと判断しその言葉を当てはめる。
この過程は僕の想像ではありますが、そのようないくつもの処理があって認識をするのが人だとしたときに、その処理過程はコンピューターにおけるプログラムだと置き換えることができます。そして、ではその認識は正しいのかという判断は、その処理=プログラムが正しいのかどうかということを検証できて初めて判断できます。
しかし、常にその既にあるプログラムを通してしか認識できない人においては、そのプログラムそのものが正しいかどうかを判断する術はないということです。人はものを正しくみることができるのか、主観を超えて客観で捉えることができるのかは、哲学の世界では大きなテーマであるということでした。現象学でもこのテーマにアプローチしているとのことで、どのようなアプローチと答えを出すのかこれから楽しみです。
2024年11月3日(土/午後):〈リベルの文化祭〉「労働」をテーマに話し合う会
よしださん
労働という多くの人がどこかで関わる概念(?)について話しました。賃金が発生する労働とそうでない労働がある、生活の糧と割り切って労働はするけど他にやりたいことがある、そんないろいろな話が飛び交いました。
言葉としては1つなのだけど、それぞれの人が思っていることは違う。これがリアルなのであって、現実というのは本当は多様で複雑であってこれこそリアル、という感じの時間であったのだと今振り返ると思います。
2024年11月3日(土/午後):〈リベルの文化祭〉秋といえば、保存食についてシェアする会
よしださん
梅干しを漬けている人が思ったより多いかも?と驚きました。もちろん、このような会に参加される方だからというのもあると思いますが、そういえば私の実家でも漬けている…。
干し柿は甘い柿だと水分が多くて干される前に腐るから渋柿しかできないはず、などというのは初耳の知識でした。そういえば、干すことで渋みも取れるはずで(正確には皮を剥くということが重要なようですが)、渋柿の最適な食べ方として保存食・干し柿のあるのだと受け継がれる知恵の偉大さを感じました。
いずれにしても、今年も柚子胡椒をはじめ、なにか保存食を作っていきたいなと思いました。いろいろな調理法を試行錯誤の上(そして数々の犠牲も…)確立してきた先人たちに感謝です。たしかに、ふなずしを最初に食べた人はどんな感想をもったのだろうか。
2024年11月3日(土/午前):〈リベルの文化祭〉ドストエフスキーとその作品の魅力
yuさん
マルメラードフの「自分は神に許されないと思っているからこそ神にゆるされる」は親鸞聖人の「悪人正機説」に通じるものがあるなと感じました。マゾッケがないと読めないのではという意見が面白かったです。少年イリューシャの飼い犬の名前はなんだったか昨日から考えていました。「貧しき人々」「地下室の手記」「悪霊」・・ドストエフスキーを読むきっかけになりそうです。
jscripterさん
ドストエフスキーはずーっと気になっているが、なかなか読めない作家です。問題意識をどう持つかに掛かっているのですが、今回の読書会に参加させていただいたおかげで、少し見えてきました。「悪霊」をまず読んでみると同時に、ニーチェの書簡集にドストエフスキーが出てくるそうなので、そちらも当たってみようと思います。
よしださん
僕はドストエフスキーの作品を読んだことがありませんが、おもしろくみなさんのお話を伺っていました。印象的だったのは、やはり(?)「なぜドストエフスキーを読むのか?」→「頭がおかしくなりたいから」という意見でしょうか。話が長くて、それぞれの登場人物のなかに矛盾があって、所作もおかしかったりするから頭がおかしくなる?ようです。その矛盾と複雑さに徐々にシンクロしていくということでしょうか。僕も科学書なり哲学書なりで常識を覆されたときに呆然としながらも楽しいと思ってしまう、その感覚に似ているのでしょうか。『悪霊』か『罪と罰』あたりを読んでみたいと思いました。
2024年11月1日(金/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
野中さん『男性危機』
伊藤さんによるジェンダー平等政策の解説が非常に秀逸だった。
yuさん『カラマーゾフの兄弟3』 ドストエフスキー
三部ゾシマ長老が死に人々が詰めかけて奇跡を待ち受けているところにありえないことが。聖人からは腐臭がしないはずが・・・。町中の人が注目している、人々は退屈していたのかなと感じました。
2024年10月30日(水/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
むしこさん『実践日々のアナキズム 世界に抗う土着の秩序の作り方』
本の感想では無いのですが、「推し活」とは何なのか、いろいろな観点から語り合ったのがとても面白かったです。この本を読まれた方の着眼点も大変面白くて、もっといろいろ伺ってみたかったです。
よしださん『想像力 生きる力の源をさぐる』内田伸子著
今日が読み始めですが、印象に残ったのは以下の部分です(P7)。
「五官を働かせて得た「直接体験」から抽象化された「経験」へと昇華する過程で、レジリエンス(ストレスを回復する精神的回復力)が高まってゆきます。」
正直、この記述に実感をもてるような体験は僕のなかに見出せませんでした。この本の冒頭はフランクルの『夜と霧』の紹介から始まります。『夜と霧』では、ナチスによる強制収容から生き延びたフランクルが、どのような人が生き残りどのような人が亡くなっていったのか記しています。そこには、精神面が生死を分かつ確かな記述がありました。読んでから時間が経っているので記憶もあやふやですが、外的な(絶望的な)世界に翻弄されるばかりでは生きられず、内的な世界を生きる時間をもち続けられた人が生き残ったような記述があった気がします。その内的な世界を形成するのが「経験」であるということなのでしょうか、あるいは形成した内的な世界自体が「経験」であるということでしょうか。想像力を生きる力と結びつけて考えたことがなかったので、興味深く読み進めていきたいと思います。
2024年10月22日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『エルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告』ハンナ・アーレント
僕の理解不足かもしれませんが、シオニストの人たちはナチスよりもイギリスを敵とみなしていた時期もあったと書かれていました。シオニストとはパレスチナにユダヤ人国家を再建しようとする人たち。当時パレスチナはイギリスにより支配されていたのか、シオニストの活動を阻む存在として忌避されていた。ナチスは、ドイツやオーストリアからユダヤ人を追い出そうとしているけど、この時点では殺戮までは至っていないから、どちらかというと悲願を阻むイギリスの方が敵であるということなのかなと理解しました。歴史は単純ではないなと感じました。
2024年10月19日(土/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『縄文時代の歴史』山田康弘著
定期的に読みたくなる縄文時代。今回も初めから読み返してみて、冒頭の縄文時代の概要を書いているところを読みました。
食料は燻製加工したり貯蔵庫を設けたりして保存する。建物は竪穴を掘って寒さと暑さを和らげる工夫をするなど、用途に応じた工夫がされた建築物を建てて生活をする。集落間のネットワークがあり、物や情報のやりとりをしている。集落間の関係をより堅いものにするために結婚制度を設けて嫁や婿をどちらかの集落に住まわせる。
これらは、縄文時代に確立されていた慣習なのですが、さて今とどこに違いがあるのかというと、、と思って考えていました。
便利さや快適さを追求しようとする方向性は時代や文化を違えてもあまり変わらないのかもしれません。結婚をして関係を堅くするというのも、血縁のもつつながりの力を示していて、近現代とあまり変わりません。時代を超えた歴史を知ると、同じところと違うところが見えてきてやっぱりおもしろいなと思いました。
2024年10月8日(火/午前):読みたい本を気ままに読む読書会
よしださん『エルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告』ハンナ・アーレント
アイヒマンは整合性のないことを言います。さっきまで自分は絶対に宣誓をしないと言っていたのに、いきなり宣誓すると言い出したりする。それの矛盾に気づいていない。本の中の表現を借りれば、紋切り型の発言に終始している。紋切り型だから、状況や周りの反応やさっき話した自分の話に対して調節が効いていない。自分と、外の世界とのあいだのコミュニケーションが成立していないように思いました。
アイヒマンはナチスにおけるユダヤ人の国外移住へ加担していました。移住といえば聞こえはいいですが、国内からの追放であり、ユダヤ人は自身の国内の全財産を放棄することになった上に必要な外貨も法外な為替レートで押し付けられたのだとか。アイヒマンは、自分の子供に自分はユダヤ人が殺されるのを国外移住させることで防いだのだと武勇伝のように語っていたのだとか。そしておそらく子供もそれを信じていた。閉じた世界の自分に都合の良い完結した物語ができていたということなのでしょうか。
2024年10月6日(日/夜):読みたい本を気ままに読む読書会
yuさん「ロシア文学の教室」文学界2023年6月号 奈倉 有里 (著)
第6講 布団から出たくないイワン・ゴンチャロフ『オブローモフ』紹介の回を読みました。
大学2年生のロシア文学の授業形式で書かれた小説です。
この授業では、あなたという読者を主体とし、ロシア文学を素材として体験することによって、社会とは、愛とは何かを考えます」山を思わせる初老の教授が、学生たちをいっぷう変わった「体験型」の授業へといざなう。オブローモフは上中下とあり、上巻では主人公は布団のなかからなかなかでてこない話のようです。だんだん主人公のような行動をしてみたいと作中の人物の気分がうつろっていました。なにが大事なことなのかと考えさせられるような本かなと思いました。